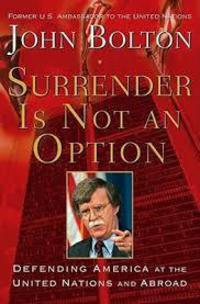・読者登録
・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル
・コラム
・みる・よむ・きく
・インタビュー
・解説
・こぼれ話
特集
・国際
・政治
・核・原子力
・入管
・アジア
・検証・メディア
・欧州
・人権/反差別/司法
・市民活動
・反戦・平和
・みる・よむ・きく
・中東
・環境
・文化
提携・契約メディア
・AIニュース


・司法
・マニラ新聞

・TUP速報



・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus
・星日報
Time Line
・2026年02月21日
・2026年02月17日
・2026年02月16日
・2026年02月14日
・2026年02月10日
・2026年02月07日
・2026年02月06日
・2026年02月05日
・2026年02月04日
・2026年02月01日
|
|
2016年11月16日15時04分掲載
無料記事
印刷用
国際
トランプの次期国務長官? ジョン・ボルトン元米国連大使 平田伊都子
2016年11月11日、トランプ政権移行チーム5人の顔写真が発表されました。 トランプJr(長男)、イヴァンカ(長女)、クシュナー(娘婿)、エリック(次男)、その中に、ジョン・ボルトンの顔を見つけました。 [やった〜!]と、声を上げてしまいました。 じっくり読み返したくて、翌日、BBC、ロイター、CBS、ABC、ハーレツ、、と探しまくったのですが、どこにもジョン・ボルトンの顔も記事も出ていない、、出てくるのは、トランプ次期政権幹部・スティーブン・バノンという悪名高い超右翼の噂ばかり、、あれれ?トランプはボルトンを外したのな??
ところが11月15日、トランプ政権の国務長官候補として、米国紙ナショナル。レヴューやイスラエル紙ハーレツなどがジュリアーニ元ニューヨーク市長と共に、ボルトンの名前を挙げていたのです。 同時テロ9・11の火消し役をニューヨーク市長として務めたジュリアーニと、お父さんが元消防士だったボルトン、、この国務長官候補二人の暴言の火消しは、誰がやるのでしょうか?
(1) ジョン・ボルトンって?:
ジョン・ボルトンはイラク民衆の敵だ。2003年のイラク戦争を仕掛けた、ブッシュ政権ネオコンサーバティブの超強硬派だ。この一派は、ありもしない大量破壊兵器の偽造証拠写真を広げて国連を騙し、イラクを空爆し、100万近いイラク民衆を殺し、300万近いイラク民衆を難民にした。アメリカはイラクの国土を破壊し、イラク大統領フセインを吊るし首にし、2016年の今も、なんのかんのと理由をつけて、イラク爆撃を続けている。明らかに、アメリカは戦争犯罪を犯している。ICC国際犯罪裁判所のお裁きを受けるべきだ。ところが、ジョン・ボルトンがアメリカをICCから脱退させ、各国と個別に二国間協定を結び、アメリカ兵の犯罪を一切問わせなくしてしまった。国連無能論、反移民、おや?トランプそっり??それもそのはず、トランプ大統領選の外交政策はボルトンが指導していたという。トランプが共和党の指名を受けてから、ボルトンはずっと支援している。
ジョン・ボルトンJohn Robert Bolton、は1948年11月20日にアメリカのメリーランド州に生まれる。イエール大学法学部卒業後、法律事務所に勤務し、、1981年のレーガン政権の8年間、国際開発庁および司法省に勤務し、1989年から1993年まで、父ブッシュ政権で国務次官補を務める。担当は対国際連合。クリントン政権の外交政策に対して一貫して批判を続け、。2001年、息子ブッシュから国務次官(軍備管理・国際安全保障担当)に任命される。北朝鮮との六者会合やイランの核開発問題などを担当した。2005年、ブッシュ政権は民主党や共和党穏健派の反対を押し切って8月に国連大使任命を強行した。が、上院が承認しなかった為、2006年12月4日に退任した。「国連などというものはない。あるのは国際社会だけで、それは唯一のスーパーパワーたるアメリカ合衆国によって率いられる」とか、「国連本部ビルの最上層10階分(事務総長執務室など幹部の部屋がある)がなくなったとしても何ら困る事はない」とか、、国連を罵倒する暴言が多々ある。在任中は北朝鮮とイランを激しく批判し、両国に対する強硬路線を主導した。
(2) ボルトンと日本の深い仲:
ボルトンと、北朝鮮を糾弾してきた安倍晋三首相とは、首相が内閣官房副長官時代から深い繋がりがある。
2006年7月5日に北朝鮮が行ったテポドン2号発射及び、同年10月9日に強行された核実験の後は安倍晋三内閣官房長官(当時)や麻生太郎外務大臣(当時)と共に北朝鮮への制裁路線を推し進めた。さらに、10月15日には対北朝鮮制裁決議の採択を実現する。バンコ・デルタ・アジアの北朝鮮の不正資金凍結も断行した。拉致被害者家族からも信頼され、2007年11月に拉致被害者家族連絡会が訪米した時には最初に面会し力づけた。さらに、北朝鮮の脅威に対抗するために、日本と韓国が核武装を検討することを主張している。この日本韓国核武装案はトランプの選挙演説に符合する。以下に、北朝鮮と拉致問題に関するボルトンの発言を紹介してみる。(ウィキペディア参照)
「拉致問題が解決するまでは、米政府による北朝鮮のテロ支援国指定解除は交渉すらすべきでない」
「6か国協議における合意は完全な失敗であり、最悪の取引だ。北朝鮮が核を放棄することはあり得ない。こんな合意はならず者政権の指導者たちに、米国の交渉担当者を疲れさせることが出来たら、褒賞がもらえるということを教えるようなものだ、、、北朝鮮は約束を守らないだろう。彼らはあらゆる口実を用いて交渉を引き延ばし、更なる代償を求めてくる」
ちなみに、11月15日の国連総会第3人権委員会は北朝鮮の人権侵害を非難し、日本人を含む拉致の解決などに向けた対応を求める決議案を採択した。北朝鮮国連代表部のキム大使を含む3人が記者会見を開き、決議に反発し日本と韓国を非難した。トランプ次期大統領に関しての質問に、「北朝鮮は誰がアメリカ新大統領になろうと構わない。要は早く北朝鮮に関する敵愾心をアメリカが取り除くことだ」と、北朝鮮代表部は答えた。
(3)ボルトンと国連西サハラ住民投票:
国連大使になったら真っ先にやろうと決心していたのは国連西サハラ住民投票だと、ジョン・ボルトンは語っていた。ボルトンが2007年に出版した「Surrender is not an option(降伏は選択肢の中にない)」から、ボルトンの国連西サハラ住民投票に対する熱い想いを引用していく。
*(2章45ページ)1997年から2001年にかけてコフィ―・アナン(当時の国連事務総長)がジェームス・べーカー(元米国務長官)に、アフリカ西岸にある元スペイン植民地西サハラの問題解決を目指す個人特使を務めることを要請した、、、、ベーカー派遣団は、1991年に国連安保理が決めた国連西サハラ住民投票を行なおうとした。その住民投票とは、モロッコへの帰属か西サハラ独立かを西サハラ住民が選ぶ二者択一の選挙を指し、1975年以来の長期にわたる懸案事項に対する解決策だとされていた。
*(7章198ページ)アナンは治療中の腕を三角巾で吊っていて動き辛そうにしていた。我々(ボルトンとアナン)は西サハラについて見解を交わした。PKOを派遣して15年にもなろうとしていたのに(2006年当時)、この問題はまだ未解決のままだった。
*(9章246〜247ページ)私が非公式協議室(国連安保理の)で、<サハラに関する1997年ヒューストン合意>の最後の報告をしたのは、ベーカー個人特使にお供した時だった。その時、「私の目標の一つは、国連西サハラ住民投票実施のPKOを展開させて、この長期懸案事項を締めくくることにある」と、提案した。
*(13章367~69ページ)ブッシュ第41代大統領政権とジム・ベーカーの西サハラ紛争解決という二つの大仕事の恩恵は計り知れない。とりわけ、国連が約束した国連西サハラ住民投票を実施して西サハラ住民に彼らの将来を決めさせ、15年間のPKOに決着を付けることに、私は執念を燃やした。それに、反対しているモロッコも住民投票を呑んだのだから、、
真剣に国連西サハラ住民投票に取り組もう。取り組まないなら、安保理は失敗を認め手を引け、、つまるところ、MINURSO(国連西サハラ住民投票監視団)というPKOは、高い代償を払っている国連PKO活動の完璧な失敗作と結論づけられる。紛争解決どころか、紛争を長引かせるに過ぎない<無用の長物>と断言できる
イラク民衆に対する罪を償うかのように、西サハラ民衆をボルトンは援護している。
COP22に関して、<獲らぬ狸>の国連事務総長とオランド仏大統領は、「一旦パリCOP21を締結したのだから、アメリカは4年間拘束される」と、言い張っています。 しかし、「4年の拘束期間なんて糞くらえ!3カ月で脱退して見せる」と、トランプ陣営は豪語しております。 可能です。 なんたって、ICC や他の国際機関から短時間で米国の脱退を成し遂げたジョン・ボルトンが、トランプ外交の指南役を務めているのですから、、
時に、トランプ大統領誕生に大きく貢献したウィキリークス生みの親ジュリアン・アサンジの記者会見 見ました?
エクアドル大使館で同棲している猫がネクタイで盛装して、代役を務めていましたね、、
トランプ大統領閣下、NSA(国家安全保障局)長官にアサンジをお勧めします。正式移民にすることを忘れないでくださいね
文:平田伊都子 ジャーナリスト、 写真:川名生十 カメラマン
|
転載について
日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。
|
|
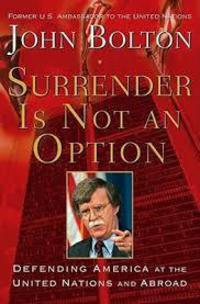
ジョン・ボルトン著書「Surrender is not an option」の表紙


|