


|

|
|
�����ι��ɤΤ����� �����Խ��Ѱ������פ��罸 ���ܾ�21�������ɳ�����
����� ������������ ������� ���ߤ롦��ࡦ���� �����ӥ塼 ������ �����ܤ��� �ý� ������ ����� ������ �������� �����ڡ���ǥ��� ������ ���ˡ������� ����/ȿ����/��ˡ ����̱��ư ��ȿ�ʿ�� ���ߤ롦��ࡦ���� ������ ���Ķ� ��ʸ�� ��ȡ������ǥ��� ��AI�˥塼��   ����ˡ ���ޥ˥鿷ʹ  ���ԣգ�®��    �����㤫�뤿��ʹ ��Agence Global ��Japan Focus  ��Foreign Policy In Focus �������� Time Line ��2026ǯ02��10�� ��2026ǯ02��07�� ��2026ǯ02��06�� ��2026ǯ02��05�� ��2026ǯ02��04�� ��2026ǯ02��01�� ��2026ǯ01��31�� ��2026ǯ01��30�� ��2026ǯ01��29�� ��2026ǯ01��28�� |
������������� ��壸��ǯ�������������ä��Τ����ե���ԥͥ������������ʼ  �������ʹ8������椬�ե���ԥͥ�������ˤ���������ܷ�ʼ�Τ���Ʈ�ˤĤ��ƽƤ���(��20�嵭�Ԥ������Ѥ������)��25�Фμ�국�Ԥ�ʪ����¤���ʼ�Τ��Ʒ��ε����ݼͤ�ƨ���Ǥ��������Ȼ��Ǥ��ä������ȥ�����Ȫ�˱��졢�������Ӥ�ƨ���������ӡ����Ԥ��������οͤη��ϥե���ԥѥʥ������ष�����������¶��ˡ�2025/08/12��
�������ʹ8������椬�ե���ԥͥ�������ˤ���������ܷ�ʼ�Τ���Ʈ�ˤĤ��ƽƤ���(��20�嵭�Ԥ������Ѥ������)��25�Фμ�국�Ԥ�ʪ����¤���ʼ�Τ��Ʒ��ε����ݼͤ�ƨ���Ǥ��������Ȼ��Ǥ��ä������ȥ�����Ȫ�˱��졢�������Ӥ�ƨ���������ӡ����Ԥ��������οͤη��ϥե���ԥѥʥ������ष�����������¶��ˡ�2025/08/12��
������ �ڹץƥ�����ϥ��ƥå�Ʈ��˽����ʤ�����̱�粽Ʈ���  ���Ƥ����줿�Ҳ�����ŷ���˰�ͤ�ϫ�Ȱ�������ƾ��³�������̸��ؤβ����������뵵���δڹץƥ�����ϥ��ƥå�����ε�ٷƽꡣ�����˰�ͤν����������������ȥ���ס����������Υ��åȤ��������ǰ����桢�Ҳ���į��Ƥ��롣�ʰ��Ĺ�����2025/07/26��
���Ƥ����줿�Ҳ�����ŷ���˰�ͤ�ϫ�Ȱ�������ƾ��³�������̸��ؤβ����������뵵���δڹץƥ�����ϥ��ƥå�����ε�ٷƽꡣ�����˰�ͤν����������������ȥ���ס����������Υ��åȤ��������ǰ����桢�Ҳ���į��Ƥ��롣�ʰ��Ĺ�����2025/07/26��
��� �ȥ��פȰ��ܡ����ꥹ�ȶ�ʡ���ɥʥ���ʥꥺ��ȹ�ȿ�ƻ���ťʥ���ʥꥺ������� �ȥ��פ� MAGA �äơ��ΰ��ܤ� ���ܤ����᤹ ��Ʊ���ʤ����(���Ĺ���)��2025/05/31�� �ϰ� �ڻ�Τ����ۥ��ᡢ��ǯ³�����Ժ�ͽ�ۤ�  ������ư�ϥ���ˤ⡣��ǯ�Ϥɤ��⥦��Ժ�ǡ��ߴ��������������ʤ��;夬�ꤷ�Ƥ��롣��ǯ��ʤ����������������ʥ���ˤޤĤ�뻰��ȸ���������¶��ˡ�2025/03/26��
������ư�ϥ���ˤ⡣��ǯ�Ϥɤ��⥦��Ժ�ǡ��ߴ��������������ʤ��;夬�ꤷ�Ƥ��롣��ǯ��ʤ����������������ʥ���ˤޤĤ�뻰��ȸ���������¶��ˡ�2025/03/26��
���ȿ� ������Ȥ����ˡ����Σ����ص�˳����¼�٤��ɤ� �ܤλ�������������ͺ�� �ص�˳����¼�٤�Ф����ɤ��֤��Ƥ��ޤ�������������ü��ȯ�������¶���������¼���Ŀ����鲬���ޤ��⤤��Ƨ�����Ǥ�����̾����ƮŪ�ޥ륯���кѳؼԤ�ͥ�줿���㡼�ʥꥹ�ȤǤ⤢�ä����Ȥ����ƻפä���⤷�Ƥ��ޤ���(�����¶�)��2025/03/11�� ������ �ڹ³���ã�����Ҳ�Ūʬ�� �Ƕ�δڹ���ɤ뤬���Ƥ����ü�ʼҲ�Ū��Ω�Ϻ������������̴ط���ᤰ��Ť��������Ω���Ⱥۤ�̱�粽��ư����Ω���طʤȤ��ơ������椬Ƴ����������ͳ������к�Ū����Ω�����ߡ���������ݷä��̤��Ʒ������줿���ø�����פȽ�̱����Ω�϶˸¤�ã���롣�ʰ��Ĺ����ˡ�2025/02/07�� ������ ����٤θ�α��Ĺ�����Ѳ����ʤ�Ȥʤ������Ȥ��ʤ����ɡ����ܤοͼ���ˡ����٤�Ф�ۤɥޥ� ����٤˴ؤ������ܤ���ƻ�Ƥ�ȡ�������פ��ֹ�«�פ��˴ؤ����Ѹ줬���𤷤ޤ��äƤ롣1��17���Υ˥塼���ˤϡ�����٤����������פߤ����ʵ������¤�Ǥ������ɡ����㡢1��15���Ρ�����פϲ����ä���?�äƤ��Ȥˤʤ롣�ʰ��Ĺ����ˡ�2025/01/27�� ������ �ڹ�̳�¶����ǤΥ�������Ҷ����Ρ��ʤ��������餱�� ���줫���Ĵ���Ǥ狼�뤳�Ȥ����ɡ� ̳�¶����λ��Τθ����ˤĤ��Ƥ���������ƻ����Ƥ뤱��ɡ��ʤ�ɤ�����餱���ʰ��Ĺ����ˡ�2024/12/30�� ���ȿ� ���¶�������ʪ���ʡ�����줿����ǯ��ϫ�¤��������Ʋ��Ⲽ����äѤʤ����ä� ������������ʤ���ߤޤꤷ�Ƥ��ޤ������βơ������ʤꥹ���ѡ����饳��ä���Ȥ������֤���ȯ�������¤�����ư�ɤ������ˤʤ�ޤ�������ɤ�����ʤϡ֤ʤ��ˡ��������ܤˤʤ�п��Ƥ��в��ޤ�������Ū�ʤ��ȤǤ���פȤ��äƤ��ޤ��������θ����̤ꡢ���Ƥ˻������褿�饳���ŹƬ����äƤ����ΤǤ��������ʤϾ徺��³������ߤޤ�Ȥ������Ȥˤʤäƺ��˻�äƤ��ޤ���(�����¶�)��2024/12/03�� �ߤ롦��ࡦ���� �ѥ쥹���ʤλ�����������������İ���ס��ظ������Ģ�٣���� ���������߽����������ˤ��뷧����Ź��ê�Ƥ�ʤ������Ĥ��Ƥ��ơ��դȡظ������Ģ�٤Σ������˼�ä��顢�ý��֥ѥ쥹���ʻ�����������������İ���פȤ���Τ��ܤˤĤ������������¶��ˡ�2024/05/14�� ����� <��Τ���魣��������������������������������� �����Ĥơ���������ë�ʺ�̸����㤫�鷲�ϸ���¿��ˤ����Ƥ��ϰ�ˤ�11��ϡ���ǯ�Τ��餷���Ȥ��̤��븷�����������ۤȤ�ɤ����ӡ����̤ˤؤФ�Ĥ����ʡ�Ȫ�˰�仨������»���ܻ�������˥㥯�������Ƥ������������ʤ�ʬ��ޤᡢɬ�פʸ�����ܻ�������˥㥯�����ʤ���Фʤ�ʤ���������������भ�ȥ���˥㥯�ι�ʴ�ʥ���˥㥯��饤�����ƶ��˻ɤ��ƴ��礵�������å��Τ�ΡˤŤ��꤬�������λŻ����褦�äѤ��Ȥ��ä�����2024/04/12�� ���ȿ� ��61ǯ�ܤ����ȵ��ԡ� ��Τ�ͤȥ���ɼ������ࡡ�����������¶�  ���⤦10���ۤɤ����ˤʤ�ޤ�����3�������������������줳��Ⱦǯ�֤�ǻ�Τ�ͤ�ˬ�ͤޤ�������ǯ�ν��μ�ޤ���������Ȫ���ɤ��ʤäƤ��뤫�˹Ԥä��ΤǤ�����֤ǥ���ɼ�������ȸƤ�Ǥ��뾮��Ȫ�Ǥ�����������˹�������ơ��������Ϥ��������Ϥ��Ф��Ȥ�����Ȥ�����ȴ����Ȫ�ΰ�����ֻȤäƤ�����פȽФ��Ƥ��줿��Τ��ɴ������������а湱�ʡˤ�Ȫ�Τ��ä����ˤˤ���Ϥ���ޤ�����2024/04/08��
���⤦10���ۤɤ����ˤʤ�ޤ�����3�������������������줳��Ⱦǯ�֤�ǻ�Τ�ͤ�ˬ�ͤޤ�������ǯ�ν��μ�ޤ���������Ȫ���ɤ��ʤäƤ��뤫�˹Ԥä��ΤǤ�����֤ǥ���ɼ�������ȸƤ�Ǥ��뾮��Ȫ�Ǥ�����������˹�������ơ��������Ϥ��������Ϥ��Ф��Ȥ�����Ȥ�����ȴ����Ȫ�ΰ�����ֻȤäƤ�����פȽФ��Ƥ��줿��Τ��ɴ������������а湱�ʡˤ�Ȫ�Τ��ä����ˤˤ���Ϥ���ޤ�����2024/04/08��
���ȿ� �㣶��ǯ�ܤ����ȵ��ԡ�Ϸɴ������ڥȥ��ȥ饯��������夲�Ƥɤ������ ����������ȿ��㡦��ۤ˹ԤäƤ��ޤ������⤦����ǯ����դ��礤�ˤʤ���ͭ�����ȸ�������֤����ޤꡢ�������Ȥ������Ȥǡ��ܤ������ʤΤǡ��ߤ�ʤȰ��դ��˹Ԥä��ΤǤ������θ���٤��ƽ�ȯ����������ȱDz�פ⤹�Ǥˣ���������ǯ�⣱����ˤ��ޤ����ܤ��Ϻǽ餫�����Ǥ���Τǡ��������̤⤢��ޤ������������¶��ˡ�2024/03/11�� ���ȿ� �ڣ���ǯ�ܤ����ȵ��ԡ۾���������֡פ��ɤ� �������ʲҤΣ���ǯ����ǯ�Ȼ������ֻ��ϰ���⤭���ϸ��οͤ����ˣ��ܤαDz��ޤ������ؽвԤ��λ��夫��٤��ꤹ��ɥ�����Ǥ�������ĺ��ʤǤ����������ʤ��Ȥˡ������λ�������ספǾ���ޤ���ޤ��ޤ�������룱��������Dz������Ȥʤä�����Į�Ǽ���ǰ�κŤ���������ޤ����������ʤ�̾��˥ʥ졼������̳��Ƥ���������Ĺë�ɧ����ˡ�����ůϺ�ξ���������֡פ��ɤ�Ǥ��������ޤ�����ϯ�ɤ⤹����������⤹���������ɤ���뤳�Ȥ��ᤷ�ޤ����������¶��ˡ�2024/03/01�� ���ȿ� �ڣ���ǯ�ܤ����ȵ��ԡ۹�ȫĮͭ������������ǯ��ޤ������������������ʤ��ʤä����������¶� �����Ȥ���¼��Ȥ������ȵ��Ԥ�̾��äƤ��Σ���ǣ���ǯ�ܤ�ޤ��ޤ������Τ����ۤܣ���ǯ�֤��������ȿ�ʹ�Ȥ����ۤȤ��ï���Τ�ʤ������Dzᤴ�������ȣ���ǯ�ϥե롼��ǡ��褯�ޤ��Ӥä������Ƥ���줿�ʡ��Ȥ����褦�ʻ����ᤴ���ޤ��������Σ���ǣ����Фˤʤꡢ�Ϥ����ǤǤ��礦�����ޤ⸽���̾��äƤ��ޤ����ؤ��Τϻ�λ�¼�Dzᤴ�����Ҥɤ�����ޤ������θ���ˤ����Ȥ������Ȥ���Ǥ�����������ȤΤۤȤ�ɤ��٤ƤƤ�������Ϥ���ޤ����ޤ�����ʤ��Ȥǡ����ȵ��ԣ���ǯ���ޡ��˰����դ��ʤ��顢���֤����̮���ʤ����פ��Ĥ��ޤޤ˥����Τ褦�ʤ�Τ�Ϥ���Ȼפ��ޤ�������������ꤤ���ޤ����裱���ͭ�����ȤˤĤ��ƤǤ����������¶��ˡ�2024/02/16�� ������ �ڴڹ�ǿ������������Ϳ�ޤ�������Ƚ�������Ȥ������Ⱦä��Ƥ����������Ĺ��� ���奸�̡��饤�֤������Ǥ��ڤ�줿������Ϳ�ޤ���������ޤ줿KBS�ʴڹ���������˿���Ĺ��Ǥ������Ϳ�ޤ��鼹ٹ�ˡ��и����ȡפȹ��⤵��Ƥ������Ȥ���λ������Ƥ��ޤä������奸�̤ϥꥹ�ʡ��ؤκǸ�ΰ������������ʤ��ޤޥ��Ӥˤʤä��Ȥ�����KBS����Ĺ�ϡ�����ޤ�KBS���и���ƻ��³���Ƥ������ȤˤĤ��ơ��й�̱�պ�פ�����ȡ���2023/11/23�� ������ �����Ǿ�����ɤ���١������Ĺ��� �����Ǿ���̤˴ؤ���˥塼����ή��Ƥ뤱�ɡ��ʤ�����褯�狼��ʤ����ǡ�����ι�ĥ�ǥ�������ƻ���Ƥ��¤٤��ɤ�Ǥߤ�����2023/11/21�� �ߤ롦��ࡦ���� ��ߤ��भ���䥢���ࡦ���ߥ���ͼ�����ä��Τ�ï������ Ĵ�����ʤ��ȥ�Ͽ����ʤ�����衪 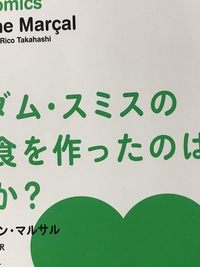 �кѳؤ���Ȥ����륢���ࡦ���ߥ��������ȿȤǡ������Ϥ�äѤ���Ƥ���äƤ��ޤ�������ϽФƤ����Τ٤�������Ȥ�������ηкѳؤˤϤ��Τ��Ȥ��������äƤ��ʤ����ܽ�إ����ࡦ���ߥ���ͼ�����ä��Τ�ï�����٤Ϥ������䤫��Ϥޤ�ޤ����������¶��ˡ�2023/07/26��
�кѳؤ���Ȥ����륢���ࡦ���ߥ��������ȿȤǡ������Ϥ�äѤ���Ƥ���äƤ��ޤ�������ϽФƤ����Τ٤�������Ȥ�������ηкѳؤˤϤ��Τ��Ȥ��������äƤ��ʤ����ܽ�إ����ࡦ���ߥ���ͼ�����ä��Τ�ï�����٤Ϥ������䤫��Ϥޤ�ޤ����������¶��ˡ�2023/07/26��
���ȿ� ������������� �����ȡ����������ʬ��ˤ��ȼ���������Ƥ��롣�����ǤϤȥꤢ�����ֿ������ݡ����ˤĤ��ƹͤ��롣�����饤�ʤǤ������ü��ȯ����������ƭ��ñ��͢����ʵ�ͤޤ�˲�ʤ��Ȥ����Τ��Ҵ�Ū���¤ʤΤ��������줬���ܤμ���Ψ���㤵��Ϣư�����Ȥ��������ʤ��Ȥ����̤˸���롣����Ǥ����äƿ��������Ϥ�夲����̱�ο�������ݤ��衢�Ȥ���������������⺸���������˶��Ф졢��Ȥ����̤ˤ�����롣(�����¶��ˡ�2023/01/08�� �ڤ���ݤݼ�ȯ�ۥ���ȥ��Ĺ�ءݤ��ꤤ���� ��ȯˢ��ض����٤����ʤ��Ʋ����������� �� ����ϥ���ȥ��ȯˢ��ض����٤����Ƥ���ԤǤ����Τϡ��ӡ�������Ǥ��ޤ����������ϡ�������פ���ȯˢ���ض����٤��äѤ����Ǥ��ޤ���̣��褯�ʤäƤ���Ȱ��Ѥ��Ƥ��ޤ�����2022/06/07�� ���ȿ� �ڥ�����ɴ����������Ȥ�����ƣƣ��Ϻ�ȣ����ͤ�ɴ���Ȥ����á������¶� ���ޤ����ߥ�����ˤ����6�Ȥ����ޤۤɿ���Ǥʤ��ä���������ˡ��������ֻ�ǣ����ͤۤɤΤ����䤫�ʽ��ޤ������ޤ������ֻ�ɴ����ή���TPP��ȿ�Ф���͡��α�ư����褷�ơ���ƣƣ��Ϻ������������¼���פ黳����ɴ���ε�ͤˡ��彣�����Ť�����̱��Ȥλ����ڰ줬����饤��ǻ��ä������ä��Ƥ�餪���Ȥ������Ǥ��������äΥ����ȥ�ϡ�ɴ����������Ȥ��ס���ս��ȸ���졢���Τ褦�˽ޤ�������2022/02/25�� ���ȿ� ����ޤ��郎���� �������¶��� ����ͭ�����ȸ����ư���Ф���70ǯ���Ƭ�����糫ȯ�˹����ơ����ϻ��פ�Ǥ��ƹ�Ȥ˿��ø������Ʈ����ĩ�����̱Ʈ�褬����ޤ�������Τ��Ʈ��ȸƤФ�뤳��Ʈ��˵��ԤǤ���ٱ�ԤǤ⤢��Ȥ�������Ⱦü�ʷ��Ǵؤ��³���ƺ��˻�äƤ���ΤǤ���������Ʈ�����椫�顢�ɤ⤦��Ĥλ�Τ��Ʈ��ɤȤ�Ƥ֤٤����꤬ͤ���ޤ줿���ȤϤ��ޤ��Τ��Ƥ��ޤ���2022/01/02�� ���ȿ� �������������¶� �����Ϥ�ɴ����ͧ�ͤ�����Τǡ������ˤ�����ʪ���������äƤ���롣���֤�������μ��������̣���Ҥ�������˼��Ȥ�ͣ�������ʪ�Ǥ����ܤޤ��ˤĤ��롣��2021/12/31�� ����� ����ʬ�����䡧�֣���11�פ���������ؤء������ȽФޤ���������ȯ���Υ���ѥ졼�ɡ� ����������̺ҤΡ֣���11�פ���ޤ�ʤ�10ǯ��ʡ�縶ȯ���Τϡ֥����������ȥ����뤵��Ƥ���פȤΰ��ܼ���ε����ȤȤ�ˤ֤��夲��줿��������ؤ����ޤäƤ��롣���������ʤ��Ҥdz��Ť����֤ޤ�Ƥ���ˤ⤫����餺��������ϡָ��ؤϤ��פȸ�����äƤ��롣���Υ����ʤ��������Ф��и���������̱����Ĺ�ϡ�������Ķ�μ����Ե��Ԥ����ӱۤ���¨�������и��Ȥ����С��Ķ�����ä�2014ǯ����ȯ���Τν����ǽФ������ڤ������¢���ߤη��ߤ�ᤰ���ϸ���̱�Ȥ�Ĵ���ǡ��ֺǸ�϶��ܤǤ���פȤΥ���ȯ���ǽ�̱�ε�������Ƨ�ߤˤ��ä���ΤǤ��롣�֤�������ä��餤����̱����ޤ��줿�餢���פȤ��Υߥ˥���Ϥ��ä����롣��2021/02/02�� ����� ����ʬ�����䡧�֥����륹�������ʤΤǤϡġץ����ʹ��ⴶ���Ԥν�ȯ�����飱ǯ�����ĤŤ��������б����ȡ�ʩ���Ѥ���㤤 �����������ʥ����륹�����Ԥι����ȯ�����飱ǯ���������������ȯ�ᤵ�줿��ΤΡ��������礬�ĤŤ��Ƥ��롣�����ؤ��ȯ����Ĺ����㳰�ǤϤʤ��������������Ф��ˤ����к��ϸ����餱�ǡ�������ֹ�̱�ؤΰ��Ϥʤ���������ס��֥����륹�������ʤΤǤϡġס��֡�������س��Ťϥ����ʤ��Ǥ����ä��ڡ٤ʤɤȿ�������äƤ����礫���ס�����ʹ�̱�������夲���ȡ�ʩ���Ѥ����ܤȤΰ㤤���ǧ���Ƥߤ�����2021/01/17�� ����ʬ�����䡧������ʿ�¤��㤦���ȤϽ���ʤ��ס���¼ů��դΰ���� �����ե��˥�����οͤӤȤȶ��ˡ֤��Τ������פ�ĤŤ������Σǣϡ֥ڥ������פ���¼ů��դ����Ƥ��ͤ�Ƥ���1ǯ�����Ϥ�����ΤĤɤ��������졢�ब�ᤶ����������ʿ�¤��㤦���ȤϽ���ʤ��סʤ����ޤ����ˤ�����������Ѥ����Ȥ��������夬�ä������ܤǤϡ�̿����餷��̵�뤷��ʿ�¹�Ȥ�Ƥ�����ΤǤ�������̤ι�פˤ��褦�Ȥ��븢�ϼԤ�����ư������®���Ƥ��뤬���οͤΰ�֤������Ѥ���뤫���ꡢ̤��ؤδ�˾�ϼ����ʤ�����������2020/12/09�� ����� ����ʬ�����䡧 ��������ա��ɤ�ĩ����������������ϽС��������������äη��֤ᤶ�� 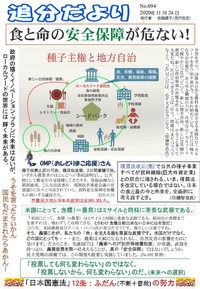 �����ܤ��������Υ١�����ץ��ˤ�äơ�����̿�ΰ����ݾ㤬��������Ƥ��롪���Ǥ⤽�ΰ����ǡ��ּ������ꡢ�����ϤΤ�����¼�����褵����¿�ͤʥ�������ա��ɤ���Ф��Ȥ��������ޤ�Ϥ�Ƥ���ס���������ա��ɤؤ�ĩ��ϡ��ֹ�̱��ʬ�ǡפȤ���������������ΰ仺��������Ρּ����פ�������ơ����������������ϽФȿ������������äη��֤�Ĥ��뤳�Ȥ�ᤶ���Ƥ��롣��2020/11/28��
�����ܤ��������Υ١�����ץ��ˤ�äơ�����̿�ΰ����ݾ㤬��������Ƥ��롪���Ǥ⤽�ΰ����ǡ��ּ������ꡢ�����ϤΤ�����¼�����褵����¿�ͤʥ�������ա��ɤ���Ф��Ȥ��������ޤ�Ϥ�Ƥ���ס���������ա��ɤؤ�ĩ��ϡ��ֹ�̱��ʬ�ǡפȤ���������������ΰ仺��������Ρּ����פ�������ơ����������������ϽФȿ������������äη��֤�Ĥ��뤳�Ȥ�ᤶ���Ƥ��롣��2020/11/28��
����ʬ�����䡧̱�����Ȥϡ������Ϥ�Ȥ�ʤ���Ρסʥϥꥹ�����ƹ��������Ρˡ��ֹ�̱�����Ǥ����Ϥ�ɬ�סס����ܹ��ˡ��  �������ؤ��ȯ�Ԥ������ۻҤ�����Ĺ��ڰ���Į�����ϡ������դ������������Ť��ʻ���餷�λ�ϡ���ư�Ȥ������դǤ�ɽ������ʤ��������ư���ˡ��Ĥ��Ƥ����Τ����ѡ��Ǥ������Ǥ⡢���ˤʤ뤳�ȤФ���פȤ������������γؽѲ��Ǥ̿���ݤ⤽�ΤҤȤġ�̱�����ΰ�������ˤɤ�Ω���������٤�����ͦ����Ϳ���Ƥ��줿�Τ����֥���ꥫ��̱�����������Τ�ΤȤ��Ƽ����ߤ��ΤǤϤʤ������Ϥ�Ȥ�ʤ���Τ��פȤ������ƹ�Υ��ޥ顦�ϥꥹ�����������Τξ������⡣���ܹ��ˡ12��֤��η�ˡ����̱���ݾ㤹�뼫ͳ�ڤӸ����ϡ���̱�����Ǥ����Ϥˤ�äƤ�����ݻ����ʤ���Фʤ�ʤ��פ��̤��복ǰ�ʤΤ�����2020/11/18��
�������ؤ��ȯ�Ԥ������ۻҤ�����Ĺ��ڰ���Į�����ϡ������դ������������Ť��ʻ���餷�λ�ϡ���ư�Ȥ������դǤ�ɽ������ʤ��������ư���ˡ��Ĥ��Ƥ����Τ����ѡ��Ǥ������Ǥ⡢���ˤʤ뤳�ȤФ���פȤ������������γؽѲ��Ǥ̿���ݤ⤽�ΤҤȤġ�̱�����ΰ�������ˤɤ�Ω���������٤�����ͦ����Ϳ���Ƥ��줿�Τ����֥���ꥫ��̱�����������Τ�ΤȤ��Ƽ����ߤ��ΤǤϤʤ������Ϥ�Ȥ�ʤ���Τ��פȤ������ƹ�Υ��ޥ顦�ϥꥹ�����������Τξ������⡣���ܹ��ˡ12��֤��η�ˡ����̱���ݾ㤹�뼫ͳ�ڤӸ����ϡ���̱�����Ǥ����Ϥˤ�äƤ�����ݻ����ʤ���Фʤ�ʤ��פ��̤��복ǰ�ʤΤ�����2020/11/18��
ϫƯ���� �ֲ��ϫƯ�Ԥθ�������פ����ߤ˸����ơ� �����ܼҲ��ǯ��������֤��ݤ��ꡢ���ؤμ��פ�����������ʤΤˡ����ϫƯ�Ԥ��ϰ̸�����١��Ȥ��ƿʤޤʤ����Ż��ˤ�꤬������ä�Ư���Ƥ�����ϫƯ�Ԥ������¼Ҳ�ˤ������������פ�ָؤ�פ��褵�졢���Ȥ���ϫ��³���Ƥ��롣����ʲ��ϫƯ�Ԥ����ѼԤ������������Ť����ᤶ���ơ��غ�����������ԡ����礦�������㡦���ϫƯ�Ԥ�������������Ҳ�ء��ֲ��ϫƯ�Ԥθ�������פˤĤ������٤����Ǥä����ޤ꤬�⤿��롣�ʴ���͵Ƿ�ˡ�2019/06/27�� ���ȿ� 1�ͤμ������ɴ�������ʤ��ʤä����������¶� ����������������Ȥο�ˬ����˴���ʤä��������ä������κ�����ī�����ŤǤ���ʶ�Ĥ�������2019/04/08�� ���� �ޤ��ޤ�³��������ǥ��Gilets jaunes�ʲ������٥��ȡˡס���Ryoka ( ��ʩ��  ���𤬤��ä������٥�˵�������ƤǤ��ʤ��ä��֤ˡ��ե�Ǥϥޥ������������Ф���ǥ⤬˽�̲��������ޤ뵤�ۤ��ʤ�����������ǯ������������鳫�Ϥ����ǥ�ϡ�SNS�ʤɤ��̤��ƣ������ܤ���������ǰ�˽������졢�����Σ����������ǣ����������ꡢ�������ͤ����ä���������ܥ�ϡ����٤Ƥμ֤������դ���ƻϩ��ǤΤ������ʤ���ߤκݤ���뤳�Ȥ���̳�դ����Ƥ���ָ������ä��ֲ������٥��ȡס�����ˤ��ʤ�ǻ��üԤ�ǥ⤽�Τ�Τ��Gilets jaunes�ʥ��졦���硼�̡Ძ�����٥��ȡˡפȸƤ֡���2018/12/05��
���𤬤��ä������٥�˵�������ƤǤ��ʤ��ä��֤ˡ��ե�Ǥϥޥ������������Ф���ǥ⤬˽�̲��������ޤ뵤�ۤ��ʤ�����������ǯ������������鳫�Ϥ����ǥ�ϡ�SNS�ʤɤ��̤��ƣ������ܤ���������ǰ�˽������졢�����Σ����������ǣ����������ꡢ�������ͤ����ä���������ܥ�ϡ����٤Ƥμ֤������դ���ƻϩ��ǤΤ������ʤ���ߤκݤ���뤳�Ȥ���̳�դ����Ƥ���ָ������ä��ֲ������٥��ȡס�����ˤ��ʤ�ǻ��üԤ�ǥ⤽�Τ�Τ��Gilets jaunes�ʥ��졦���硼�̡Ძ�����٥��ȡˡפȸƤ֡���2018/12/05��
�ˡ������� �ؿ�����Ϻ������������ؤ���ߡ٤��ɤࡡ��ʼ����ȯ�Ť�����ʤ�����ءֿ���ȳˤ϶�¸�Ǥ��ʤ��פλ���(1)��������˧ɧ ��ɮ�Ԥ�8��6�����鸶�����ػ߱�ư������������λ��ۤȱ�ư����Ƭ��Ω�äƤ���������Ӥ���(1994ǯ1�92�Ф��µ�)ů�ؼԤο�����Ϻ��䤷���ֳˤȿ���϶�¸�Ǥ��ʤ��ס��ֳˤϷ������ѤǤ���ʿ�����ѤǤ����ϵ��οʹ֤���¸�����ꤹ��פ��Ȥ�Ȥ�������촬�ˤޤȤ�ؿ�����Ϻ��������������ؤ���ߡ�(���縶��ط���40ǯ��ǰ���ȴ��Ѱ���1994ǯ3��̿�Ҵ�)���ɤ�Ǥ��롣ɮ�ԤϿ��������̾�丶�����ػ߱�ư�ˤ������פΰ�ü���Τ�ʤ��顢��������ʤɤ��ɤ�Ǥ��ʤ��ä����繾��Ϻ���إҥ����ޡ��Ρ��ȡ٤���Ǹ���ر�ư�ˤȤäƤޤ��Ȥ˼���֤��ΤĤ��ʤ����¤ο��ﲽ��ʨ���Ȥ⤤������9�����ػ����ˤ����빭�縶�嶨��ɽ�����Ȥ��Ƥο�������ˤ�������¤λѤˤĤ��Ƥε��Ҥ˶������ݤ���ä��������������λ���ɮ�Ԥ��ΤϹ���ˤ��äƤ⡢�פ���̤�Ϥʡ����ɤ�����פȤ⤤���٤��������üԤȤ��ơ���������Ȥϱ��֤ˤ��ä��������ơ����θ�ο�������θ���ؤˤ����뿿���ʱ�ư��̤�������ռ�Ū�˹ͤ��褦�Ȥ⤷�ʤ��ä��������������ηаޤˤĤ��Ƶ������Ȥϡ����פäƤ��ʤ�����2018/08/26�� �ߤ롦��ࡦ���� �������Ȥ�����γ��ܡ��֤��ͤ����Ǥơ� �������¶�  �����ܺ�ȤΤ������Ȥ�����˴���ʤ��ޤ��������ɤ⤿���ˤȤƤ���Ũ�ʳ��ܤ�����ץ쥼��Ȥ���92ǯ�������Ǥ������ƻ�Ȥ��礭�����夲�Ƥ��ޤ�����ɽ��Ȥ��ƶ��̤��Ƥ����Ƥ���Τϡ֤��餹�Υѥ�䤵��ס֤���ޤ����ȤƤ����פǤ����������ܤ��ˤȤäƤ���ɽ��ϡ��ʳؼԤǤ⤢�뤫�����Ȥ�����Ρ֤��������ܡפΤҤȤĤǤ���֤��ͤ����ǤơפǤ��������ܤ��ɤ�Ǽ﹥���ˤʤä��Ҥɤ⤿�����������ޤ�����2018/05/11��
�����ܺ�ȤΤ������Ȥ�����˴���ʤ��ޤ��������ɤ⤿���ˤȤƤ���Ũ�ʳ��ܤ�����ץ쥼��Ȥ���92ǯ�������Ǥ������ƻ�Ȥ��礭�����夲�Ƥ��ޤ�����ɽ��Ȥ��ƶ��̤��Ƥ����Ƥ���Τϡ֤��餹�Υѥ�䤵��ס֤���ޤ����ȤƤ����פǤ����������ܤ��ˤȤäƤ���ɽ��ϡ��ʳؼԤǤ⤢�뤫�����Ȥ�����Ρ֤��������ܡפΤҤȤĤǤ���֤��ͤ����ǤơפǤ��������ܤ��ɤ�Ǽ﹥���ˤʤä��Ҥɤ⤿�����������ޤ�����2018/05/11��
ȿ�ʿ�� �����̱�ɤȤ� ï���� �ӽ����� ���ָ��Ϥ����Ԥ��롣����Ū���Ϥϡ����Ф����Ԥ����Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely�ˡס�����Ϻ�������130ǯ�����ѹ����˲ȥ�������ȥ�1834��1902ǯ�ˤθ��դǤ������Ϥ����椷���층��������̱�������������롣Ω��������������롣��ͳ�����©�κ����ߤ���롣��ˤλ��¤���¤Ȥ��Ƴؤ��椫��ȯ����줿�ʸ��Ǥ�����2018/04/27�� ���ȿ� ������ڤΤۤ��������ǴĶ���ͥ������¿���οͤ��פäƤ���餷���� �����¶� �����ܷкѿ�ʹ���Ż��Ǥˡ֤��ʤ���٤Ƥ빩����ڡפȤ�������ब�ܤäƤ��ơ���̣�˶�����ɤ�Ǥߤޤ�����������ڤȤϡ���ڹ���ǰ�Ƥ�줿��ڤΤ��ȤǤ�����ڹ���Ȥϡ������ͤ��Ȥꡢ�����ߤꡢ����������Ƚ��Ǥ������֤ǡ����۸��������ȯ�����������ɡʣ̣ţġ˾����ʤɤο�������ڤ��Ƥ빩��Τ��Ȥ�����ޤ��������Ǥ϶�����ή�����Ǥ���ޤ�����2018/04/24�� ���ȿ� �ڤ�餫��ۤͤ��ϡ��Ϥʤ���˸¤롡�������¶� ��2003ǯ�����顢�⤦15ǯ�ۤɤ����ˤʤ롣�������������Ƥ����顢���ԻԾ�����������Ⱥ��줵�餪ʹ�������ä��ФƤ�����������ڤ���ɽ�Ȥ⤤�������ڤ���³���Ƥ��룴����������ˤμ����̱�������⤷�����ΤǽƤ�������2018/04/04�� ���ȿ� �ڤ�餫��ۤ⤦�������������羧���Ϥޤ롡�����¶� �������ϴ����ü�ä��˰��֤��뻳���ϡ���̸������ϰ�Τ��ä������դ��ĵ��������ʤߡ����Ȱ��⤹��ȡ����ߤ����������Ŀ������Ϥޤ롣���ߤμ��ۤ⽪��ä����Ĥ�ܤ˿夬���ꡢ�Ŀ�������������ޤ����θ��ʤ�פ��Ф������ޤ�ޤ�Ȥ����������Ĥˤϡ�������������������դ�롣���Ĥ��ԻĤ˻פ��Τϡ��Ĥ�ܤ˿夬���ä��Ȥ���ˡ����������羧���Ϥޤ뤳�Ȥ�����2018/03/25�� ���ȿ� ��ڤι�ƭ�ȿ������ƥ� �����礷������³�����Ȼפä�������˶�����ŷ�����Ѥ�³����ǡ���ڤι�ƭ���Ȥޤ�ʤ�����¼�����������ԻԤǤ⡢�����ѡ���Τ�������ڻ�ʬ�ΤҤ��ڤ��170�ߤȤ������ʤ��Ĥ��Ƥ���������ǤϤ�������ľ����Τ����ȡ����֤���ä��꿧�������ä���������ä���ȡ��������������餷����������̿������ۤ�������졢�����ѡ����ϰ¤���äƤ��뤬�����ʤ��Ϥ�Ϥ�⤤���ƥ�Ӥ�Ĥ���ȡ���������������Ȭɴ���Τ���������ʬ�¤��Ϥʤ�ʤ��͡����Ǹ�������������äƤ������������¶��ˡ�2018/01/24�� ���ȿ� ���Υ��ޡ������¶� ��������������ܤ�����ϡ����������ϤȤ����Τ��Ƥ������ܰ�Υ����Ϥ�����8000��;���Υ���ǯ��50�ȥ����ϡ�����Υ���������7������Ƥ��롣�Ȥ��äƤ⡢���ܤΥ�����Ψ�ϣ���������16���ȥ��͢������롣���˼���������2�̤�͢���������2017/12/11�� ���ȿ� ���Ȥ�TPP�������ˤ�ȤDz����ͭ�����Ȥ�¸�ߤ�ͤ��� �������¶� ����Ʊ��ɽ�Ȥ��ƴؤ�äƤ������ͭ�����ȱDz�פ���ǯ�ǣ�����ǯ��ޤ�������ǯ��������dz��š��䤬��������Ϥ��ϰ��Ǥ����Ť����褦�ˤʤä��������������ǡ����Σ���ǯ�����ȤϤȤƤĤ�ʤ��ʻ�����ä��������Τ��٤Ƥ�Ծ춥���Ǥ���륰�����Хꥼ�������Ӥ��ʤ��ǡ���̱�����Ȥ��������졢��̱�����Ϥ�����������Ƥ��ä�����������ǯ�����ޤäƤ��롣ͭ�����ȤȤϲ������������Τ��Ȥ�ͤ����ࣱ��ǯ�Ǥ⤢�ä�����2016/12/08�� ���� ��ˡ������ϱ������Ƥ��ޤ�ʤ��������ܹ�ͺ �������������������ˡ��������������Ĺ�ˤϺ�ǯ������衢������֤�˿��Ĥ�Ƴ���������̱�ޤ����������ϣ���ˤĤ��ơּ�����ΰ����դ������ΤǤʤ������Ҹ�������Ȥ�Ȥ�줫�ͤʤ��פȽҤ١�������ɬ�פȤ�ǧ��������������Ф���̱���ޤ�����ϡָ��Է�ˡ��������ɾ��������뤳�Ȥ����������Ƥ���פ�ɽ�������������������������ˡ������ʿ��Ѳ��Ĺ�ˤϻ�����ˡ�������³���ƿ��Ĥ�Ƴ��������¼����ĤϺ�ǯ������衢��ǯ������֤ꡣ��̱��̱�ʡ����������������ܰݿ��β�̱�Σ����ɤ��ַ�ˡ����аޡפ�ơ��ޤ˰ո�ɽ���������θ�˼�ͳƤ�Ĥ�Ԥä������ε����ˤ����ַ�Τ褦�ʱ��������פ�פƤ��롣��2016/11/30�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף������� �������Τ�Ƥʤ� �����������ʥե�����������ա�  ���ϡ�Ĺ��ϳ���̵�����椬�ȤǤϵ����������Ū�˿��٤뤳�Ȥ����ʤ�����ΰ�ĤǤ�������ʤȤ�������Φ��ʬ��¿���ե�Ȼ��Ƥ���Ȥ������⤷��ޤ��������ͧ�ͤ��Ƴڤ����椬�Ȥ�����Ū�˹ԤʤäƤ��ޤ��������˱�������ʤ���ͧ�ͤ��²��ˬ�ͤ���Ƥ����Ȥ�������ޤ�������ʤȤ�����������ä�������������֤ϡ��ͤˤȤäƤϳ��̤γڤ��ߤλ��֤Ǥ�������Ϥ���ʤȤ��Τ��ä�2016/11/23��
���ϡ�Ĺ��ϳ���̵�����椬�ȤǤϵ����������Ū�˿��٤뤳�Ȥ����ʤ�����ΰ�ĤǤ�������ʤȤ�������Φ��ʬ��¿���ե�Ȼ��Ƥ���Ȥ������⤷��ޤ��������ͧ�ͤ��Ƴڤ����椬�Ȥ�����Ū�˹ԤʤäƤ��ޤ��������˱�������ʤ���ͧ�ͤ��²��ˬ�ͤ���Ƥ����Ȥ�������ޤ�������ʤȤ�����������ä�������������֤ϡ��ͤˤȤäƤϳ��̤γڤ��ߤλ��֤Ǥ�������Ϥ���ʤȤ��Τ��ä�2016/11/23��
TPP��æ�������Хꥼ������� �Ԥ��ͤޤ뿷��ͳ����ȡȤ⤦�ҤȤġɤ����� �����������������Ƥ������Ȥߤ����졢����ͳ����˴�Ť��������Х벽�˻�������äƣ���ǯ�ϷФġ��������郎��ä����������Хꥼ�������ο��������Ū�����Ȥߡ�������Ĥ������ï�⤬���Ԥ������������Ϥʤ�ʤ��ä����դ˺��������Ϻ���Τ�����ˤ��롣�ͤӤȤ�˭���ˤ���ȹͤ����Ƥ����Ծ�кѤ���Ĺ��������դ�����ؤ��������Ϻ��γ������������ϡ�Ĺǯ�Ѥ߾夲���Ƥ���̱�����Ȥ���˴�Ť��������������ƥ���������ʥ���ʥꥺ����ӳ�����β��ԡ��֥ƥ��ꥺ��פγ����⤿�餷�����������¶��ˡ�2016/10/24�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף��������γڤ��ߡ����������ʥե�����������ա�  ������²����֤ȿ��٤�ͼ�Ӥ����̤ʻ��֤��Ф��Ƥ���ޤ�������Ϥ�����������äŻ���Ȥ������Ȥ�Ʊ����Ǻ�ߤ�������ȸ������ȤǤ⤢�äơ�����ʤȤ�����̣������������֤Ȥβ��ä������Υ��ȥ쥹���ä��Ƥ���ޤ���������Կ��Ǥ�����¼�Ǥ�Ʊ�����Ȥ��Ȼפ��ޤ�����������¼�ϼ֤��ʤ��Ƥϥ���ӥ˥����ȥ��ˤ�Ԥ����Ȥ��Ǥ��ʤ����������Ż��������мҰ����˵���Τߤǡ��٤ߤ����ˤ�֤��ʤ���������ˤ���뤳�Ȥ�������ޤ�����2016/09/14��
������²����֤ȿ��٤�ͼ�Ӥ����̤ʻ��֤��Ф��Ƥ���ޤ�������Ϥ�����������äŻ���Ȥ������Ȥ�Ʊ����Ǻ�ߤ�������ȸ������ȤǤ⤢�äơ�����ʤȤ�����̣������������֤Ȥβ��ä������Υ��ȥ쥹���ä��Ƥ���ޤ���������Կ��Ǥ�����¼�Ǥ�Ʊ�����Ȥ��Ȼפ��ޤ�����������¼�ϼ֤��ʤ��Ƥϥ���ӥ˥����ȥ��ˤ�Ԥ����Ȥ��Ǥ��ʤ����������Ż��������мҰ����˵���Τߤǡ��٤ߤ����ˤ�֤��ʤ���������ˤ���뤳�Ȥ�������ޤ�����2016/09/14��
���� ���Խ�Ĺ�Ѹ��۶��ź����衡ī����ʹ���������ܤäƤ��롡�������¶� ��ī����ʹ�����Τ����Ǥ��������ܤ���������Ф������֤ޤ��������Ȥ����٤����פȤ����Ф��ǻϤޤ룸���������֡ض��ź��ˡ�ơ������μ�ˡ�������פǤ��롣��������������ܤ϶��ź�ι����Ф�Ƥ�פȤ���ƻ����ǥ������̤��Ƥ��ä�����ή�줿����̱��ȿ�Фˤ�äơ�����ޤǣ����ѰƤˤʤä����ź��֥ƥ����ȿ��Ⱥ������פ�̾�����Ѥ��ƽ��ι�����Ф���Ȥ��������Ǥ��롣��2016/08/30�� ʡ�礫�� ���ޤ�������å��������� �����ե����ޤǷ�ˡ��ͤ��롡�����Ҳ����������ܥ��ꥹ�ȶ��ļ㾾��Į����� ��2005ǯ2����ꥹ�ȼԤ�Ʊ����2̾�ȡֶ��β�����Į�ؽ���פ�ȯ���ּ�ʬ�θ��դ�ʿ�¤���פ���ɸ�ˡ�10ǯ�����γؽ����Ť��줿����Ω������Ȥϡפ���Ϥޤä��ؤӤ�¿���ˤ錄�ä��������ܹ��ˡ�˿������ǡ������������˷�ˡ������ơ��ͤ���褦�ˤʤä��������ơ�2011ǯ3��11������������̺Ҥ�ȯ�����������ʡ����츶����ȯ�Ž�˻��Τε��������λ���ʡ�縩̱�����Ǥʤ������ι��������ï��ο�������ϧ�����ȶ��ˡ��ڤ�ü���Ф˿���Ф��줿�ȹͤ��Ƥ��롣�ʺ�����ˡ��ͤ����إԥ������ȥ�٣����椫��ˡ�2016/08/11�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף���������鷻��ե�������͡����������ʥե�����������ա�  �ͤˤ�4�ĤۤɺФ�Υ�줿�郎���ޤ���������������ͤȤ⤤���밭�����ǡ������������������ơ��褯ξ�Ƥ��ܤ��Ƥ��ޤ������ͤ���Ĺ���٤�����Τۤ�����Ĺ�ο��Ӥ��ᤫ�ä��Τǡ��褯�лҤ˴ְ㤨��줿�ꤷ����ΤǤ����ͤϥե�������ͤˤʤ뤳�Ȥ�������ᡢ16�ФDzȤ����ӽФ��ƽ��Ԥ����ꡢ����ǰ����餷��17�Фλ��˻Ϥ�ޤ��������ǽ�˼�ʬ�������˸Ƥ����²����Ǥ������ब�����λ�ʬ�������ͷ�Ӥ��褿�ꤷ�ơ����������ʾ��˹Ԥ��ޤ�����������ˤĤ������ʰտޤϤ���ޤ���Ǥ�������������郎�֥ե�������ͤˤʤꤿ���פȸ��äƤ����ξ�Ƥ���ʹ�������϶ä��ޤ�������������Ƥ����櫓�ǤϤʤ��Ǥ��礦�����༫�Ȥ�˾���Ʊ��ƻ����ळ�Ȥˤʤä��ΤǤ�����2016/07/06��
�ͤˤ�4�ĤۤɺФ�Υ�줿�郎���ޤ���������������ͤȤ⤤���밭�����ǡ������������������ơ��褯ξ�Ƥ��ܤ��Ƥ��ޤ������ͤ���Ĺ���٤�����Τۤ�����Ĺ�ο��Ӥ��ᤫ�ä��Τǡ��褯�лҤ˴ְ㤨��줿�ꤷ����ΤǤ����ͤϥե�������ͤˤʤ뤳�Ȥ�������ᡢ16�ФDzȤ����ӽФ��ƽ��Ԥ����ꡢ����ǰ����餷��17�Фλ��˻Ϥ�ޤ��������ǽ�˼�ʬ�������˸Ƥ����²����Ǥ������ब�����λ�ʬ�������ͷ�Ӥ��褿�ꤷ�ơ����������ʾ��˹Ԥ��ޤ�����������ˤĤ������ʰտޤϤ���ޤ���Ǥ�������������郎�֥ե�������ͤˤʤꤿ���פȸ��äƤ����ξ�Ƥ���ʹ�������϶ä��ޤ�������������Ƥ����櫓�ǤϤʤ��Ǥ��礦�����༫�Ȥ�˾���Ʊ��ƻ����ळ�Ȥˤʤä��ΤǤ�����2016/07/06��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף��������郎�����Υԥ��ɥݡ�������������ʥե�����������ա�  ���������ڤ��ϥե�Ǥ�Pied de porc(�ԥ��ɥݡ���)�ȸƤФ졢���Ū�ݥԥ�顼�ʿ���ΤҤȤġ�����Ϥ�������Τ��ä����ܤ����ȸ����а��հ��߲��ǽФƤ��롢���ǤפˤפˤΤĤޤߤ�פ��⤫�٤�����¿���Ȥϻפ��ޤ������ѥ�ʤɤΥӥ��ȥ������ȸ����дݾƤ����ͤ�ʪ�Τ��Ȥ�¿���Ǥ������δݾƤ������Ǿ��䤷�Ƥ���Ź�⤢�뤯�餤�ǡ���ǫ�˲��������줿���ϡ����줬�����ڤ��ʤΤ��Ȼפ��ۤɤ����٤�ǻ����̣�襤���繥���������ΰ�ĤǤ�����2016/04/30��
���������ڤ��ϥե�Ǥ�Pied de porc(�ԥ��ɥݡ���)�ȸƤФ졢���Ū�ݥԥ�顼�ʿ���ΤҤȤġ�����Ϥ�������Τ��ä����ܤ����ȸ����а��հ��߲��ǽФƤ��롢���ǤפˤפˤΤĤޤߤ�פ��⤫�٤�����¿���Ȥϻפ��ޤ������ѥ�ʤɤΥӥ��ȥ������ȸ����дݾƤ����ͤ�ʪ�Τ��Ȥ�¿���Ǥ������δݾƤ������Ǿ��䤷�Ƥ���Ź�⤢�뤯�餤�ǡ���ǫ�˲��������줿���ϡ����줬�����ڤ��ʤΤ��Ȼפ��ۤɤ����٤�ǻ����̣�襤���繥���������ΰ�ĤǤ�����2016/04/30��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����������쥹�ȥ��ؤ�̴�����Σ������������ʥե�����������ա�  ������路���Ȳ���Ω�Ƥʤ��顢����ꥨ�������ѥ�饹�˶����������Ȥ��ˤϡ����Ȥ⤤���ʤ����ȴ��Τ褦�ʤ�Τ�����ޤ����쥹�ȥ����ʤ��դ�����ä��夤���Ȥ����פ��ȡ����줫��Ϥޤ�ǥ��ʡ��ؤι�ޤ���ԡ����¤���ˢ�ǹ���ᤷ�ʤ��顢��˥����Ӥؤ�ή��Ƥ椯���ʤΤ褦�ʤ�ΤǤ��礦������2016/03/17��
������路���Ȳ���Ω�Ƥʤ��顢����ꥨ�������ѥ�饹�˶����������Ȥ��ˤϡ����Ȥ⤤���ʤ����ȴ��Τ褦�ʤ�Τ�����ޤ����쥹�ȥ����ʤ��դ�����ä��夤���Ȥ����פ��ȡ����줫��Ϥޤ�ǥ��ʡ��ؤι�ޤ���ԡ����¤���ˢ�ǹ���ᤷ�ʤ��顢��˥����Ӥؤ�ή��Ƥ椯���ʤΤ褦�ʤ�ΤǤ��礦������2016/03/17��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����������쥹�ȥ��ؤ�̴�����������ʥե�����������ա�  �ե�ˤϥ���֥�ƥ�����ã�ι��쥹�ȥ�������˽�̱Ū�ʥӥ��ȥ��ޤ�¿��¿�ͤʰ���Ź������ޤ������ե�������ͤ��ܻؤ��֤���ä���ͤ����ϳ�����⤬���٤Ϲ��쥹�ȥ��ؤ�̴����ĤΤ��Ȼפ��ޤ�������Ӥ䤫����������������ե��ɥ�ʥ�������������ڤʥ磻�顼�˼���Τ褦�ʥ磻��ꥹ�ȡ���������̤��줿���Ѥ������ؤξ�Ǯ������ȴ���줿����Ǻ���롢�����Ⱥǿ��Υե�������������������������������Ϥ��ܤ�ȴ������ȡ�ɾ���Ȥ䥬���ɥ֥å��������ͥåȥ�ӥ塼����Υץ�å��㡼�ȡ�����ޤ����Ϥˤ���ȴ��Ⱦ�Ǯ�η뾽�Ǥ�����2016/03/03��
�ե�ˤϥ���֥�ƥ�����ã�ι��쥹�ȥ�������˽�̱Ū�ʥӥ��ȥ��ޤ�¿��¿�ͤʰ���Ź������ޤ������ե�������ͤ��ܻؤ��֤���ä���ͤ����ϳ�����⤬���٤Ϲ��쥹�ȥ��ؤ�̴����ĤΤ��Ȼפ��ޤ�������Ӥ䤫����������������ե��ɥ�ʥ�������������ڤʥ磻�顼�˼���Τ褦�ʥ磻��ꥹ�ȡ���������̤��줿���Ѥ������ؤξ�Ǯ������ȴ���줿����Ǻ���롢�����Ⱥǿ��Υե�������������������������������Ϥ��ܤ�ȴ������ȡ�ɾ���Ȥ䥬���ɥ֥å��������ͥåȥ�ӥ塼����Υץ�å��㡼�ȡ�����ޤ����Ϥˤ���ȴ��Ⱦ�Ǯ�η뾽�Ǥ�����2016/03/03��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����������ߤΥ����ס����������ʥե�����������ա�  ���ޥ��ʥ�20�٤������ˤʤꡢ���˽Ф�ȼ���������Ȥ��Ƥ������䤨������¼�ο��ߤϡ������쿧�ζ������������ʲ�������Τ˵����뤳�ε���ϡ����Ȥ�ɤ�Υ����פ��Ȥ⿴�ⲹ��Ƥ���ޤ����ե�������⤢�������ʥ����פ����̣�襤������Ϥ���ʥ����פ��äǤ����жл��֤������3ʬ�ۤɤΥۥƥ�ޤǤ�ϩ�⡢��֤��㤬�ߤ��Ѥ�ä����Ȥ����֤νжФ��ȡ����⤺�ĥ��Ρ��֡��Ĥ�Ƨ�ߤ���ʤ������˿ʤߡ��Ѥ����ˤ�äƤ�10ʬ�ʾ夫����ޤ����������ߤμ���ϥۥƥ��Ȥ⡢�ܥ��顼�ǿ椯��˼�������ѤǤȤƤⴥ�礷�ơ�����Ū���ߤ�æ����֤�³���ޤ�������ä���ǿ��⤫���������Ż����Ƥ��Ƥ��åץ����ȿ�ʬ����ɬ�ܤǤ�����2016/01/22��
���ޥ��ʥ�20�٤������ˤʤꡢ���˽Ф�ȼ���������Ȥ��Ƥ������䤨������¼�ο��ߤϡ������쿧�ζ������������ʲ�������Τ˵����뤳�ε���ϡ����Ȥ�ɤ�Υ����פ��Ȥ⿴�ⲹ��Ƥ���ޤ����ե�������⤢�������ʥ����פ����̣�襤������Ϥ���ʥ����פ��äǤ����жл��֤������3ʬ�ۤɤΥۥƥ�ޤǤ�ϩ�⡢��֤��㤬�ߤ��Ѥ�ä����Ȥ����֤νжФ��ȡ����⤺�ĥ��Ρ��֡��Ĥ�Ƨ�ߤ���ʤ������˿ʤߡ��Ѥ����ˤ�äƤ�10ʬ�ʾ夫����ޤ����������ߤμ���ϥۥƥ��Ȥ⡢�ܥ��顼�ǿ椯��˼�������ѤǤȤƤⴥ�礷�ơ�����Ū���ߤ�æ����֤�³���ޤ�������ä���ǿ��⤫���������Ż����Ƥ��Ƥ��åץ����ȿ�ʬ����ɬ�ܤǤ�����2016/01/22��
���եꥫ �֥ۥ������åȡ�����å� �ס������른���ꥢ̱�粽��Ʈ�Ρ��ह����ǯ�����������֥ǥ�ޥ��ɡ��٥���Abdelmadjid Benkaci��  ���ۥ������åȡ�����åɡ�Hocine Ait Ahmed�ˤϣ�������ǯ������������른���ꥢ�λ������ӤȤ����Τ��륫�ӥ������ξ�����¼�����ޤ줿�������åȡ�����åɤϤ���¼��̾���Ǥ���Τ�����ϥ��른���ꥢ���ʥ���ʥꥺ�����Ƭ�˰��֤�����ʪ�Ǥ��ꡢ��������ǯ��������˳�̿���������ͤ���ΰ�ͤʤΤ����ۥ������åȡ�����åɤ���ͳ��ʹ֤�º���Ȥ��ä����ͤ�ؤӼ�ä��Τϥ��른���ꥢ��̱�ޤˤ����Ƥ��ä����������ޤϥ��른���ꥢ�Υʥ���ʥꥺ��ˤȤäƤϷ礫�����Ȥ��Ǥ��ʤ���ʪ�Ǥ����å��ꡦ�ϥå���Messali Hadj�ˤˤ�ä���Ω���줿���ۥ������åȡ�����åɽ���������ƻ���鳰��뤳�ȤϤʤ��ä��Τ��������ơ���Ϥ���ƻ�른���ꥢ���ۤ����������������른���ꥢ��̱�ޤ˥ۥ������åȡ�����åɤ����ޤ����ΤϤ鷺�������Ф��ä��Τ�����2015/12/30��
���ۥ������åȡ�����åɡ�Hocine Ait Ahmed�ˤϣ�������ǯ������������른���ꥢ�λ������ӤȤ����Τ��륫�ӥ������ξ�����¼�����ޤ줿�������åȡ�����åɤϤ���¼��̾���Ǥ���Τ�����ϥ��른���ꥢ���ʥ���ʥꥺ�����Ƭ�˰��֤�����ʪ�Ǥ��ꡢ��������ǯ��������˳�̿���������ͤ���ΰ�ͤʤΤ����ۥ������åȡ�����åɤ���ͳ��ʹ֤�º���Ȥ��ä����ͤ�ؤӼ�ä��Τϥ��른���ꥢ��̱�ޤˤ����Ƥ��ä����������ޤϥ��른���ꥢ�Υʥ���ʥꥺ��ˤȤäƤϷ礫�����Ȥ��Ǥ��ʤ���ʪ�Ǥ����å��ꡦ�ϥå���Messali Hadj�ˤˤ�ä���Ω���줿���ۥ������åȡ�����åɽ���������ƻ���鳰��뤳�ȤϤʤ��ä��Τ��������ơ���Ϥ���ƻ�른���ꥢ���ۤ����������������른���ꥢ��̱�ޤ˥ۥ������åȡ�����åɤ����ޤ����ΤϤ鷺�������Ф��ä��Τ�����2015/12/30��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף��������Υ���ɥ��å� ���������ʥե�����������ա�  �������֤�;͵���ʤ��������äȿ�����Ѥޤ������Ȥ������ˤ褯���Τ�����ɥ��å����ե�Ǥ��ڤ�����ο����Ȥ��Ƴڤ��ޤ�Ƥ��륵��ɥ��å���˻���������ζ���̣���Ǥ����ʤˤ�ꥫ�ȥ���Ȥ鷺�˿��٤뤳�Ȥ�����ơ������դ��μ�֤����ʤ��Τ�̥�ϤǤ������Ф�������Ф����ΤǤ����顣��2015/11/27��
�������֤�;͵���ʤ��������äȿ�����Ѥޤ������Ȥ������ˤ褯���Τ�����ɥ��å����ե�Ǥ��ڤ�����ο����Ȥ��Ƴڤ��ޤ�Ƥ��륵��ɥ��å���˻���������ζ���̣���Ǥ����ʤˤ�ꥫ�ȥ���Ȥ鷺�˿��٤뤳�Ȥ�����ơ������դ��μ�֤����ʤ��Τ�̥�ϤǤ������Ф�������Ф����ΤǤ����顣��2015/11/27��
��� �ѥ�Ǻ�ȯ�����ƥ����� ���ѥ��Ʊ��¿ȯ�ƥ����������Ȥ����Τ餻��ʹ�����ΤϻŻ���Ǥ������ֺ�ī�����ܻ��֤ǡˡ��ѥ������郎������������ä����ޤ���Ǥ������ѥ�ˤ��οͤ����ʤ��ʤ����顢������˲�����ꡢ�������ޤ줿�ꤷ���ͤϤ��ʤ��ä��Τ��ʡ������ǽ�ˤ����פ��ޤ������ȡ�Ʊ���ˡ��˥塼�衼���ǣ�������ǯ��������˵������Ȥ��Τ褦�ʡ���������ؤȲ������褬�������Ƥ����ΤǤϤʤ������Ȥ���ͽ��������ޤ�������2015/11/16�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף������ߤΤ��⤤�ǡ��������ʥե�����������ա�  ���������ä����դ�ꡢ����դ�ƻϩ�����Ϥᡢ�ڡ�����ˤʤä��ߤ�����ʹ�����Ƥ���ȡ������������褿������ǯ�פ��Ф��ޤ������κ��μ�ʬ�ϤҤɤ��������Ǥ��ơ�����Ū�ˤ�����Ū�ˤ�����ǰ��Ȥ��������֤Ǥ��������ڰ����αؤ��饷��ȥ�Х��˾�ꡢ��ƻ��ʤद����ɸ��ˤ�뵤���Ǽ����椬�Ĥ�Ȥ��ʤ���⡢��γ��˸����롢�㤬���ä����Ѥ�ä��Ӥȡ���������ֻ������餭����������ä��Τ�����Τ��ȤΤ褦�˳Ф��Ƥ��ޤ�����2015/11/04��
���������ä����դ�ꡢ����դ�ƻϩ�����Ϥᡢ�ڡ�����ˤʤä��ߤ�����ʹ�����Ƥ���ȡ������������褿������ǯ�פ��Ф��ޤ������κ��μ�ʬ�ϤҤɤ��������Ǥ��ơ�����Ū�ˤ�����Ū�ˤ�����ǰ��Ȥ��������֤Ǥ��������ڰ����αؤ��饷��ȥ�Х��˾�ꡢ��ƻ��ʤद����ɸ��ˤ�뵤���Ǽ����椬�Ĥ�Ȥ��ʤ���⡢��γ��˸����롢�㤬���ä����Ѥ�ä��Ӥȡ���������ֻ������餭����������ä��Τ�����Τ��ȤΤ褦�˳Ф��Ƥ��ޤ�����2015/11/04��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����ѹ��������Ǿ��ۤ���������Ĺ���ߡ��������ʥե�����������ա�  ������������¼�ϰ�ǯ���̤������äʵ�������ħ�Ǥ������Ƥ��ä����Ʋᤴ���䤹���֤��դ�����Ϥ�뺣��ʬ����Ϥޤ��ߤδ����ϤȤƤ⸷�����Ǥ������Ū��Ϥ���Ȥϸ��äƤ⡢���ä�����Ѥ����ȥޥ��ʥ�15�٤�ɹ�����������Ǥ�����˼�Ϥ��ä�������Ƥ��ޤ����������Τʤ���ǡ���Ȥ⤷���������������ѡ�����Ȥμ��٤Ǥ�ȩ��Τɤ⤫�餫��Ǥ��������������������������Ⱦ��Ⱦǯ��³���ޤ������礷��Ĺ���ߤ��������Ĥ�����뤷���ʤ����ˤϡ��������������Ѱդ��ʤ��饭�å���βи������ˤؤФ�Ĥ��Ƥ�������ΤǤ�������Ϥ�������˺��ѹ����������ä�2015/10/21��
������������¼�ϰ�ǯ���̤������äʵ�������ħ�Ǥ������Ƥ��ä����Ʋᤴ���䤹���֤��դ�����Ϥ�뺣��ʬ����Ϥޤ��ߤδ����ϤȤƤ⸷�����Ǥ������Ū��Ϥ���Ȥϸ��äƤ⡢���ä�����Ѥ����ȥޥ��ʥ�15�٤�ɹ�����������Ǥ�����˼�Ϥ��ä�������Ƥ��ޤ����������Τʤ���ǡ���Ȥ⤷���������������ѡ�����Ȥμ��٤Ǥ�ȩ��Τɤ⤫�餫��Ǥ��������������������������Ⱦ��Ⱦǯ��³���ޤ������礷��Ĺ���ߤ��������Ĥ�����뤷���ʤ����ˤϡ��������������Ѱդ��ʤ��饭�å���βи������ˤؤФ�Ĥ��Ƥ�������ΤǤ�������Ϥ�������˺��ѹ����������ä�2015/10/21��
ʸ�� ����¼�Υե�������������ޤ뽩����̣�����ʥ����������ʥե�����������ա�  �������ϸ�������¼����ڤ�˭�٤Ǥ���̾ʪ�Υ���٥Ĥ�Ϥ�����٤�ľ���ǤϤ�����������ڤ���äƤ��ޤ������˰��κʤȤ���Ф�����ڤ��㤤�˹Ԥ����Ȥ��ᥤ��Υ��٥�ȡ��콵ʬ����ڤ��㤤�˥������Ƥ�ڰ����ޤǹԤ��������ˤ��äѤ���äƤ��ơ���ͤ���¢�ˤ˼����Ȥ����Τ���ͤ����ä����������֥������Ǥ������ϸ��ϥʥ����û��ǡ�����������ľ���ˤ⤿�������¤�Ǥ��ޤ����ä˴ݥʥ��Ϻǹ�Ǥ�����2015/09/20��
�������ϸ�������¼����ڤ�˭�٤Ǥ���̾ʪ�Υ���٥Ĥ�Ϥ�����٤�ľ���ǤϤ�����������ڤ���äƤ��ޤ������˰��κʤȤ���Ф�����ڤ��㤤�˹Ԥ����Ȥ��ᥤ��Υ��٥�ȡ��콵ʬ����ڤ��㤤�˥������Ƥ�ڰ����ޤǹԤ��������ˤ��äѤ���äƤ��ơ���ͤ���¢�ˤ˼����Ȥ����Τ���ͤ����ä����������֥������Ǥ������ϸ��ϥʥ����û��ǡ�����������ľ���ˤ⤿�������¤�Ǥ��ޤ����ä˴ݥʥ��Ϻǹ�Ǥ�����2015/09/20��
ʸ�� ���른���ꥢ����μ�桡���Ӥκפ꤬��ǯ���Ť��Ƥ��������������֥ǥ�ޥ��ɡ��٥��ʥ��른���ꥢ�ͥ��㡼�ʥꥹ�� Abdelmadjid Benkaci��  ������������ඵ�̤����Ӥκפ�ϲ������ˤ��ϤäƹԤ��Ƥ������������Ǥ�����ˤˤ���Aid El Kebir�ʤ��������Ӥκפ�Ȥϥ��֥�ϥ�ʥ��֥�ҥ�ˤΰ��äˤ��ʤ����ΤǤ������֥�ϥ�Ͽ�����©�ҤΥ�����ޥ�������Ӥˤ���褦��̿����졢���������λ���������˼ºݤ˥�����ޥ�������Ȥ��ޤ��������λ������ϥ��֥�ϥ�˰�Ƭ���Ӥ����ꡢ�����Ӥ�©�Ҥο�����Ȥ������Ӥˤ������衢��̿�����ΤǤ�����2015/09/13��
������������ඵ�̤����Ӥκפ�ϲ������ˤ��ϤäƹԤ��Ƥ������������Ǥ�����ˤˤ���Aid El Kebir�ʤ��������Ӥκפ�Ȥϥ��֥�ϥ�ʥ��֥�ҥ�ˤΰ��äˤ��ʤ����ΤǤ������֥�ϥ�Ͽ�����©�ҤΥ�����ޥ�������Ӥˤ���褦��̿����졢���������λ���������˼ºݤ˥�����ޥ�������Ȥ��ޤ��������λ������ϥ��֥�ϥ�˰�Ƭ���Ӥ����ꡢ�����Ӥ�©�Ҥο�����Ȥ������Ӥˤ������衢��̿�����ΤǤ�����2015/09/13��
ʸ�� ����¼�Υե����������̵�¤β�ǽ�����ĥѥ������������ʥե�����������ա�  �� �ե�������ǤϤ���ޤ����ԥ���ѥ���������ɥ��å��ȸ��ä���������ʴ��Τ��ο��ϡ����ܿͤ�����˿�Ʃ�����ä����Τ������������Ǥ����ͼ��Ȥ��Τɤ�⤬�繥���Ǥ�������������ͳ�Ϻ��Ȥ��μ�ڤ��⤢��褦�˻פ��ޤ�������Ϥ��������ο�������ɽ�֥ѥ����פ��ä���Ǥ�����Ǥ�ѥ����Ͽ͵��������Ǥ����ͤμ��ब˭�٤ǡ���������̣�դ���̵���硣��������ܿͤ��ͤ��繥���Ǥ�����2015/09/11��
�� �ե�������ǤϤ���ޤ����ԥ���ѥ���������ɥ��å��ȸ��ä���������ʴ��Τ��ο��ϡ����ܿͤ�����˿�Ʃ�����ä����Τ������������Ǥ����ͼ��Ȥ��Τɤ�⤬�繥���Ǥ�������������ͳ�Ϻ��Ȥ��μ�ڤ��⤢��褦�˻פ��ޤ�������Ϥ��������ο�������ɽ�֥ѥ����פ��ä���Ǥ�����Ǥ�ѥ����Ͽ͵��������Ǥ����ͤμ��ब˭�٤ǡ���������̣�դ���̵���硣��������ܿͤ��ͤ��繥���Ǥ�����2015/09/11��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����ǥ����Ȥδ�ӡ��������ʥե�����������ա�  ���������Ϥ��ä����������ꤳ��ǡ����ʤ���֤����ȿ����Ϥߤ������Ȥ�������ͼ����ɬ�פʤΤ��ǥ����ȡ���̣�����ǥ����ȤϿ����κǸ������ʻ��֤�������äƤ���ޤ����쥹�ȥ������������ǥ����Ȥ����¤䤫��������Ǥ������ɤ��餫�ȸ����ȡ�����ޤǤ���������ڤ䤫�ˤȰռ����ƺ�ꡢ���뤳�Ȥ�¿���ΤǤ����������Ǥϥե��ʡ�����¤䤫�ˡ����줬�����ȥ쥹�ȥ��Υǥ����Ȥ�ʬ����ݥ���Ȥ��⤷��ޤ���2015/09/05��
���������Ϥ��ä����������ꤳ��ǡ����ʤ���֤����ȿ����Ϥߤ������Ȥ�������ͼ����ɬ�פʤΤ��ǥ����ȡ���̣�����ǥ����ȤϿ����κǸ������ʻ��֤�������äƤ���ޤ����쥹�ȥ������������ǥ����Ȥ����¤䤫��������Ǥ������ɤ��餫�ȸ����ȡ�����ޤǤ���������ڤ䤫�ˤȰռ����ƺ�ꡢ���뤳�Ȥ�¿���ΤǤ����������Ǥϥե��ʡ�����¤䤫�ˡ����줬�����ȥ쥹�ȥ��Υǥ����Ȥ�ʬ����ݥ���Ȥ��⤷��ޤ���2015/09/05��
���� �罰��ư������Ū�ʽи�  ����������8��30����������˰��ݴ�Ϣˡ�Ƥ˹��Ĥ��뤿��˽��ޤä��͡����ä�ʹ���ʤ��顢��̱������͡����ܤ���������������Ƥ��뤳�Ȥ��ޤ�����
��2015/08/31��
����������8��30����������˰��ݴ�Ϣˡ�Ƥ˹��Ĥ��뤿��˽��ޤä��͡����ä�ʹ���ʤ��顢��̱������͡����ܤ���������������Ƥ��뤳�Ȥ��ޤ�����
��2015/08/31��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף�����Ū�ʥե��殺�顡�������ʥե�����������ա�  �����Ƕ�ǤϤ��������ȡ��ɤ��̰����̤���ꤶ������뤳�Ȥ�¿���Ǥ������ե�������ˤȤäƤʤ��ƤϤʤ�ʤ����ࡢ���줬�֥ե��殺��פǤ�������ξ��������ǡ������ͦ������äƥե��殺��ˤĤ��ƽ��Ȥˤ��ޤ��������ҤǸƤ���ΤäƤϤ�����ΤΡ��ºݤ˥ե��殺��٤��Τϡ����Ի���˥����դ��Ƥ�����Τ٤����Ƥ��ä��Ȥ��Ǥ��������Ǥ�魯��ʤ�����Ū�ˤ��ޤ��ä����Ȥ�Ф��Ƥ��ޤ�����2015/08/27��
�����Ƕ�ǤϤ��������ȡ��ɤ��̰����̤���ꤶ������뤳�Ȥ�¿���Ǥ������ե�������ˤȤäƤʤ��ƤϤʤ�ʤ����ࡢ���줬�֥ե��殺��פǤ�������ξ��������ǡ������ͦ������äƥե��殺��ˤĤ��ƽ��Ȥˤ��ޤ��������ҤǸƤ���ΤäƤϤ�����ΤΡ��ºݤ˥ե��殺��٤��Τϡ����Ի���˥����դ��Ƥ�����Τ٤����Ƥ��ä��Ȥ��Ǥ��������Ǥ�魯��ʤ�����Ū�ˤ��ޤ��ä����Ȥ�Ф��Ƥ��ޤ�����2015/08/27��
TPP��æ�������Хꥼ������� �ԣУи�ġ����Τ������ܤ������⤭�夬�äƤޤ�ǥԥ����ߤ������������ڰ� ��TPPɺή�β�ǽ�����⤯�ʤäƤ��������������ܤ������Ϥ��Ǥ�TPP������ˡ�TPP���ߤȤ��ƹ������������פ�Ȥ��ä���ȡɡ��ڤ��ܤʤ��ɿʤ�Ƥ��롣��2015/08/25�� ���������ڤ��� ������Ū�פäơ��ɤ��������ȡ� ���ܼ���ϡ����ĤƼ�������������ءפǡ��Dz�֣��̣ף��٣ӻ����ܤ�ͼ���פ��仿�����֤��ޤλ����˺���줬���ʲ�²�ξ𰦤䡢�ͤȿͤȤΤ����������Ĥʤ��꤬�������Ķ���������Ķ���Ƹ����Τ��ʤ������Ƥ����פȽƤ��롣�츫���ޤȤ⡣����������ϡ����£���ǯ�ˤϣ��С����λ���ν�̱������Τ�ʤ��Ϥ��Ǥ��롣�ޤ�����ϡ�����������˽��ı��İ��ΰ��ܴ���������������Ų��ȸƤФ줿�߿��������˺�ƣ�ɺ�Ȥ��������Ȱ�²�μ���˷�Ǥ��ꡢ��̱����˥ꥢ��ƥ��ʤɻ��Ƥʤ�����������ϡ�����ʸ�Ϥ�ľ��ˡ����ٷк���Ĺ���ν�̱������ˤĤʤ����������Ⱖ�����ٷк���Ĺ�������ܿͤο����Ǥ��ä����Τ褦�˸�ä��ߤ�ʤ����������⤷������ξ�������ۤǤ��롣�ʰ�ƣ���ˡ�2015/08/23�� ȿ�ʿ�� �ù���������Ĥ���ä�����ۤ�����¼��  �� ���3.11����ǯ5���˴���ʤä��������Ƥ���С�91�ФˤʤäƤ�������������������郎1���Ǥ��ӤƤ���С�21�Фμ㤵��̿����Ȥ��Ƥ����������ޤ�4�ͤη�������ޤ�ƤϤ��ʤ��ä�����Ϥ�������ȡ������褬�⤦����Ĺ�����Ƥ����顢�������������ޤ�ƤϤ��ʤ��ä��פ����ʤ��ä����Ĥ��䤬�ֲ��������ȿ�Ф��ʤ��ä��Ρ����Ρ��ù���˻ִ�ʤ����Ρ��פ�İ���Ƥ⡢�֤���ʤ��ȸ��������ǤϤʤ��ä��פȸ��������ǡ�����ʾ�ϸ���Ĥ�����ä��ʤ��ä�����ϡ��⤦�����Ȥ����Τ�1���ְ̤��������ȻפäƤ�������2015/08/22��
�� ���3.11����ǯ5���˴���ʤä��������Ƥ���С�91�ФˤʤäƤ�������������������郎1���Ǥ��ӤƤ���С�21�Фμ㤵��̿����Ȥ��Ƥ����������ޤ�4�ͤη�������ޤ�ƤϤ��ʤ��ä�����Ϥ�������ȡ������褬�⤦����Ĺ�����Ƥ����顢�������������ޤ�ƤϤ��ʤ��ä��פ����ʤ��ä����Ĥ��䤬�ֲ��������ȿ�Ф��ʤ��ä��Ρ����Ρ��ù���˻ִ�ʤ����Ρ��פ�İ���Ƥ⡢�֤���ʤ��ȸ��������ǤϤʤ��ä��פȸ��������ǡ�����ʾ�ϸ���Ĥ�����ä��ʤ��ä�����ϡ��⤦�����Ȥ����Τ�1���ְ̤��������ȻפäƤ�������2015/08/22��
ȿ�ʿ�� ���������Ǽ���ˡ�ơפˤĤ��� ���ܿ�����դˤ�äơְ����ݾ�ˡ���פζ��ԤȤ�������������˽��Ӥ�Ƥ��롣��κ����˴ؤ����֤Ǥ��ꡢ���������֤�Ķ�������齽ʬ���ĤϿԤ������ʤɤȤ������ۤ��Ǥ�����ǧ�Ǥ��ʤ���������ʿ�¤�̱������ɸ�֤���ʤ顢��ǯ�Ǥ���֤��Ƶ��������餤�����ʰ�ƣ���ˡ�2015/08/22�� ��� �֥������Υ��ȡ��פȥۡ��������ߥ���壷����ǯ����壴����ǯ���ϥ��⡼�����Υꥢ�ꥺ�������ء�¼������ ���������ꥶ�٥������֥롼����ˤ�뤿���ؤ�ʬ����ɾ���֥ϥ�ʡ������������פ���˥٥ȥʥ�����˿��줿�������ޤ���1965ǯ�������ؼԥϥ��⡼�������٥ȥʥ�����˴ؤ����ƹ�̳�ʤγ������������衢��������ʸ��ȯɽ�����ΤǤ���������ů�ؼԤΥϥ�ʡ��������Ȥ��⡼�����θ�����ٻ������Ȥ����ΤǤ����⡼�������������Τ��̥٥ȥʥ��Ũ�뤹��ΤϤ�ᡢ���λ�Ƴ�ԤǤ���ۡ��������ߥ��֥������Υ��ȡ��פˤ���٤����Ȥ����ΤǤ����̥٥ȥʥ�ΥϥΥ����ܤ���٥ȥʥ��ά���Ƥ��롢�Ȥ��������ܤβ��ϸ���Ǥ��ꡢ���⤽��٥ȥʥ�ϣ��Ĥι�ʤΤǤ��롢�ȡ���2015/08/16�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף����ۤΤܤΥ������ȥ����������ʥե�����������աˡ�  �����������ȥ����ե��ǥס��� ���ƥ��ϥե�ͤ����ˤȤäƤ⡢����äȤ������������ե�β����Ǥ�٤ߤ����ˤʤ�ȡ����㤵�ֺ����ϥס�����ƥ��ˤ��뤫���פʤɤȤ��ä�����Ω��������������Ƥ�º�ɤΤޤʤ����Ǹ��Ĥᡢ�Ҷ��������勞�勞���Ƥ���褦�ʥ�����β��������Ǥ��礦������2015/08/13��
�����������ȥ����ե��ǥס��� ���ƥ��ϥե�ͤ����ˤȤäƤ⡢����äȤ������������ե�β����Ǥ�٤ߤ����ˤʤ�ȡ����㤵�ֺ����ϥס�����ƥ��ˤ��뤫���פʤɤȤ��ä�����Ω��������������Ƥ�º�ɤΤޤʤ����Ǹ��Ĥᡢ�Ҷ��������勞�勞���Ƥ���褦�ʥ�����β��������Ǥ��礦������2015/08/13��
�Ķ� �����Ȼ䡡��������ʥ����ͥå��ռԡ�  ���������αƶ����ľ����轵���ͤ˵�����Ϣ��ƹԤ���Ƥޤ������줬�ٶ������ʤ������ܤ�������Ф��Ƥ褯�ܤäƤ����Τ�Ф��Ƥޤ�����������ǯ�������ܤϸ������Ǥ������顢�㤨�������¿����ȯ�Ž겣����줿���٤�����פʤΤ��ȻҶ����˻פä���ΤǤ�����2015/08/13��
���������αƶ����ľ����轵���ͤ˵�����Ϣ��ƹԤ���Ƥޤ������줬�ٶ������ʤ������ܤ�������Ф��Ƥ褯�ܤäƤ����Τ�Ф��Ƥޤ�����������ǯ�������ܤϸ������Ǥ������顢�㤨�������¿����ȯ�Ž겣����줿���٤�����פʤΤ��ȻҶ����˻פä���ΤǤ�����2015/08/13��
�ߤ롦��ࡦ���� �Dz�����ܤȸ�ȯ�פϤ⤦�����ˤʤ�ޤ�����������¼��  ������ǯ11�ϻ���ڤη��Ǿ�Ǥ����Ϥ���Ƥ���10�����ФΤ褦������˾�DZ�ư�������ꡢ����600�ս�ʾ�Ǿ�Ǥ��졢���θ����110�ս꤫��ͽ�����äƤ���Dz�Ǥ���
��2015/08/11��
������ǯ11�ϻ���ڤη��Ǿ�Ǥ����Ϥ���Ƥ���10�����ФΤ褦������˾�DZ�ư�������ꡢ����600�ս�ʾ�Ǿ�Ǥ��졢���θ����110�ս꤫��ͽ�����äƤ���Dz�Ǥ���
��2015/08/11��
ʸ�� ����ӥ���ι���إХ륫��Υ��ѥ��٤��ԻԤǸ��飲�����ȵ�������ͥ����вȡ�  ��������ӥ��ι�̱Ū���ʡإХ륫��Υ��ѥ��٤����ܿͤ��ɤ��餸��Τ������ܤ����ޤä������褽10���֤θ���ǽ��ޤä���ǥ�����150�Ҥˤ⤪��ӡ���Фο�����֤�����ī����ƥ�ӽб顢���Բ�����ӥ��ǰ������οͤȤʤ롣���ܤ�ȯ�����ˤϤ���ʤ��������⤷�Ƥ��ʤ��ä��Τ����顢�ܤ������϶ä������������˶�ʳ�������������뤳�Ȥˤʤä�����2015/08/09��
��������ӥ��ι�̱Ū���ʡإХ륫��Υ��ѥ��٤����ܿͤ��ɤ��餸��Τ������ܤ����ޤä������褽10���֤θ���ǽ��ޤä���ǥ�����150�Ҥˤ⤪��ӡ���Фο�����֤�����ī����ƥ�ӽб顢���Բ�����ӥ��ǰ������οͤȤʤ롣���ܤ�ȯ�����ˤϤ���ʤ��������⤷�Ƥ��ʤ��ä��Τ����顢�ܤ������϶ä������������˶�ʳ�������������뤳�Ȥˤʤä�����2015/08/09��
���� �������롼��ȷ�ˡ������Σ���������ͥ�����Ȥϡ����������롼���Ȥ�ʤ��Ȥ�ˡ�Ƥϲķ�Ǥ��� �����Ȥ����ǥͥåȤǤ褯����Τ�60���롼���Ȥäơ������Ǥε������Ǥ��ڤäơ�9��Ⱦ�Фι�����δ֤˽����ǺƲķ褹��ΤǤϤʤ������Ȥ��븫���Ǥ����Τ��ˤ���������ǽ��������ΤǤ���������������ˡ��褯�ɤ�ȡ���̱�ޤ��������Ǥ���ˤ�Τ���碌��ˡ�Ƥ�ķ褹�롢�Ȥ����ΤǤ����60���롼���Ȥ�ɬ�פ������ʤ��ΤǤ�����2015/08/09�� TPP��æ�������Хꥼ������� �ԣУ���ƻ���棲�������ͥ�å������ʤȥХ�����³���ʥХ������ߥ顼�� �� ����ꥫ�ξ���Ĵ�٤Ƥߤ�ȡ�����Ū�ʲ������ʤξ��ȡ�ͭ��ʪ�Ǻ��Х��������ʡʥ說����������ޡ��κ�˦��Ȥ����ʤʤɡˤξ��Ȥ��õ����֤��ڤ줿��³����Ф���Ƥ�̾����äƤ��ꡢ����Ū�ʲ������ʤθ�³�ξ����ͥ�å������ʡ��Х��������ʤξ��ϥХ������ߥ顼��bio similar)�ȸƤ֤����Ǥ���2010ǯ��ȯ����������ꥫ��Ϣˮˡ��Patient Protection and Affordable Care Act (PPAC Act)�Ǥ�FDA�ʥ���ꥫ���ʰ����ʶɡˤ�ǧ�Ĥ��飱��ǯ�֡��Х��������ʤΥǡ������ݸ���Ȥ���Ƥ��ޤ����������ڥǥ����ˤϼ��Τ褦�˽�Ƥ��ޤ�����2015/08/05�� TPP��æ�������Хꥼ������� �ԣУ���ƻ���� ��TPP�ʴ���ʿ�ηк�Ϣ�ȶ���˸�Ĥ��˥塼�������ɤ��դä����������Τ������ڹ�դ�������줿�ȿ�ʹ�Ǻ�����ƻ���줿�������Ǥ��͡���ʬ��θ�ľ�����������Ƥ����Τ�����������������ΤϿ����ǡ������ݸ���֤Ȥ���������Ǥ��롣ī����ʹ�ε����Ǥ��ƹ��12ǯ�����ܤϣ�ǯ���˥塼�������ɡ��������ȥ�ꥢ���ޥ졼�����ϣ�ǯ���ĥ���Ƥ���Ƚ�Ƥ���������Ͽ�����������������ۤɹ���Ȥΰ��Ϥǡ��ݸ���֤�Ĺ�������������Ȥ��̣���Ƥ��롣�Ȥ����ǡ�����ī����ʹ�ε����Ǥϡ��ƹ�ϥХ��������ʤˤĤ��Ƥ�12ǯ�פȤ������ˡ���Х��������ʤˤĤ��Ƥϡ�Ȥ��������ɽ����ȤäƤ���ΤǤ��롣����Ϥɤ��������ȤʤΤ�����������2015/08/05�� ʸ�� ������¼�Υե�������ף��������ܤ����������褿��ͳ�����������ʥե�����������ա�  �������ˤϼ�ʬ�Τ��θ�����������Ѥ��Ƥ��ޤ��в����롣��ï�����ä����Ϥ狼��ޤ������ʤ��Ȥ��ͤ�������Ĺ�����̤Ϥ������ä��ͤ˻פ��ޤ����������Ҥ���Ź�бĤ��Ф�����줫���ʤ˰ܾ������ͤϡ���˾�Τ��ʤ��ˤ��ޤ��������衢��⡢���֡��ջ֤Τ��٤Ƥ����������ե������Ź�ϡ�����Ȥϸ������̤ηбļԤ˰ܤ��Ѥ�ꡢ�����λ������ɸ�Ǥ��ꡢ��̤Ǥ⤢�ä���ʬ��ʬ�ȤȤ⤤����Ź�ޤϤʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ�������ʬ�ε��Ѥ䵤����������������Ϥ⤦�ʤ����ܤ����ˤ���ΤϤ�����ο����ؤ��¤Ǥ����⤦�ե���������䡢�����ͤ��������Τ�Τ���ʤ��ΤǤϤʤ������������ȡ���2015/08/02��
�������ˤϼ�ʬ�Τ��θ�����������Ѥ��Ƥ��ޤ��в����롣��ï�����ä����Ϥ狼��ޤ������ʤ��Ȥ��ͤ�������Ĺ�����̤Ϥ������ä��ͤ˻פ��ޤ����������Ҥ���Ź�бĤ��Ф�����줫���ʤ˰ܾ������ͤϡ���˾�Τ��ʤ��ˤ��ޤ��������衢��⡢���֡��ջ֤Τ��٤Ƥ����������ե������Ź�ϡ�����Ȥϸ������̤ηбļԤ˰ܤ��Ѥ�ꡢ�����λ������ɸ�Ǥ��ꡢ��̤Ǥ⤢�ä���ʬ��ʬ�ȤȤ⤤����Ź�ޤϤʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ�������ʬ�ε��Ѥ䵤����������������Ϥ⤦�ʤ����ܤ����ˤ���ΤϤ�����ο����ؤ��¤Ǥ����⤦�ե���������䡢�����ͤ��������Τ�Τ���ʤ��ΤǤϤʤ������������ȡ���2015/08/02��
ʸ�� �ƤΥ��㥺�ե������ۤ��С���������ʥ����ͥå��ռԡ�  �����ۤ��п����ƤΥ��㥺�ե����ϣ�������ǯ�Ρֹ�ݥ����ͥåȥե�����TAMA����פǡ������λ��˥��㥺�����ͥåȤ�Ϥ���ä����Ȥʤä������ɥ롢�Хǥ����ǥե�� Buddy DeFranco�������ͥå��ռ�) ��Ʊ�����ơ����DZ��ս��褿���Ǥ�����2015/07/29��
�����ۤ��п����ƤΥ��㥺�ե����ϣ�������ǯ�Ρֹ�ݥ����ͥåȥե�����TAMA����פǡ������λ��˥��㥺�����ͥåȤ�Ϥ���ä����Ȥʤä������ɥ롢�Хǥ����ǥե�� Buddy DeFranco�������ͥå��ռ�) ��Ʊ�����ơ����DZ��ս��褿���Ǥ�����2015/07/29��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����פ��ФΥ���٥��������������ʥե�����������ա�  ������������¼��֤����äƤ���ȡ����ܤǤϤ��ޤ긫�����ʤ�����ʥ���٥�Ȫ�˽Ф��路�ޤ�������������¼�ϥ���٥Ĥ�ͭ̾�ʻ��ϡ��ղƤνв��̤Ǥ������̤Ǥ����⸶�����������äʤȤ���������٥Ĥκ��ݤ�Ŭ���Ƥ���ΤǤ�����ȩ����ʿ�Ϥˤ����ƹ����륭��٥�Ȫ�ϡ����ε��ᡢ��������ޤ��ޤ��������ơ�����٥�Ȫ����˾��⤤�֤�����ޤ��������ϡְ��ʤε֡פȸƤФ�Ƥ��ޤ���ǯ�˰����������ؤ����ޤäơ��ˤ��ʤ˰��֥��٥�ȡ֥���٥��塼�פ��Ԥ��ޤ�����2015/07/28��
������������¼��֤����äƤ���ȡ����ܤǤϤ��ޤ긫�����ʤ�����ʥ���٥�Ȫ�˽Ф��路�ޤ�������������¼�ϥ���٥Ĥ�ͭ̾�ʻ��ϡ��ղƤνв��̤Ǥ������̤Ǥ����⸶�����������äʤȤ���������٥Ĥκ��ݤ�Ŭ���Ƥ���ΤǤ�����ȩ����ʿ�Ϥˤ����ƹ����륭��٥�Ȫ�ϡ����ε��ᡢ��������ޤ��ޤ��������ơ�����٥�Ȫ����˾��⤤�֤�����ޤ��������ϡְ��ʤε֡פȸƤФ�Ƥ��ޤ���ǯ�˰����������ؤ����ޤäơ��ˤ��ʤ˰��֥��٥�ȡ֥���٥��塼�פ��Ԥ��ޤ�����2015/07/28��
ʸ�� ������¼�Υե�������ף����������ʥե�����������ա�  ����������ϳ��������Ӥʤ���̴����Фᡢ�ʤ����줿����ƥ��������Ǥ��顢��Ω��3ʬ�ۤ��⤯�ȿ�������塣������ī���Ϲ������ä����������ʤɤȹͤ��ʤ��顢������Ӥ��Ϥ�ϭ������ߡ���ʬ�Υǥ����˸������ޤ�������������¼�ˤ���230���ۤɤΥ���ȥۥƥ�ǡ���������������������ȥåץ�������ˤϡ���īͼ��600̾ʬ�ۤɤο��������ޤ����ͤ�̾���ϸ����������������ȽƤ�����Ǥ����ե�������ˤ�������25ǯ�������ͤǤ�����2015/07/25��
����������ϳ��������Ӥʤ���̴����Фᡢ�ʤ����줿����ƥ��������Ǥ��顢��Ω��3ʬ�ۤ��⤯�ȿ�������塣������ī���Ϲ������ä����������ʤɤȹͤ��ʤ��顢������Ӥ��Ϥ�ϭ������ߡ���ʬ�Υǥ����˸������ޤ�������������¼�ˤ���230���ۤɤΥ���ȥۥƥ�ǡ���������������������ȥåץ�������ˤϡ���īͼ��600̾ʬ�ۤɤο��������ޤ����ͤ�̾���ϸ����������������ȽƤ�����Ǥ����ե�������ˤ�������25ǯ�������ͤǤ�����2015/07/25��
���� �ҷ����ܺ�� �͡������ɲ�ˤĤ��ơ�  �����ҷ����ܺ�� �͡��ե��¿���Υ�ǥ�����ѵҤ��ǹ����ɾ����������Ω���̡פ˴�ư���Ƥ��顢���ǯ���ޤ������Υơ��ޤǤ��ʤ���ȿ�������������Ȥϡ�̴�ˤ�פäƤ��ޤ���Ǥ�������������������Ϥ���饸�����Ȥ����ɲ�ˤĤ��Ƥ��Τ褦�˽Ҥ٤ޤ������ʴ�ơ���Ryoka)��2015/03/10��
�����ҷ����ܺ�� �͡��ե��¿���Υ�ǥ�����ѵҤ��ǹ����ɾ����������Ω���̡פ˴�ư���Ƥ��顢���ǯ���ޤ������Υơ��ޤǤ��ʤ���ȿ�������������Ȥϡ�̴�ˤ�פäƤ��ޤ���Ǥ�������������������Ϥ���饸�����Ȥ����ɲ�ˤĤ��Ƥ��Τ褦�˽Ҥ٤ޤ������ʴ�ơ���Ryoka)��2015/03/10��
���� ���Խ�Ĺ�Ѹ������λ����˻פ������ο��ʤΤ�ȿ�ե���������������ط��Ť�����Ȼפ��Τ����������¶� ���ʥ��������Ƭ��������礭���װ��ˡ������ι�ݶ��������ư�������Ҳ�ե��������������롣�Ҳ�̱�����ϥե�������ΰ���Ǥ���Ȥ��ơ�������Ϥ�ؤäƤ����ɥ��Ķ����ޤϼҲ�̱�����ԡ���٥���ؤ˹����ä������ҥȥ顼������Ω���������ޤȼҲ�̱���ޤι���ʿ��ϥʥ�������äƤ�������2014/01/22�� ���������ڤ��� ���������Ρ֥˥塼���ԡ����ס���������̩�ݸ�ˡ�Ρ����ϡפȡ֤��ġס�����̱�ޤȴ�ν�����ܸ���Ф��빶�⤬³�� �����������Ѥ��褦�Ȥ��Ƥ�������������������������ܸ���Ф��빶��Ϥ�ळ�Ȥ��ʤ������Ѷ�Ūʿ�¼���פȤ������դ��ܼ������衢�⤷������Ʈ�٤ˤ��롣�����ʿ�¤Ȥ������դ���������Ǥʤ������դ��Ф��빶��ȸƤ�Ǥ⤤�������������Ǥ�¿���οͤ���Ŧ����褦�ˡ����硼�������������뤬̤�跿�Ⱥ۹�Ȥ��������ӣƾ���֣�������ǯ�פǶ��פ���������֥˥塼���ԡ����פ����줹����դǤ��롣�˥塼���ԡ����ξ�ħŪ�ʥ���������ϡ������ʿ�¤ʤꡡ��ͳ���콾�ʤꡡ̵�Τ��Ϥʤ�פǤ��롣�Ѷ�Ūʿ�¼���Ϥ����Ʊ���θ��դǤ��롣��2014/01/13�� ���������ڤ��� ���ܤΡƽ��ǤϻҶ��ͻ���٤����������Σȣ˷бİѰ��ˤʤä��ؼԤ������������˽����ѵ������ˡ������ ������������������������NHK�бİѰ��Ȥʤä�Ĺë���һ�����ܤ��˽��ϡ㤷����٤�ǯ���Ƿ뺧���ƻҶ��ϣ������ͻ���٤����Ȼ��Х˥塼���Υ����֥����ȡ������ˤ�ȯ�����Ƥ��롣�������ʤ��Ⱥ��ν���Ψ�Ǥ����ȡ���������ǯ������ܿͤ������ˤʤäƤ��ޤ��Ȥ���������Τ褦���������顢���θ����ˤʤä��˽����ѵ������ˡ���ѻߤ��衢�ȼ�ĥ���Ƥ���ΤǤ��롣��2014/01/09�� ���������ڤ��� �����ԥå��ȷ��������ź�ȷ����������� ���˥塼�衼�������ॺ�ˤϺ�ǯ����������dz�����륽�����ߵ������ԥå��ˤ��ʤ������̡�褬�Ǻܤ��줿����֤˾�ꡢ�Ƥˤ���ä�ʼ�Τ��ɤ˸��ؤΥݥ���������դ����Ƥ��롣�����ˤϡ�A celebration of the joyous human spirit!'�ʳڤ�������ο��ν�ŵ���ˤȽ�Ƥ��롣��֤�ʢ���ˤ��礭��SECURITY(�������ƥ��ˤȽ�Ƥ��ꡢʼ�Σ��ͤ����Ϥ�ƻ뤷�Ƥ��롣�����θ������˥������Ǥϥƥ����郎ʣ�������Ƥ��롣�ڤ�����ŵ�ȡ���Τ�Τ����ٲ�������̷�⤷�Ƥ��뤳�Ȥ����������硣��2014/01/07�� ���� ���������������̱�դ��ä�ȿ�Ǥ����������٤ء�����������θ�ľ�������������ˡ�Ƥ��Ф����̱��ɼ�ʥ����å����١ˡ���Ԥ��������� ��������̱��¿���δ�˾��ȿ���ơ����Τ褦��Ϳ�ޤ�˽�����뤳�Ȥ��Ǥ��������Ϥ����Ĥ����롣�����ǣ����Ȥ����������������٤�����ʾ����������̱�դ�������ɽ�����Ƥ��뤫�˭�������֤������ȹ��ǤΥơ��ޤΤ��쭣��Ԥ������Ի��äǤ����¼�������ˡ�2013/12/07�� ���ȿ� ��Ʀ�ΰ����ݾ�����С��Һ� ��Ʀ�ϸ����ޤǤ�ʤ����ܤο�ʸ���ˤ������פΰ��֤����롣��Ʀ�Ǻ�ä�̣���䤷�礦�椬�ʤ�������ܤο�������Ω������Τ�������������������Ʀ�����ܤ����Ȥ�ͭ��Ū�ʥ�������ΰ�����ʤ����פʺ�ʪ�Ǥ⤢�ä�������������������ܤ���Ʀ�������ϼΤƤ�줿�ޤޤ�����2013/07/10�� TPP��æ�������Хꥼ������� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۣԣУФ�ʿ��Ū��¸���� �����������ϡ���������ܹ�ա�ǯ�����Ȥ����ƹ��Х��������ߤ������������˱�ä�TPP���ä˸��������Τ����ͤ��ʤ�Ǥ��롣�����ͽ�ꤵ��Ƥ��뻲�ı�����Ǥ��������ȯ�Ʋ�Ư��͢�п�ʤȹ�碌�ƣԣУл��ä������Ĺ��ά����˷Ǥ��롣������ơ��ԣУФȤϲ���������ϻ䤿���Τ��餷�ξ졢Ư����ˤʤˤ�⤿�餹�Τ���ͤ��Ƥߤ롣��2013/06/18�� ���� dz���������⸶����������ʲ���������������ʿ�İ��Ի� 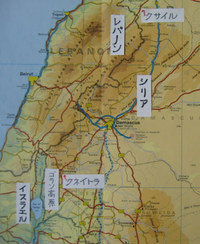 ��2013ǯ6��10��������ꥫ�ȥ������δΤ���ǡ㥷�ꥢ�����ݲ�ġ䤬���Ť����ͽ����ä��������ꥢ���ܡ����ꥢȿ������ɽ����Ϣ������ꥫ����������EU �ʤɤ����ä��ơ���餬�����Ȥ����Ρ㥷�ꥢ���������ܻؤ����Ȥ��Ƥ����������ȹ�ݵ��ؤ���������礬����ʡ㥷�ꥢ�����������Ʈ�����������Ǥ��ơ��㥷�ꥢ������㥷�ꥢ�����ȸƤ֤Τ�̵��Ǥ��ƨ��ƻ���äƤ���Ȥ����פ��ʤ�����2013/06/10��
��2013ǯ6��10��������ꥫ�ȥ������δΤ���ǡ㥷�ꥢ�����ݲ�ġ䤬���Ť����ͽ����ä��������ꥢ���ܡ����ꥢȿ������ɽ����Ϣ������ꥫ����������EU �ʤɤ����ä��ơ���餬�����Ȥ����Ρ㥷�ꥢ���������ܻؤ����Ȥ��Ƥ����������ȹ�ݵ��ؤ���������礬����ʡ㥷�ꥢ�����������Ʈ�����������Ǥ��ơ��㥷�ꥢ������㥷�ꥢ�����ȸƤ֤Τ�̵��Ǥ��ƨ��ƻ���äƤ���Ȥ����פ��ʤ�����2013/06/10��
���� �������Ȥθ��������ǧ�� �������塡�� �����ܰݿ��β�ζ�Ʊ��ɽ�Ǥ��붶������Ĺ�ν����ְ��ؤˤĤ��ơ��������Ϸ��ε�Χ��ݻ����뤿���ɬ�פ��ä��ס��ֲ�����α�Υ���ꥫ�����ᴱ����¯�γ��Ѥ�ʸ������פȤ���ȯ�����Ф����⳰����Ƚ����ޤꡢ�褯���������Ȥμ����Ȥ������֤�Ķ��������ˤʤ�ĤĤ��롣�����طʤˤϰ��ܼ�����о�ʹߤˤ狼�˶��ޤäƤ���������Ūȯ�����Ф����⳰����Ƚ�����롣������������æ�Ѥ��ĥ������ܼ�������ȯ�����Ф���ٲ����ǰ�ȸ��äƤ⤤����ΤǤ��롣�⤦�����ܤ����������������æ�Ѥ������ؤβ����뤤�������ι���Ūɾ���Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥؤ���Ƚ�Ǥ��롣���ܹ��ˡ������ˡ�դβ����Ȥ�������Ūư�����Ф���ٲ��⤢�롣��2013/06/03�� �к� ���Խ�Ĺ�Ѹ�������Ծ�dz���˽��ȥޥ͡�˽���ɤλϤޤꡩ���������¶� ��23������������Ծ������ʿ�ѳ�����˽�������������2000ǯ����17����1426�߰¡˰���ǡ�����11�̤��礭����Ͽ����������˽���ɤ��ߤ뤫���Ծ�ط��ԤΤۤȤ�ɤϡְ��Ū�ʲ���ˤ����ʤ��פȤߤƤ�������п�ʹ���Ƥ��롣�̤����Ƥ��������ɥޥ͡�˽���ɤλϤޤ�Ȥϸ����ʤ������������¶��ˡ�2013/05/23�� ���� ������Ϻ������Ƚ�Ϥޤ����ߤ�����Ū����Ǥ���ʸޡ� �������ε������顡������Ϻ������Ƚ�����ܤ��������ϡʣ��ˡ������塡�� �������ϡַ�ˡ�γ˿��ϸ��Ϥ�����Ǥ���פȸ��äƤ����͡�����Ϸ�ˡ��ˡ�ˤ��������Ϥ������Τ����ƻ��ǤϤʤ������Ϥ����¤�������ƻ��Ǥ���Ȥ������Ȥ������櫓�������줬��̱�λ��ۤȤʤäƤ��ʤ��Ȥ����������줬���Τ�������ΤȤ��Ƥ�¸�ߤ��Ƥ��ʤ������������ˤ��Ƥ�������Ƥ���������2013/05/06�� ���� ������Ϻ������Ƚ�Ϥޤ����ߤ�����Ū����Ǥ������ˡ������塡�� ���������ܤ��������ϤϹ�̱�������ջפˤ�ä���ɽ�Ȥ������Ф줿��Τǹ�������Ƥ��롣�Ȥ��������֤����¸�ߤ��롣��ȸ��Ϥ�ŷ�Ĥΰջפˤ�äƷ�������Ƥ���Ȥ���������¸�ߤȤϰ㤦������ˡ����̱�縢������ˡ����Ȥη��֤�ȤäƤ��뤳�ȤǤ⤳�Τ��Ȥϸ����뤳�ȤǤ��롣��2013/04/16�� TPP��æ�������Хꥼ������� ���Խ�Ĺ�Ѹ��۴ڹ�μ��ץ�ǥ����ϡ����ܤ��ԣУФ����롢�ڹ�Ͼ���٤��ʡפȰ��Ƥ˼���ǽƤ���Ȥ������������¶� ���ڹ�ȥ���ꥫ�μ�ͳ�ǰ��ꡢ���ƣƣԣ���ȯ�����ƺ�ǯ��������ǣ�ǯ���вᤷ�����������ܤǸ�Ļ��ä�ᤰ�ä���������ȤʤäƤ���ԣУСʴ���ʿ�ηк�Ϣ�ȶ���ˤϼ¼�Ū�����ƣƣԣ��Ǥ���Ȥ���졢���ܤ��ԣУФ˻��ä�����硢�ʤˤ������뤫���Τ뤿��ˤϴ��ƣƣԣ���ߤ�٤����Ȥ����Ƥ��롣�����ǡ���֤���̱���ͤ��ȸ��äƣ����ꡢ�ڹ�ؽФ���������2013/04/14�� ���� ������Ϻ������Ƚ�Ϥޤ����ߤ�����Ū����Ǥ���ʰ�ˡ������塡�� ������������ˡ��ȿ�פ��Ƶ������줿������Ϻ�κ�Ƚ��������Ƚ���ä������Τ��ȤϤ��θ������Ǽ�̱�ޤ���������䡢���줤���äѤ��˺����줿�褦�ʰ���������Ƥ��뤳�Ȥˤ褯������Ƥ��롣����Ū���Ѳ��ͤ�����ä��Ȥ��Ƹ���¦����ϸ��ΤƤ���褦�ˤ��롣��ˤ�ή��⡢������ή���®���������ή���������Ȥ�������Ǥ���褦�ˤ���ۤ��ʤ���꤫��Ϥ����˺�줵�����Ƥ������֤ȴ��������뤳�Ȥ��������Ϥ���֤Ǥ����ǥ����Ϥ褯�ΤäƤ���˺�Ѥ���������餸�Ƥ���Τ���������2013/04/13�� ���� ��ˡ96�������ư���ᤴ�����ȤϤǤ��ʤ� ���������塡�� �����٥Υߥ����ȾΤ����к������ԥǥե�æ�ѤΤ���ζ�ͻ����������Ĺ��ά�դ���̬�ˤ��Ʒ�ˡ����������������Ȥ��������������ܲ����������줹�롣�ޤ��ϷкѤ����Ȥ����̤˷Ǥ��Ƥ���������κ���Ū���������ۤ˷�ˡ�������֤���Ƥ��뤳�Ȥ�ï�⤬�ΤäƤ��뤳�Ȥ�������������ư������ˡ96�������ư���Ȥ��ƽФƤ��Ƥ���Τ������ܤξǤ���˸��Ƥ���ͤ�¿�Ȼפ��롣�����˿��Τ������Τ����������ᤤ�����˷�ˡ������ƻ�ڤ�Ω�Ƥ��֤������Ȥ������Ȥ������ļ��Ҹ��ιԻȤ˼��夷����ˡ9��ι�ȴ���ä����ʤ�褦�Ȥ��뤳�Ȥ�Ʊ�����ȤǤ��롣��2013/03/15�� �ˡ������� �����㵤���ȸ�ȯ������ʪ�������������� 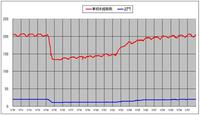 ��������������������Ǥ��������⤿�餷�������㵤��ʡ����츶����ȯ�Ž��������ʪ���Ϥɤ��ʤä��Ǥ��礦��������Ϥ��������Ƥ����������̤�¬���ͤ�ߤƤߤޤ�������2013/02/11��
��������������������Ǥ��������⤿�餷�������㵤��ʡ����츶����ȯ�Ž��������ʪ���Ϥɤ��ʤä��Ǥ��礦��������Ϥ��������Ƥ����������̤�¬���ͤ�ߤƤߤޤ�������2013/02/11��
�ϰ� �ڰ���ë����ۤ�Ϥ�ФƤ����������ɸ����ġ��� ����Ϥꡢ�ȸ����٤����������̤����������Ϳ�ޤ���夬�ä��� ��2013/01/22�� ���� ���¤��������Ҳ��̤�衡�����ʣ��� �������Ȥ������դ�ή�ԤǤ��뤬�ġ��������塡�� ��������������������Ω�ȤȤ��ή�Ԥδ��Τ��뱦������ᤰ�äƱ�������Ҥȥƥ�Ӥ�Ƥ��������������������Ω�ȤȤ�˳������뤤���������Ф����Ǥ��Ф��������Ƥθ�ư�ˤ������ơ�����Τߤʤ餹������ⱦ�����Ȥ����ٲ��������ǤƤ��롣������г�Ū�ˤ�̱²���Ū�ǹ�ȼ��Ū�ʡ�����������Ū�ˤ϶������Ū�ʿ��̤�ǻ���������Ǥ��Ф���Ƥ��뤳�Ȥؤη�ǰ�Ǥ��롣���ս�����������������������ī�����Ф����з�Ū�ʻ�����������Ƥ��뤳�ȤǤ��롣�ޤ�������ǤϷ�ˡ��������ĥ���졢������Ȥ��ܻؤ��Ȥ���Ƥ��롣��̱�ޤȤ����ݼ����ޤ������ǥ�٥���ɤ���Ĺ�����ݼ�̱²�ɤη��������ޤäƤ���ΤǤ��롣7��λ��������������ޤǤϤ���������ĥ�����̤ˤǤƤ��뤳�ȤϤʤ��Ȥ���Ƥ��뤬���ɤ��ʤΤ����������к�������ͥ�褵���Τ������к��������������ܤ�����������̷��ˤ��äƸ��¤ˤ϶��β����ʤ�ˤ����Τ�����2013/01/21�� ���� ���¤��������Ҳ��̤�衡�����ʣ��˲ָ���ηкѤȤ������դ�פ��Ф������ġ������塡�� ���㤤�ͤ����Ϥ��ޤ��Τ�ʤ����⤷��̤��ͤ��ǯ��ǤϤ褯�Τ�줿���դ��ֲָ���ηкѡפǤ��롣1960ǯ�θ�����ļ���ϡֽ��������ײ�פ��Ǥ��Ф�������Ĺ�ϤϤ��ޤäƤ�����1962ǯ������ī����ʹ�μ紴�Ǥ��ä�����Ϻ�Ϥ��ι�����Ĺ�˵�ǰ�������ֲָ���ηкѡפȤ�����ɾ���ΤǤ��롣����Ͽ�����ĥ�ˤ��Х֥�Ǥ��ä�����ʷк���Ĺ�ǤϤʤ��ΤǤϤʤ������Ȥ����������ä���������ɾ�Ϥ��θ�ι�����Ĺ�ο�Ÿ�ǥϥ���Ȥ����뤬���Х֥�кѤȤ��������Ǥ����ä��Ȥ�����롣1960ǯǯ��ν��Τ����ȸ��ߤȤǤϷкѵ��Ϥ����Ȥߤ�㤦���顢���ηк�ɾ�Ϥ��Τޤ��Ѥ����ʤ������������ηк������ι���������Ȥ�����¿ʬ�ˤ���Ȼפ�����2013/01/09�� ���� ���¤��������Ҳ��̤�衡�����ʣ��ˡ����ܷк���ά�δ������������塡�� ���ַкѤκ���ͥ��ס�ï�⤬�����Τʤ������ʤȤ���������ˡ�������ƹ��ɷ�������������롢���ļ��Ҹ��ԻȤ���ǧ����ʤɤ���٤��顣��������������ȤƤߤ�Ȥ����˵�ǰ���ФƤ��롣�פ���ˤ������������ƤФ�ޤ����ʵ�������������롢���ζ��κ����������Ȥȸ���̾���ڷ���ȤȤ����櫓�Ǥ��롣����Ϸк�Ū���Զ����٤˱餸�������ư���ͻ�����Ȥ�������Ū�ʡ��ˤʹ�Ȥβ������Ǥ��뤬�����Ū�ڶ�ʹ�Ĥ����ѻĹ�ˤ��������Ĥ��Ƥ����ʤ������ܤǤϥХ֥�кѤ���þ�Ȥ��θ�˼���줿20ǯ�Ȥ�����̤����Ƥ��ĤäƤϤ��뤬������Ū��æ��ϩ�ʤ��ޤޡ������̴��ߤ�褦�ʡֹ�����Ĺ�פθ��Ƥ���ư��ؤ�ť�¤ؤ�ƻ��ʤ������Ǥ��롣��2013/01/04�� ���� ���Խ�Ĺ�Ѹ��۶˱����������ȼҲ�ư���������¶� ���˱������������ǯ����������7��λ�������η�̼���ǤϷ�ˡ�����ǯ��ˤ⸽�¤β���Ȥ����ܤ��������äƤ�����������������Ϥ���ʬ�����Ķ����������������̤�ɤ����뤫��������ʻ�¤����ʬ�Ϥ�����������������Ȥ⤽����˿Ȥ��֤��Ҳ�ư�ξ줫�顢�ʤ������ʤä�����ͤ��Ƥߤ�������2013/01/01�� ���� ���¤��������Ҳ��̤�衡�����ʣ�)�������������ܤ�̱²�����Ķ�����뤫�����塡�� ��̱�������������̤ϲ���ļ��ʤ�������ǰ�˴�Ť���Τ�¸��Ǥ��ʤ��ä��Ȥ������Ȥ˿Ԥ��롣�¸��Ǥ��ʤ��ä��Ȥ������ϼ���Ū�ʻ�ߤ���Ǥ��ʤ��ä��Ȥ������Ȥˤۤ��ʤ�ʤ����ͤ�̱���ޤ��������������Ƥ������������ƴط��θ�ľ���ˡ������Թ�̱�����褬���ա����ϱ��ѡʴ�ν��Ƴ������ž���ˤ�ɾ�����Ƥ���������������Ū�˻�ߤ������ΤȤ��������������θ��������Ѥ������˲��̱���ޤ��̡��οȤ��դ���������ǰ�ˤʤäƤϤ��ʤ��ä��Τ��Ȼפ������������ˤ�ꤿ�����Ȥ��ʤ������뤤�Ϥ狼��ʤ��ä��ΤǤϤʤ����Ȥ�����ǰ���褷�Ƥ������ΤϤ��Τ��Ȥ��ä�����2012/12/29�� ���� ���¤��������Ҳ��̤�衡�����ʣ��ˡ������塡�� ��ʡ��dz����줿�ɣ��ţ��ʹ�ݸ����ϵ��ءˤβ�Ĥؤ�ʡ��ν��������ι��Ĺ�ư�ٱ�ε���ΥХ�����������̤ˤĤ��Ƥΰ����ʹ������18��������Ȥ���������̱�ޤȸ����ޤ���ɴ�����ꡢ̱���ޤϻ��Ԥ��Ȥ������Ȥ��ä����ۤܡ������̤���ä������μ�Τ��Ȥ˴ؤ�����ƻ��Ĵ�������Τ��˶ä�����롣���𤷤��Τϸ���10�����������ƻ�κ�����ä������Ĥ�ʤ顢�ܤ�ţ�Ť��Τ褦�ˤ��ƥƥ����ƻ��ߤƤ��뤬�������ȸ�����������˿��������Ĥ�Ϸ빽�٤��ޤǵ����Ƥ��뤬���ܤ��ɤ�ˤ�ʤ줺���Ĥ����ä����ʤ��ʤ����դ��줺�Ŷ줷��ʷ�ϵ�����Ǥޤɤ���Ǥ��������Ф餯�Ϥ��ε�ʬ��³���Τ������ȡ��פ�����2012/12/27�� ���� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۺ���ζ�줵�����δ�æ��ȯ��ë����������ο����ϼ��ä��줿�����褤���ȡġ��������¶� �����δݤ�Ǥ���æ��ȯ���㤬����ˡ������æ��ȯ����ӤĤ����Ȥ˷ٲ������ˤ���������ɽ�ʤο�ë��������������ͦ����Ĺ�������η�ˡ�˴��������ˡ���ꡪ��������Ρ������ߡ��פȥĥ��å����ǤĤ֤䤤�Ƥ��롣��ë�������ر������æ��ȯ�٤ˤϺ���ζ������ʸ�����æ��ȯ�˱��⺸��ʤ��פȽƤ��롣������������ǡ���ˡ��ʿ��Ū��¸���ϴ������ʤäƤ��롣��ë�������������ζ����æ��ȯ�ȷ�ˡ��ʿ��Ū��¸������ʪ���ȤǤ⤤���Τ�����������2012/12/27�� ���� �ݼ�ȿư�λ��夬��äƤ����ʤ�ƾ��̤��Ĥ������������塡�� ���ޤ������κ����ݼ�ˤ��ݼ�ȿư�Ȥ������դ��ꤲ�Ĥ���Ƚ���Ƥ������ݼ�ˤ⤤���������뤳�Ȥ��狼��ʤ��ä������Ȥ�������ΤäƤ�ʬ�������ȤϤ��ʤ��ä��������餫��˲��ͤ��ǡ��ݼ�ȿư�γؤ��ܡ١�����ҡդ�Ф�������2012/11/24�� ���� ���¤�̤��ʤ��Σ��˿��ơ����������ʸ��ɤδ�ν��Ū������Ƚ�Ȥϡ������塡�� ���Ƕᡢ˴���ʤä��㾾���˴��Ĥϸ�ǯ��ͥ�줿���ʤ���������Ф����ؤβ֤�餫���Ƥ�����ʸ�ؤ�ݽѤ˺Фʤ�ƴط��ʤ��褦�������ˤ�ط��Ϥ���ޤ����и�����Ϻ�����ޤη����ȹ������ä�֤��夲�����Ȥ��Ф���Ϸ���Ȥ��������⤢�뤬����Ϥʤ��Ȼפ�����ϼ��ν�������ͺ���Ȥ�������������Ω�ˤ�뺮�¤Ȥ�������������ˤ����������ͤ��褷��ʬ�ν��֤����롢��Ƨ����Τ��⤷��ʤ����и�����Ϻ���ɤΤ褦�������ӥ����ȹ��ۤ���äƤ���Τ������뤤�Ϥ������ɽ���Ƥ���Τ��Ȥ������Ȥ������٤��Ǥ��롣��2012/10/30�� ���� ���Խ�Ĺ�Ѹ����Ϥ����������������ƥ�ȼҲ�ư���������¶� �������饹����ߥ�����Ρإ�ǥ����롦�ǥ⥯�饷���٤��ɤ�ľ���Ƥ��롣�������Хꥼ�������ǹ�̱��Ȥ����Ƥ��������ȼ����Ȥ�����Ȥ�����Ω���Ƥ����IJ���̱�����Ȥ����������Ȥ�������ʬΩ�Ȥ�����Τ�����̱����Ū���������ƥब�Ϥ������äƤ��롣���ܤ����������Ϥ���ŵ���Ȥ����롣��2012/10/29�� ���� ���¤�̤��ʤ��Σ��ˡָ�ȯ��¸�Ҳ��ž���פΰ�̣���䤦�������塡�� ������ͽ����ή�Ѥ���ƻ����Ƥ��뤬������ˤ϶ä����̤ꤳ�������Ƥ��ޤ�����������̺Ҥ����������������������ܤ�ƻ����ꤷ�ƹԤ��Ȥ�¿���οͤ���äƤ������Ȥ�������������ͽ���μ��֤Ƥ���Ȥ���Ȥ���Υ�줿�������ܤ����������뤫��ʬ����Ȥ�����Τ��������Ȥ���̾�ˤ��ͽ����ʬ���ȼ��ԤϺ����٤Ǥ��롣��Ⱥ����Ǥ��롣��ȯ�̺Ҥ�����������Τ��ޤ�ΤҤɤ��˱��줬���˸�������̺Ҥ���������������Ϥ��������ʹ���Ф����٤�����Ƥ����������������Ƥ���Τ�����ͽ���μ��֤Ǥ��롣����Ϥ������˴ط��Τʤ�ͽ���Ǥ���С�������̤�Ω�Ƥ�Ф����ΤǤ��äơ��������������ޤ����ι٤Ϥ���٤��Ǥ��롣��2012/10/23�� TPP��æ�������Хꥼ������� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۤ��餷���������TPPȿ�б�ư�������¶� ��������ư�Ȥ���Ÿ������Ƥ���TPPȿ�б�ư�����������������ܤ�ư�������Ǥʤ����������Ծ졢ˡ���٤����Ǥ�TPP���������äƤ��뤳�Ȥ����դ�ʧ���٤����������ƹ����ܤΰո����ɤ��Ρ����������Ϥɤ����뤫���ʤɤȤ��ä�Ⱦʬ���ɤ˿�����褦�ʱ�ư�ǻ��֤�ư���ʤ��Ȼפ������������θ��졢ϫƯ�θ���Ǥ���¸��������Ʈ���Ȥ��Ʊ�ư���Ȥ�ľ����������Ƥ��롣��2012/10/15�� ���� ���¤�̤��ʤ��Σ����ƹ���ͥ��������ά���������ꡡ�����塡�� ���ɣͣ���������Ƥ��뤬�����ξö�Ū�б�����ޤäư��ݤ��������ؤ��饴��Ȣ��ű��줿�ꤷ�ơ��ٻ��η�����������Ω�Ĥ����Ǥ��롣���ܤ˲����ٱ�ε�ж��Ф������������Ū�Τ褦������Ǥ��ꡢ����ꥫ�θ��ؤ�����ܤϤ�äƤ�������Ƿ�ɤΤȤ������줷�������ʤ����ţդ˥Ρ��٥�ʿ�¾ޤ�������Һ�Ȥ˥Ρ��٥�ʸ�ؾޤ�����줿�Τϸ��ߤ�����������դߤƤΤ��Ȥʤ�ɤ����ͤ�������Ȥ��������롣�ţաԲ�����Ʊ�Ρդμ�����ͳ�������ȿ�ʤ�ʿ�¤��²���ɵ�Ǥ���Ȥ����ΤϤʤ��ʤ���̣���Ǥ��롣��2012/10/15�� ��� ��ʿ�İ��ԻҤ��ܡ۴��������Хޡ������ޤ�������夬��ʤ�2012ǯ����ꥫ����������  ���֥勵����������������ɼ�ǥ��ʥ����פȡ���������ꥫ���Ͳμ�Υ���å�������ɮ�Ԥ����ä��Ƥ��������ֿͼﺹ�̤��줿���פȡ�ʹ���֤��������Ժ���ɼ�⥦�����ߡ��������å��פȡ�����å����������������11��6���ޤǡ�3���֤⤢�뤸��פ�ɮ�ԡ���2008ǯ�λ������������ǥ��OK�����ɡ���ǯ��2�������������ߥ��å����ڥ�Х˥���ˡ���ѥå��͡פȡ�����å��������֤��ۤ����פȡ�ɮ�ԡ���2012/10/14��
���֥勵����������������ɼ�ǥ��ʥ����פȡ���������ꥫ���Ͳμ�Υ���å�������ɮ�Ԥ����ä��Ƥ��������ֿͼﺹ�̤��줿���פȡ�ʹ���֤��������Ժ���ɼ�⥦�����ߡ��������å��פȡ�����å����������������11��6���ޤǡ�3���֤⤢�뤸��פ�ɮ�ԡ���2008ǯ�λ������������ǥ��OK�����ɡ���ǯ��2�������������ߥ��å����ڥ�Х˥���ˡ���ѥå��͡פȡ�����å��������֤��ۤ����פȡ�ɮ�ԡ���2012/10/14��
���� ���¤�̤��ʤ��Σ��˺������餳����ˡ9������� ��æ�ʥ���ʥꥺ��Ȥ��ƤΥ�����������ۤ��롡�����塡�� �����ܤ������θ�˼���Ȥ������Ĥ����Τ�2006ǯ�Ǥ��ä�����Ϸ�ˡ�������礭�ʲ���Ȥ�����������������ͤʴ���������������������ԥ쥸����դ����æ�Ѥ��濴�ˤ����ΤǤ��ꡢ���������ǰ��ӥ����ȸ�����̣�Ǥ��������ä��Τ��ȸ����롣���ΰ��ܤ���ؤ��ɤ����ޤ����֤ˤĤ��ƤϤ��餿��ƽҤ٤�ɬ�פ��ʤ���������ΰ��ܤ����ĤȤ����������ΰ㤤�ϳ�ǧ�����֤�ɬ�פ����롣����ϰ���Ǥ����С����ս������������Ȥ�����������꤬�礭����夷�Ƥ��뤳�Ȥǡ����ĤƤη�ˡ�����ʤɤ����ʹ��Ϥɤ��ʤä����Ǥ��롣��2012/10/09�� ���� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ְۡ������ۡ���ˡ�������������ס������������¶� ��������������俷ʹī������2�ʡְ������ۡ���ˡ�������������ס����ܤλ����Ի��������塢̾�Ų���������������̱�ޤ������ְ��ء�����Ի��Ϥʤ��ä��Ȥ�����ˤ�̵�뤷���ӳ��������˾�ü���Ƥ��롣��2012/10/02�� ���� ���¤�̤��ʤ��Σ��˾���������ϩ���ˤ����Τܤäƹͤ��롡 ���塡�� ����̱�ޤ�������������ˤʤ�Ϥ�������Ϥޤ������ܿ������ФƤ���Ȥϻפ�ʤ��ä���ë�������ۤ������Ф��з�ˤʤ�Τ��ȻפäƤ��������ܤκ��о�ˤ�����������̱���������Τ��餷�ʤ�������Τ�����̱���ޤ�����ϩ������ά�դˤ��ĤƤξ���������ϩ���ؤβ������뤫�餳��Ϥ����̣�������ε���Ȥ�����Τ����Τ�ʤ����츫�����ʣ������������̤��Τ��Ȥ����ػ볦���ɤˤʤ�褦�˸����뤬���ͤ�Ϥ����Ǿ���������ϩ�����о줷��2000ǯ�ν��̤ޤ�����Ū���Ҳ�Ūư����ܤߤ뤳�Ȥ�ή��Ȥ��������������ͤФʤ�ʤ�������ϸ��ߤ���̤��������ӥ����Ȥ��������������Ȥ������ϡ����¤�¸�ߤ�����������ˤ�äơ����νŤͤˤ�äƻ볦��������Ȥ����褦�˽и������Τ����ͤ������ˤ���ǽ���Ȥ������Ǥ������������ܶ�Ǥ��ʤ��ΤǤ��뤬���β����ĩ��Ǥߤ롣��2012/09/30�� ��� ��ʿ�İ��ԻҤ��ܡۥ��Υ������֡��ॹ��ࡡ���ʤ�Ǥ⤫��Ǥ⥢�륫������  ��2012ǯ9��2�����������Ҥ������֥��å��顼�ࡦ���饤����ʤ��ʤ�����ʿ�¤�ˡפȽ������Ҥ��塢�����Υ�����ඵ�̤����ĥǥ�깭������������˥����䥨���ץȤ϶��˥ǥ��ػߤ��������ޥ졼�����ʤɤΥ��������Ϥǥǥ���ȼ������⤬���ͤ����ѥ�������Ǥϥ������14�͡��ڥ������5�ͤλ�Ԥ�Ф��Ƥ��ޤä��������Ĥ��оݤϡ�������ඵ�ζ��ĥ�ϥ�ޥɤ�������Dz�㥤�Υ������֡��ॹ����ˡ����ĥ�ϥ�ޥɤΥ̡���̡���ܤ����ե�����ɽ�����ʹ�㥷�㡼������֥ɡ䤬�ä�ä�����9��21������22���ˤ����ơ��٥��η�������ӥ���������������ȿ�����11�ͤλ�Ԥ�Ф�������9��22�����ѥ�������Υӥ�����Ŵƻ��ϡֱDz�����Ի�����10����η������פȡ�ȯɽ�����������ĥǥ�ϻפ��Ÿ���ˤʤäƤ�����������ꥫ�ϡ���ݼҲ�ϡ��ɤ������Ĥ���Τ�����������2012/09/25��
��2012ǯ9��2�����������Ҥ������֥��å��顼�ࡦ���饤����ʤ��ʤ�����ʿ�¤�ˡפȽ������Ҥ��塢�����Υ�����ඵ�̤����ĥǥ�깭������������˥����䥨���ץȤ϶��˥ǥ��ػߤ��������ޥ졼�����ʤɤΥ��������Ϥǥǥ���ȼ������⤬���ͤ����ѥ�������Ǥϥ������14�͡��ڥ������5�ͤλ�Ԥ�Ф��Ƥ��ޤä��������Ĥ��оݤϡ�������ඵ�ζ��ĥ�ϥ�ޥɤ�������Dz�㥤�Υ������֡��ॹ����ˡ����ĥ�ϥ�ޥɤΥ̡���̡���ܤ����ե�����ɽ�����ʹ�㥷�㡼������֥ɡ䤬�ä�ä�����9��21������22���ˤ����ơ��٥��η�������ӥ���������������ȿ�����11�ͤλ�Ԥ�Ф�������9��22�����ѥ�������Υӥ�����Ŵƻ��ϡֱDz�����Ի�����10����η������פȡ�ȯɽ�����������ĥǥ�ϻפ��Ÿ���ˤʤäƤ�����������ꥫ�ϡ���ݼҲ�ϡ��ɤ������Ĥ���Τ�����������2012/09/25��
���� ���ս��������ɤ��ͤ��뤫�������塡�� ���ξ��֤Ϸ�ɤΤȤ����и�����Ϻ������Ū���š��ظ�Υ���ꥫ��ư����ޤ�ơˤ˾褻���ơ�����ê�夲���֤��������˿ʤळ�Ȥ�¥����Ƥ��ޤä��Ȥ������ȤǤ��롣���������ȿ�������Ͷȯ��������Ф������ܤǤ�ȿȯ�����߽Ф��Ƥ��롣��������㤷������ʹ�����뤬�������ɽ��Ū�ʰ��������˲�ʤ���ê�夲���֤��鳰���ĤؤȤ����Τ�ƻ�ڤǤ��ꤽ��ϤɤΤ褦�ʷаޤ�ФƤǤ��äƤ⤸�ޤ���������Ϥ���ʤ���Фʤ�ʤ���ê�夲���֤Ȥ���̷��β��ϡ����ڤε�°�����Ƥˤ��뤳�ȤǤϤʤ���ê�夲���֤��̼�η��֡��㤨�����ս���ζ�Ʊ��ȯ�ˤ˿ʤळ�ȤǤ��롣��ͭ�����ڤʤɤ�¸�ߤ��ʤ�������������Ū�ʤ�ΤǤ��뤷������̷���ȯ�����������Ū�ˤ�뤷���ʤ�����������ڤǤ��뤳�Ȥμ�ĥ����ˤεչԤǤ��롣����ʸ����ˡ�2012/09/23�� �ˡ������� ���ܡ��ظ�ȯ��������ɸ�γյķ�������ꡡ����æ��ȯ����ˡ�٤���Ω��ᤶ������������˧ɧ ��������դϡ�2030ǯ��˸�ȯ��Ư���Ȥ���褦����������������������פȤ�ʸ�����������ͥ륮�����Ķ���Ĥ��ޤȤ�ֳ�Ū���ͥ륮�����Ķ���ά�פγյķ�������ä���19���ˡ��¼�Ū�ˡָ�ȯ������ᤶ�������ˤ��������뤳�Ȥ���Ȥ����롣�⳦�����äƤζ��Ť�ȿ�ФȤ��ɤ�����ȯΩ�ϼ����Τ��ϰ���פθ��̤��¤����ȿȯ���ƹ�Ϥ�����Ū��ȿ���ʤɤ˲ä��ơ����ļ��꼫�ȤΡָ�ȯ��ɬ�ספ��ܲ�����ա�������Զ��²��ˤ���Τ���ʡ��ζ����Ϥɤ��عԤä��Τ�����2012/09/20�� ��� ��ͭ�ϡ����դ�ʧ��������ư���������ܥ�ǥ�����������ʾ�δ��� �����ս����ᤰ��������������˶������٤������Ƥ��뤬�����������ܥ�ǥ���������Ū�������Ƥ��롣���λ����Ϥ����餯�������������������¦�������ä�����������礹��ȡ���ǥ����������Ƥ���ʾ�˾����ϴ���Ū�Ǥ��ꡢ��������ط���ᤰ�����λ����ξ��ξ��̱��Ω������Ƥ���Ȥ⤤���롣���Ū��ͽ¬�κ���ϡ�����¦�Ȥ����������¦��ȿ���ǥ⡢������˽���������ξ������й�����ˤϡ�������ܡ����ͤο����Ϥ���ư������¦�ˤ�����Ƥ��롣��ͭ�ϤȤʤä����ս������ΩŪ�ʴĶ����Ρ�����ͧ�����Τʤɤ�ʧ����������뱿ư�Ϥɤ����������� ��2012/09/18�� ���� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۼ���������������ϡַ�ˡ�פȥ�ǥ����Ϥ������������٤����������¶� ���ޥ���ǥ�����ˤ��路�Ƥ��뼫̱�������������ͤθ��䤬�Ф���������٤äƤ��뤬�����������Ȥ�Ʊ���������ʹ9��7���渫�Ф����֥����ɤ֤궥������̱���������ס���ε����ǥʥ���ʥꥺ������ꡢ����Ū���Ҹ��ιԻȤȷ�ˡ9����������������ϩ�����礦��̱������������Ԥ�����������ΰ�ͤ����μ���ˤʤ롣���ܤϤ��������������Ԥ��ä�������������������ϣԣУ�,æ��ȯ�������ǤȤ����Ƥ��뤬�����������Ϸ�ˡ���Ȥ������Ȥ�ޥ���ǥ����ϤϤä����Ǥ��Ф��٤�����������2012/09/15�� ��� ��ʿ�İ��ԻҤ��ܡۥ����βоä����ï���������ܿͤϲ��⤷��ʤ��Τ餵��Ƥ��ʤ��Τ����Ȥ��ʤ�����  ���ꥢ�βо����ï����
��2012/09/08��
���ꥢ�βо����ï����
��2012/09/08��
���� ¦��˿�����ߤ�����ơ������塡�� ���Ȥ�����Τʤ�����פǤ��뤬��ʹ�����Ƥ���Τ��������ͤ�������ư�������Ǥ��롣�֥֥롼���������⤫�פȤ�������դǤϤʤ�����¦��˿�����ߤ��������֤����Ф��Ƥ��롣ë����̱�����ۤ�����̱�������ۤ���������������Ԥ��ˤʤäƤ��Ƥ���Τ�����2012/09/07�� ���� ���ܤεIJ���̱������̱�����������塡�� �����ܤΥ�ǥ����ʤ�Ƥ���ʤ�ΤʤΤ��������ؽ���ʸ�ա٤κ������9��6����ˤ��轵�������μ��괱š����ư���Ť��Ƥ�����Է�ȿ��ȯϢ��Υ��С������ļ���Ȥβ��̤���夲�Ƥ���Τ��ɤ�Ǥߤ����ۤǤ��롣�꤬�֡�ȿ��ȯ�ǥ�����Ĵ�š�ˤΤꤳ���11�ͤ����Ρפȸ����Τ������ɤޤʤ��Ƥ�仡�Ǥ���ʸ����ͭ�ΰ��ϰ��ʤΤ�����Ū��ɾ�Ǥ��롣���θ��Ǥ��⸫���뤫����夲�Ƥߤ롣��̾�̤���̤˻��ä������С��������Ż������Ĥ餤�����ΤΤ���ʤ��̡��Ǥ��뤳�Ȥ������ä��Τ������Ȼפ������Υ��С�����ض��������Ҥ���ɽ�ʤ�¯�ˤ�����ͭ���Ԥ��ä����������ʤΤ������������Է�ȿ��Ϣ����ɽ���������������̡����ä����Ȥ�ɾ���Ǥ��ʤ����Ȥ�ʸ�դθ����θ³��ʤΤ��������𤱤ʤ��ä�����2012/09/04�� ���� �����Τ��餯���ܤ�����Ū�ջ֤������ư�ˡ������塡�� �����Ĥ�ʣ������Ȥ������դ�ȯ���Ƽ�Ǥ�������꤬������ʿ���ְ�Ϻ�Ǥ��롣���1939ǯ���ȥ��ԲĿ����������ˤ������Ƥ����ȯ�������������٤�Ф��δ֤����ļ�������շ�ĤǼ�̱�ޤμ�ä���ư�ʤɤϲİ�����Τ��ȸ����뤫�⤷��ʤ�����θ�������ư�ȸ����뤫���������Ǥ����֤Τ����ˤ�ʣ������Ȼפ���Ȥ��������롣����դǺ��夲���������Ǥ˹�դ�������Ԥ������ļ�������աԾ�������ˡ�Ƥ�ʤ���Ȥ���Ǥ���䤦�դˤ��ζ�Ʊ��ƼԤǤ��뼫̱�ޤ����������Τ�����Ǥ��롣��ʬ�˸����ä��äƤ���褦�ʤ�Τ���̷�����������ư�Ǥ��뤳�ȤϤ����ޤǤ�ʤ���������ά�Ȥ��äƤ⤢�ޤ�����ۤ�˵�ܤ���ϲİ����������Ǥ��롣��2012/09/02�� ���ȿ� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۥ����������������������¶�  ���ƹ���Ժ�ˤ�뿩���������¤Τ�ΤȤʤäơ��ȥ���������ΥХ���dz���ؤλ��Ѥ�����ȤʤäƤ��롣�������Ǥ�Ʊ�����꤬���롣�Х���dz���Ѥ˥���å��Ф�ѡ���䥷������������Υ��ࡣ����5ǯ����������¼�Ǥߤ��Τϡ��Ĥ�Ȫ���������٤��ʤ���ʪ��ž��������ʤ��ä�����2012/08/25��
���ƹ���Ժ�ˤ�뿩���������¤Τ�ΤȤʤäơ��ȥ���������ΥХ���dz���ؤλ��Ѥ�����ȤʤäƤ��롣�������Ǥ�Ʊ�����꤬���롣�Х���dz���Ѥ˥���å��Ф�ѡ���䥷������������Υ��ࡣ����5ǯ����������¼�Ǥߤ��Τϡ��Ĥ�Ȫ���������٤��ʤ���ʪ��ž��������ʤ��ä�����2012/08/25��
���� ȿ����������Ѥ��������Ȥ��ǥ����θ�ư�����դ����塡�� �����ﵭǰ���Ȥ����г�ν��������һ��Ҥ�ᤰ�äƴڹ�����Ȥδط�����Ω�ĤȤ����Τ�������ä�������ˤĤ��Ƥ����ܤ�������Ǥ�������ۣ��ˤ��Ƥ������Ȥ˼�Ȥ����װ�������Ȼפ��������ξ�Ǥ����ˤϤޤ����ʤ��ޤ��ߤ˻�äƤ����쥢������̱²���꤬������äƤ���Ȥ�ͤ��Ƥ��������Ū��ȿ��Ū��̱²������쥢�������������Ƥ����Τ����ܤζ�����쥢�����ϰ���Ф����б���¸�ߤ������Ȥϴְ㤤�ʤ����פ��������ڹ�Υʥ���ʥꥺ���̱²����դ����ܤ��������ۡ����Ū��ȡդ��Ф���ȿȯ�Ȥ��ƽФƤ������Ȥ����Ū�ʻ��¤Ǥ��롣���Τ��Ȥ�̱²����ˤĤ������ܤ����Ū��٤���äƤ��뤳�ȤǤ��뤬��������쥢������̱²����β��β�ǽŪ���פǤ��롣������٤�̱²����β��η����Ǥ��롣��������ǧ��������̱²�����Ȥ�Ǥ�ʤ��Ȥ����˻��äƤ������Ȥˤ�ʤ꤫�ͤʤ�����2012/08/22�� ���� ï�����ɤ줳�����̡����ݤ줹��ޤǤ��Ф褤�������塡�� �������ԥå���빽���⤷����������������ˤ���������Ϥ���ʾ�ˤ��⤷�������ֶ�פȤ������դβ��䤬�Ƥϥ�ǥ�����ޤ�Ƥˤ��魯�����������ͤ�����ɤȤ���̾��������Τ����¤��Ҹ��ȹԤ����ǤϤʤ��������������Ǥ����ϤȤ�����ν�ζ����岡���Ⱥ�������˾褻��ˡ�Ƥ�̱���ޤȼ�̱�ޤϱ�Τ褦�˽���������Ƥӹ������������������̱�ޤ��᤹��褦�˼����褯�ˤޤǤ��ɤ�Ĥ��뤫�����줾�����������������Ȥ�����̤˻�뤫��ï��ͽ¬�ϤǤ��ޤ������ܤδ�ν�����ϴ�ν��Ƴ������ž����Ǥ���̱���ޤؤ��������夬�Ԥ�줿�ִ֤��餢������ʤ��Ȥ��Ƥ����٤���Ϥ��ä�������ˤĤ��ƤϤ����Ǥ��餿��ƽҤ٤�ޤǤ�ʤ���������Ϻ��������̤��Ǹ�ζ��̤����äƤ��롣̱���ޤ�����Ȳ��Ρ���̱�ޤ�����Ū���������Υ��ʥꥪ�Ǥ��롣��������ˡ�ƤȤ������ڻ��ޤǤ��ä����ϥ��ϥ��ϤǤ���˰㤤�ʤ�����2012/08/11�� �Ҳ� ��лɤ��ػ���ȿ�̱�������������ܹ�ͺ ����������������ɻߤΤ��ᡢ��������С��ʴ�¡�ˤΰ���Ź�Ǥ����ػߤ��줿�������ȳ��ϡֹ����β������ǿ�ʸ�����ä���פ�ȿȯ����������ϫ�ʤϣ����ζػߤ��ᡢ�����ʰ�ȿ�ˤϣ�ǯ�ʲ���Ĩ���������߰ʲ���ȳ���ʤ�ȳ§������ߤ������������������͵��������лɤ��ϰ�ˡ����ͽ�ۤ��졢���ܻ��λҸ�ϫ��ϣ�������ε��Բǡ֥����å���Ű�줷�����פȽҤ٤����ޤ��������ˤĤ��Ƥ⡢��ϫ�ʤϺ��塢�����������Ƥ����Ȥ�������������롢����С���������ϤξƤ���Ź�ϡֿ���Ǽ��פεҤǤˤ���ä�����2012/08/04�� ���� ��ĥ�쥤�������ʰ�Ϻ�ˤä�2���ܤ��ʡ������塡�� �������ʤ��ƥ�Ӥ�Ĥ������ɤ����Ѥ�������������������Υ桼�˥ե�������Ƽ����ˤĤ��Ƥ��롣���Ф餯���Ƥ��Ƥⲿ���������狼��ʤ�������Ƭ���Ѥˤʤä��Τ��ȻפäƤ����Τ����ʤ����������������ʤˤʤä��饹����ɤǡ֤���ʤ饤�������פȤ��������뤬���ꡢ������ǥ��١�������äƥ��������ϰ��Ҥ����Τ��Ȥ����Τ��狼�ä�������������������ɤ˸����ä�˹�Ҥ��äƥ�����ɤΥե���˰�������Ѥˤϥۥ���Ȥ�������������夬�����Ȥ����櫓�ǤϤʤ������������Τ��Ȥϵ��ˤʤ����⤷�Ƥ�������2012/07/28�� ���� �������Ҳ��ư���Ȼظ����ʸޡˡ������塡�� ��������Ū��ž���������Ϥ����餳����˸����롣����������Ǵ������פ��ϼ������ư���⸲������������ݼ鲽����ȿư���ؤȤ���ư���ˤʤäƤ��Ƥ��ꡢ�������Ϥζ������Ȥ��Ƹ��ݲ�����褦�˻פ��롣̱���ޤμ�̱������̱�ޤΤ���ݼ鲽���ݤϤ�����Ƥ���Ȥ��������������2012/07/26�� ���� �������Ҳ��ư���Ȼظ����ʻ͡˴������פ����ۼԤȤʤä�̱���ޡ������塡�� �����Τ�̱�դ�������������������������ʤ��ä��Τ�������褢���Ȥ����֤�̱���ޤ��Ѽ����ƹԤä��Τ����Ȥ������䤬�ꤲ�������뤫�⤷��ʤ�������ϸ��ߤ����ܤ�������Ҳ��Ÿ˾�����ǽ��פʤ��ȤǤ��ꡢ����˵��Ť����ȤǤ��롣���ޤ������Ȥ����꤬��Ĥ��롣��̱�����뤤��̱�����������Ϥδط��δط��⤢�롣����ˤĤ��ƤϤ⤦����������ǿ���뤳�Ȥˤ��ơ����������������˸��ڤ��褦����2012/07/25�� �ˡ������� ���Խ�Ĺ�Ѹ���æ��ȯ��ư�ˤ�����ޤ줿���̡��ӳ�������쥤�����ࡡ���������¶� �����٤����ä����ꤷ�����ȤʤΤ��������ΤȤ����Ҳ�ư�ؤ��ӳ�������쥤������ο�Ʃ����Ω�ġ�������������椬�����ɤ졢���������ͤ�����Ƥ���������ФƤ������Ȥ��طʤˤ���Τ�������������ˤ��Ƥ⺤�ä����Ȥ��Ȼפ����ǽ�θ��ݤ�TPP(����ʿ�ηк�Ϣ�ȶ���)ȿ�б�ư�Ǥ��ä���TPP�ϡֹ�פ�ȿ���롢˴���ƻ�פȤ����ƤӤ����ǡ������οͤ������Ф��빶���³���Ƥ���ֺ����ø�������ʤ���̱�β�סʰʲ������ò�ˤ����δݤ�Ǥ��ƥǥ��Ϥ���ĤŤ���æ��ȯ��ư�����δݤ���Ω�Ĥ褦�ˤʤä������������Υ֥����Ǥϡָ�ȯ�Ȥϡ����ˡ��Է�ʵ��ѡءפǤ��ꡢ�֡��ָ�ȯ���Ѥʤ�ī���ͤˤ���Ƥ�졣�Ҥ줿���Ѥϡ��Ҥ줿̱²�ˤ�����������Τ�����פȡ����̤��ӳ�����ݽФ��μ�ĥ��Ʋ���ȷǺܤ��������ˤʤäƤ��롣����ǽ����̿�Τ���Ĥ��뤬���쥤������Ͽͤο�����ξΩ�ʤɤȤƤ�Ǥ��ʤ��Ϥ��ʤΤ�������2012/07/24�� ���� �������Ҳ��ư���Ȼظ����ʻ����ƹ���������������֤��ȴ�ν���ۡ������塡�� ��̱���ޤ������������Ѽ��ˤϥ���ꥫ��̱�����������Ѽ������뤳�ȤƤ����ʤ���Фʤ�ʤ������Х��������֥å��������������˲��Ƥ���Τ����ܤ�̱��������������������ϩ������äƤ���Τ�Ʊ���Ǥ��롣���뤤�Ϥ���ʾ��ȿưŪ�ʤȤ�������Ƨ������ĤĤ���Τ��������ظ�ˤ���Τϥ���ꥫ����������������������Ҳ����١ˤ��ݻ��Ǥ��롣�����ȷкѤˤ�������Ĺ�кѤν���塢���������Ʒ����кѤȶ�ͻ�кѤλ����Ϥ��ݻ����褦�Ȥ��Ƥ�����Τΰݻ��Ǥ��롣���̲ߥɥ�ϥ���ꥫ�������кѻ��ۤκ������������֤ϼ����ĤĤ���Τˡ����٤˸Ǽ�����̷��ξ�ħ�Ǥ⤢�롣��2012/07/24�� ���ݡ��� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۣף£ä�����ǣԣУС����������Ф졪 ������Σף£�������طʤˤ���Τϡ���Ĺ���쥢������ꥫ���λԾ�Ȥ��Ƽ����⤦�Ȥ����Τ�����ꥫ���ȳ�����ά��WBC�Ϥ��Υġ��롣�����������TPP����ǡ������ץ쥤��TPP�� �ƹ�����ʤ��������������٥ץ���������ϰΤ���ȿTPP̱����ư��TPP��ȿ�Ф���͡��α�ư�����ÿͤȤ����Ǹ�������ٻ����롣�������¶��ˡ�2012/07/23�� ���� �������Ҳ��ư���Ȼظ��������ˡ��������饪����ѥ��ء������塡�� ������ꥫ�������Τ˥��Хޤ��о줷�����Υ���å��ե졼���ϡ֥����פ��ä���������פ��Ф�������ʤ��Ȥ������դ��⤷��ʤ������ͤ�ϻ��˿����֤ä��������������������Ū�˸��ߤ�ư�����Ф���������Ҳ�����٤����졢�����ѳפ��᤹�����������ä��Ȥ������Ȥ����������Ϥ⤦���Хޤμ��դǤ�ȿ�Τˤ��줿��ΤǤ��졢������åѥ������ˤʤɤȤ���¸³���Ƥ���Τ�����2012/07/19�� ����� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۣ�������塢�塹�ڸ��ࡡ�뤵�����ʹ�������ա��������¶� ���������ͤ����ޤä���������Ρ֤���ʤ鸶ȯ����ס�������褦���塹�ڸ���θ�塢���ΰ����ʹ�������ƤӤ����ͤΰ�͡��繾��Ϻ�θ��դ����ˤ��߹��������2012/07/17�� ���� ����椯�������Ҳ����٤���ǡ��������Ҳ��ư���Ȼؼ�������ʰ��ˡ������塡�� ���������������鸫���̱������������������Ƥ���������Ϻ��˿�������ɾ����Τ������Ǥ��롣�����פäƴְ㤤�Ϥʤ���̱���������˴��Ԥȶ��˴�������ä��ͤ�¿���ä��Τ������������δ����Ȥ���餬̱�դ�ɤΤ褦�����Ƥ��뤫�Ǥ��ä������δ�����Ū�椷���ΤǤ��뤬�������Ȥ���̱�դ�¸³���Ƥ���ΤǤ���С������Ϥä��ꤵ���ʤ���Фʤ�ʤ�����������η������ϡդˤʤä�̱�դϸ��ߤ�¸³���Ƥ��롣������ͤδ���Ūǧ���Ǥ��롣����Į��⤬�ؤν��ͤ����Ϥ��λ����ߴ��ʤΤ��⤷��ʤ�������ʸ����ˡ�2012/07/12�� �����к� �ֶ�ͻ������椬�߾����ס��������˭ ���ֶ�ͻ������椬�߾����ס�����ϡ�7��5���դ������п�ʹ�ι���̤��礭���٤äƤ��븫�Ф��Ǥ����ȡ��ӥ��Ǥ��ͻ����Ǥ�����ͻ�Ծ�Τ椬�ߤ�ޤͤ�����Ȥ�����ͳ��ȿ�Фˤ��äƤ��뤳�ȤϤ褯ʹ���ޤ����Ȥ�櫓�ᥬ�Хʤɤε����ͻ���ؤ����Τ褦�˼�ĥ�����ȡ��ӥ��Ǥ��ͻ����Ǥ�Ƴ����ȿ�Ф�³���Ƥ��ޤ���������ͻ�������Ƚ�ʤΤ��ʡ��Ȥ���ä��餵�ˤ��餺�������¾�Ǥ�ʤ�����ͻ����Ǥ�ȡ��ӥ��Ǥ�ȿ�Ф�³���Ƥ����ѹ�����̤ζ�ԡ��С����쥤���ˤ����������Ф����ΤǤ�������ATTAC��ML����ˡ�2012/07/06�� ���� ��������ν����ȻϤ�ʤ���Фʤ�̤��ȡ������塡�� �������Ȼ����˿�ʪ�Ϥ���̡����������뤬����Ф���������������Ȥ����Х��ͤȽ����ˡդǤ��롣�������Ȥ�Ũ���פ��ȤǤ��롢�ȤϤ��ޤ�ˤ�ͭ̾�ʾ�ëͺ��θ��դǤ��롣�������Ȥ�������̿��å�����ȤǤ��ꡢľ�ܤ˻����ʤ��Ƥ�褤���������Ϥ��ޤ��ޤǤ��뤷�����μ��ʤ���ˡ�ϸ��ߤǤϹ�̯�ˤʤäƤ��롣����⤷�ʤ�������Ω�Ƥƺ�Ƚ�˻�����������Ū�˴ƶؤ��Ƥ��ޤ����Ȥ⤽��ƻ�Ǥ��롣��²�ط����˽��ط���˽���Ƿ��Ϳ���뤳�Ȥ⤽����ˡ�Ǥ��롣���Ϥ�����Ū��ȤϤߤ�������������ˤ�뤳�ȤϹ�̯�ˤʤäƤ��Ƥ⡢����Ũ���Ȥ����ܼ����Ѥ��ʤ��Τ����������⥢��ꥫ��̵�ͤ���Ʈ�����ͤ��Ȥ���������ܼ����Ѥ��ʤ��ä��褦�ˡ��ͤ�Ϥ��������������Τ�Τ��Ѥ��뤿��ˤ���������ָ����Ƥ���Ȥ��������뤬�������λ��뤿�븽�������ˤ��Ƥ�����Ѥ��뤳�ȤϤ������뤫���ȼ��䤹�롣��������������ӥ����Ȥ����Ȥ�����Ω������ʳ��ˤʤ��Ȥ������Ȥ�����2012/06/30�� ���� ¤ȿ�������ꡢŷ�����Ϥ䤬�ƻѤ��������塡�� �����Ϥ�¦�Τ����Ϥ��Ĥ�Ʊ����������ˤ��Ƥ���Ȼפ����������Ǥ丶ȯ�Ʋ�Ư�ʤɤ˰۵Ŀ���Ω�Ƥ�̱���ޤξ�����Ϻ�����ƱĴ�����̡��ؤι�������ޤ�����������ħ����ΤϾ�����Ϻ���Ф����ǥ�����ޤ����Ǥ��롣������Ϻ����������ˡ�פ��Ƶ��ʤɤ�����Ū�ƶؤƤ������ȤϤ��κ�Ƚ��̵��Ƚ�褬�Ǥ뤳�Ȥ����Ƥˤʤä��������丢��¦�Ϥ���Ǥ�ʤȤ������Ǥ�����³���Ƥ�������Ǥʤ��������β�²���������Ф�������̿�������˾��Ф��Ƥ���Τ�����²����Ͼ�����Ϻ�����������Ū�������⤷��ʤ��������ʤ��Ȥ������Ȥϴط����ʤ�������������Ū��ǰ����ǰ������˲�²�����������Ф����Ȥϲ�²��Ҷ���ͼ��ˤ��ƶ�������Τ�Ʊ���Ǥ��ꡢ���δ֤Υ�ǥ�����ư������������ƤΤ��ȤǤ��롣����Ū��Ƚ������Ū��������ƻ����̾��Ǥ��Ƥζ������٤ƤϤĤʤ��ä���ư�Ǥ��롣��2012/06/26�� ���� ������Ϻ������Ū�ƶؤϲ����̣���Ƥ��뤫 �� ���塡�� ���۸������ȸ�������ˤʤäƤ��Ƥ��뤬���ɤ���⤦��Ĥ����ɤ�����ޤĤ�������¿�����롣�ͤ����δ��ۤʤΤ�������������Ϥɤ���ŷ�������Τ��ȤǤϤʤ������ܤμҲ��������ޤ������ʤΤǤ��롣���ξ�ħŪ�ʤ��Ȥΰ�Ĥ��ʤ�³�����뾮����Ϻ������Ū�ƶؤǤ��롣��������ˡ��ȿ��ᤰ���Ƚ�ϰ쿳��̵��ˤʤä�����Ȥ�ȡ���Ƚ���³���뤳�Ȼ��֤�̵�Ťʤ��ȤʤΤˡ�����¦�����ʤ����Τϲ����̣����Τ�������Ϸ�ɤΤȤ��� ��2012/06/09�� ���ڡ���ǥ��� �����ϥ�α���������RASD-TV�����ƥ�Ӥ����ϴ��������ˤ��������¼������  ������ǯ���Σ��������å��ˤ�������ϥ�����������Ĺǯ�ɵڤ��Ƥ��른�㡼�ʥꥹ�ȡ�ʿ�İ��Իһ��Ʊ�Ԥ��������ϥ����̱�����פ����ä����ͤ����ϣ�ǯ�˰��ٳ��Ť�������������İ�����Υӥǥ����ƤǤ��롣ʿ�Ļ�ˤ��С���������ϥ��른���ꥢ������֤��줿�����ϥ����̱�����פǹԤ���Τ��̾�ʤΤ�������ǯ���ξ��ϰ�äƤ��������른���ꥢ���饵�ϥ麽������ɥ��롼����ɴ��ʾ��Ϣ�ͤ�����ܥ��ǽ��Ǥ������Υۡ��॰�饦��ɡ������ϥ���������ϡˤǹԤä��Τ��ä������λ���Ʊ�ȼԤȤ�����������ϥ�α���������RASD-TV���ä˶�̣�����ä�����2012/06/03��
������ǯ���Σ��������å��ˤ�������ϥ�����������Ĺǯ�ɵڤ��Ƥ��른�㡼�ʥꥹ�ȡ�ʿ�İ��Իһ��Ʊ�Ԥ��������ϥ����̱�����פ����ä����ͤ����ϣ�ǯ�˰��ٳ��Ť�������������İ�����Υӥǥ����ƤǤ��롣ʿ�Ļ�ˤ��С���������ϥ��른���ꥢ������֤��줿�����ϥ����̱�����פǹԤ���Τ��̾�ʤΤ�������ǯ���ξ��ϰ�äƤ��������른���ꥢ���饵�ϥ麽������ɥ��롼����ɴ��ʾ��Ϣ�ͤ�����ܥ��ǽ��Ǥ������Υۡ��॰�饦��ɡ������ϥ���������ϡˤǹԤä��Τ��ä������λ���Ʊ�ȼԤȤ�����������ϥ�α���������RASD-TV���ä˶�̣�����ä�����2012/06/03��
���� ���ܷкѤϥ��ͤ��ʤ��ΤǤϤʤ������λȤ���������Ƥ���Τ��������塡�� ����ϻ��β֤Τ������ξ�ס�����ζ���ˡ���Ϥꡢϻ��Ϥ�������Ǥ��뤳�ȤϳΤ������߱��ι��������⤢�������������̤ˤϤ����ʤ��Τ����Τ�ʤ������ͤˤϤ����Ǥ��롣������������Ū�ˤϤ����ȤϤ����ʤ���ϻ��ܤι�Ŵ��֤�ᤰ�ä����ɡ����ֹ���ˤϷ㲽�������ޤ������Ȥ��¤�Ǥ���Ѥ��ݱ��ʤ��˸�������פ���롣��ǯ����ǯ���Ѥ�餺������Ū�����Ĥ���줽���Ǥ��뤬�����Ԥ���äƤ��Ƥ�������ʤ�����ȯ�Ʋ�Ư�����Ȥ������֤�ͤ����뤫�������2012/06/03�� ʸ�� ��Τη��ȱơ�����¼������  ���������ѥ�Υ��������ȡ������٥르��(Vincent Vergone)��ηݤ˸��ȱƤ�Ȥä�����ʪ�����롣�ץ饭���Υ������פȸƤФ�����֤�Ȥ���Τ��������ܤǤϸ������ȸƤФ�Ƥ������ŰǤ���ǥ�Τ˸�����ͤ������αƤ�ʪ�����ΤǤ��롣��2012/06/02��
���������ѥ�Υ��������ȡ������٥르��(Vincent Vergone)��ηݤ˸��ȱƤ�Ȥä�����ʪ�����롣�ץ饭���Υ������פȸƤФ�����֤�Ȥ���Τ��������ܤǤϸ������ȸƤФ�Ƥ������ŰǤ���ǥ�Τ˸�����ͤ������αƤ�ʪ�����ΤǤ��롣��2012/06/02��
���� �Ҥ���Ͼä��Ƥ��ޤä��Τ��ʡ��ˡ������塡�� ���Ҥ���ʤ���ˤϤĤ餤��٤���������Ƥ���衣��������ޤǽгݤ��Ƥ����в��ȸ����뤫���Τ�ʤ����Τ��ˡ��ͤβȤˤⲿ�ܤ��Υӥǥ���ģ֣Ĥ⤢�ꡢ�Ҥ���뤳�ȤϽ���롣�������ޤˡ��ˤϤĤ餤��٤뤳�Ȥ⤢�롣��äѤꡢ�Ĥ��Ĥ��������ޤ�ƺǸ�ˤϿ����ޤ��ΤȰ������Ĥ롣�Ф��٤˲�²�Ǥ褯���˹Ԥä����Ȥ�פ��Ф��⤹�롣�ͤ����äƤ���ΤϤ����Ҥ���Τ��ȤǤϤʤ����Ҥ���ξ���ϥƥ��䡢����ʤ�Ϫŷ���Ȥ����Ȥ��������������줬���ޤ긫�����ʤ��ʤä��Ȥ������ȤǤ��롣��2012/05/31�� ���� ��Ĥ�40��ǯ���顡Ϣ���ַ��Ȳ��������������塡�� ��1972ǯ�Ȥ���ǯ�Ϥ����̣�Ǿ�ħŪ��ǯ���ä������θ���礭�ʱƶ���Ϳ�������郎�����ä��ΤǤ��롣����ꥫ�Υ˥����������Τ�ˬ����ƥ��²Ϥ��ޤä��Τ⤳��ǯ���ä���9��ˤ�����ѱɤ�ˬ�椷��������Ȳ��̤�����ꥫ������������²�����Ū�˿ʤ������ǯ�ν��ˤ�Ϣ���ַ��Τ�������ǤνƷ��郎���ꡢ��˽��������ȯ�Ф⤢�ä����ޤ���5��ˤϲ���������ִԡ����������ˤ����ä��������ơ�40��ǯ��ǰ�Ȥ������Ȥ�Ϣ���ַ������ͤ�����˽Ф�������ε�ǰ��ŵ�ˤ����ܤ�����2012/05/20�� ���� ���ļ���ϥ���ꥫ�˲��˹Ԥä��Τ��ʡ��ˡʤ��Σ��ˡ������塡�� �����ļ���ϥ���ꥫ���ͳ���Ƽ�̱�ޤ�����ޤζ��Ϥ���빩��˹Ԥä�������Ͼ�����Ϻ��Ƚ�������ܤ�������ư���ȤĤʤ��äƤ���Ȥ�����롣����������ϩ���ˤ�ä��ߤ��줿�֥å���������������Ʊ������ϩ�������Ĥϼ����Ѥ��Ǥ��뤳�Ȥ�ɽ�����˹Ԥä��Τ����顣�֥å�������������Ѥ��Ĥ��ĤĤ⥪�ХޤϤ�������Ϥ��Ƥ��롣�������Ƴ���Ǥ��롣���Υ��Хޤ� ��2012/05/08�� ���� ���ļ���ϥ���ꥫ�˲��˹Ԥä��Τ��ʡ��ˡ����Σ��������塡�� ����̱���������ǽ��Ƹ���ˬ�Ƥ������IJ�ɧ����ϥ��Х������Τ��Ф������Ƕ�Ĵ�������Ω�������ס�5��2���դ���ī����ʹ�ε����Ǥ��롣��Ĵ�������Ω����������Τϸ����褦�Ǥ���ȸ�������ï�������Ȥ����ǥ���ꥫ�콾���Ω�������Ȥ��������ǤϤʤ��Τ������Ĥ�̱��������������������ˤ����ȸ��������ƴط��θ�ľ����ľ����°��Ƴ�ǧ���˹Ԥä������ǤϤʤ��Τ�������Ū�˸�Ω������������������ꥫ�Τ����դ������ƹ��������κ��Ԥ뤳�Ȥθ岡������ߤ˹Ԥä������ǤϤʤ��Τ�����ä�����Ǹ����м�̱�ޤ�����ޤζ��ϡ�ϢΩ��ޤ�դκ����ä����ظ�ˤϾ������ǤǤϤ���ʤ�ȹԤ��ʤ�̱���ޤȼ�̱�ޡʸ�����ޤ�ˤζ�Ĵ���������Ⱥ�꤬����ΤǤϤʤ����������ä��������Ȥ��������ȤˤϤʤ�ޤ�����2012/05/04�� ���� ������Ƚ�����������η�̤Ǥ��뤬����줿��Τ��礭����פ��ȡġ������塡�� ���ǿ�Ƚ�Ǥȸ����褦����ͭ��Ϥ������ʤ��ȻפäƤ��������⤽�⤳�κ�Ƚ�ϴ���Ǥ��ä������ɤ����Ƥ������Ȥ����������Ϥ�����������ʤ��ä�����Ƚ�Τ������Ĥ䤳�λ���νи�������ˤĤ��ƤϤ���ޤǤ����餳����Ǹ�äƤ������餢�餿��ƽҤ٤�ɬ�פϤʤ���������̱������������Ť�������������������ϫ�ʤ�¼�ڻ���ʤɤ��о줷���������夬�¸������ȷ�����������������ˡ���Ǥ��ФƤ�������2012/04/27�� ʸ�� ��������λ��۲ȡɵ���δ���λࡡ�������Ȥ��Ƥοʹ֤�õ���������塡�� ������16����˴���ʤä�����δ����������Ƽ�ε����˶��̤���Τϡ�������λ��۲ȡɤ�ɾ���������ä�������Ū��ƤΤ褦�˷ɤ��ͤ�¿��Ⱦ�̡�Ũ�դ���Ŀͤ⾯�ʤ��餺���������������ब����Ū�ʵ�ͤǤ��ꡢ������λ��۲ȤǤ��ä����Ȥ�ï�⤬ǧ��Ƥ������ȤǤ���褦�˻פ������ܤ���˽��Ʋ�ä��Τ�19�Фκ��Ǥ��ꡢ������衢������Ϥꤪ�դ��礤�����Ƥ��������������β��ä�ɤΤ褦�˹ͤ��Ƥ����Τ���̤��¬�꤫�ͤƤ��롣����ۤ��礭�ʤ�Τ��ä�������ʬ���Ȥ���ǤϺǸ�ޤ�ʬ����ʤ��Τ����Τ�ʤ������Ϥ���Ǥ⤤���Τ��ȻפäƤ��롣��2012/04/24�� ���� ���Ρ����ܤ�����������פʤ������ˤ��뤫 ���塡�� ��Ÿ˾��ʤ�����������������������¤�³�������ܤ����������٤Τ��Ȥʤ��顢����ʸ��դ��Ϣ�ͤ�Τ⤤�������Ѥ�������������Ȥơ�����ʳ��θ��դ��⤫��Ǥ��ʤ��Τ�Τ��Ǥ��롣̱�����������Ȥ����������������Ȥ����٤��Ǥ��뤬���ҤȤĤޤ��ʤ��Ȥ�Ǥ��������������Ⱦü�ʤޤ��Ѥ߾夲�ƹԤ������Ǥ��롣������ϰ������ꡢ�ԣ�P���ø�����ꡢ��ȯ�Ʋ�Ư���ꡢ������������ʤɤǤ��롣�������������Ϥ�����ɡ��𤬿Ԥ����Ȥ������Ȥʤ����꤬�Ĥä����Ȥ��۲�ˤ⼪�����롣�ɤ��⤽������ΤȤ����˻��֤��ܼ��Ϥ���ΤǤϤʤ��Τ�����2012/04/23�� ���� ������Ƚ�����β������첿�����餫�ˤʤä��Τ��������塡�� ����Φ�������פȤ����뾮����Ϻ��Ƚ�Ϥ��褤�裴�������Ƚ���ޤ��롣����¦�Ͼڵ�Ȥ�����Ф���Ĵ��κ��Ѥ��ऱ��줿�����Ǥʤ���������Ĵ��Τͤ�¤�����餫�ˤʤä������̤���ʤ鹵�ʴ��Ѥˤʤ���֤Ǥ��롣�����Ǥʤ��Ƥ�̵�ͽ�ۤ����Ȥ�����������Ǥ⸡����λ����۸�Τ϶ظǣ�ǯ�ε᷺����Ƚ��̤�ͽ�Ǥ�����ʤ��������������Ȥä�������Ϻ�ε��ʤ����ͤ����ͤȤ��ƹ�«���뤳�Ȥ���Ū�Ǥ��ä��褦�ˡ����ͭ��Ƚ������Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ���Ȥ������ǤϾä��ʤ��������������Ū���礭���������Ϥ��ط����Ƥ����ˡ��(��Ƚ��)�⤽����̤��Ƥ���Ȼפ��뤫�������2012/03/25�� ���� ž���������ܡʤ��ν�Ȭ�ˡָ��ߤ�Ķ�ۡפȤ������ȤˤĤ��ơ������塡�� ���ޤ������Τ����ֶ����Ķ��פȤ������դ�̥���줿���ֲ桹�ϲ���عԤ��Τ��פȤ������٤Ȥ����ռ�����ǹͤ���ü���Ϳ������褦�˻פ��������Ǥϡָ��ߤ�Ķ��פȤ������դ˸������������������Τ��⤷��ʤ��������λ���Ū���䤤�����ϼ��ʤ����¸³���Ƥ����2012/01/11�� ���� ž���������ܡʤ��ν����˿ʹ֤ȼ����δط���ͤ��롡�����塡�� ���ʹ֤ϼ����ΰ����Ǥ���ʤ��顢�����Ȥ����äδط�����ġ��������³������ʹ�Ū��������������������ߤ������ط�����ĤΤǤ��롣�ʹ֤ϼ����ΰ����Ǥ���ȸ��äƤ⤽���ưʪ��Ʊ���ǤϤʤ����ʹ�Ū�����Ȥ����������줿��Τ��𤵤�뤫��������οʹ�Ū�����Ȥ�����Ū��ˤ�ʪ���ˤ����롣��2012/01/08�� ���� ž���������ܡʤ��ν�ϻ����Ĺ�������Ϥء������塡�� ���Ҷ������ˤϥ��륿ͷ�Ӥ���Τ������륿ͷ�ӤȤ����Ȥ⤦�����䤯���ݤ�������⤢�롣���Ĺ���Ρ��֤ȹ��Υ֥롼���٤��פ��⤫�֡����륿ͷ�ӤǤʤ������Ĥ��Υ�����ɤ�ʤ������ʬ�Ϥ�ͷ�ӤǤ��ä����������Τ��Ȼפ�������ꥫΥ�졢���Ĥˤʤ뤳�Ȥ�顣���������եȤء��ճ��ʤȤ��������Ÿ���뤫�⡣����������������ʤ���Τͤ��꤫�ʡ�����ͷ�Ӥξ���ʬ�Ϥ������⤷��ʤ����顢����Ĺ�������ϤءפȤ������Ȥ�⤦�����ͤ��Ƥߤ�������2012/01/07�� ���� ž���������ܡʤ��ν��ޡˡ��к���Ĺ���ۤμ����������塡�� �����ܷкѤ������кѤδ����οʹԤ���ǣ�����������̺Ҥ��������������ܷкѤ�ͽ¬�����������б�����������꤬�ФƤ���Ȥ����Τ�ȿ�����ष���߹�������㤤�ˤ��ʤ��������Ϸ�ɤΤȤ������ܷкѤ�����ꥫ�кѤ�ţշкѤ��Ф�������Ū�ˤޤ��Ǥ���Ȥ����˲�ʤ������ܷкѤϥ���ꥫ�кѤ�ţշкѤ�Ʊ���褦�ʾ��֤�����Τ��ȼ���ƻ��Ÿ���Ǥ���Τ����Ȥ������̤ˤ��롣��2012/01/06�� ���� ž���������ܡʤ��ν���)���ǤǤϺ�����ĥ�ϻߤ���ʤ��������塡�� ��2008ǯ�Υ�ޥ���å��ˤ������Ū���Զ��ϥ���ꥫ�����ܤʤɤκ�����ư���ͻ������Ÿ���ʤɤˤ�ؤ�餺��ž�Ϥ��Ƥ��ʤ�������ꥫ�ζ�ͻ�굡��ü��ȯ������������Ū���֤˺�����ư���б���������Ⱥ����ϰ�������櫓�����ܺ�̳���Ĥ�ߡ����줬��Ĥδ����ˤʤäƤ��롣�ɥ��桼���β��Ͳ���ˤʤäƤ��롣��2012/01/05�� ���� ž���������ܡʤ��ν����˱ߤȿ�̱���η�ѡ������塡�� �����ļ����ˬ�椬���Ƥ������������λ���ȼ����ī���ؤ��б��Ĥ����Ȥ��뤬����������ΤʤȤ�����ʬ����ʤ�����������¾�ʤ������β��̤�������ܤ����Τ����ܤ����߽���������ι�Ĥ��㤦���˹�դ����Ȥ�����Ǥ��롣���ϴ������ܤι�Ĥι�����Ϥ���Ƥ��뤫�顢���߽�����ǥ���ꥫ��Ĥ��㤦�Ȥ������Ȥθ�ľ����ȯŸ������������Ƥ��롣���ζ�ͻ�̤Ǥζ��Ϥ�ʤᡢξ��֤��ǰפǤαߤȿ�̱���Ǥη�Ѥ���Ÿ���뤫���Τ�ʤ�������֤��ǰ�Ѥ��ƥɥ��𤷤Ƥ���Τ����顢�ܳʤ���бƶ����礭�ʤ�ΤȤʤ��ǽ�������롣��2012/01/03�� ���� ž���������ܡʤ��ν���˶�Ʊ���ۤȤ��ƤΥ���ꥫ�������塡�� ������ꥫ���椫�饦�����볹������������ޤ쥢��ꥫ�кѤ�Ҳ���ѳפα�ư���ФƤ������Ȥ϶�̣���������Х������Υ������������������Ǽºݤϥ֥å���������Ƨ�����ä����Ȥ�פ��������ȸ����롣����ꥫ������ʺ����ֻ����������ĺ�̳��Ǥ��롣����ꥫ�кѤ��Զ�æ�ФΤ���κ�����ư���ͻ���¤ϵ�ǽ����������Ū�ˤϿ��ή�����ɥ��Ҥ��ˤ������������ե졼�����������Ǥ�餸�������ʤΤǤ��롣����ꥫ�������кѤηʵ��۴Ĥ����Ƥ����Ϥ���Ȥ����Τϲ��θ��ۤǤ��롣����ꥫ�������θ�Ҵ��Ǥ���Ȥ����Τ�Ʊ���褦�ˡ�����ꥫ�Ϸ����Ϥ�Ʊ���褦�˥ɥ���̲ߤ˰�¸���뤬������ϥ���ꥫ���������Ǥ���Ȥ�����Ʊ���ۤˤ�äƤ��뤳�ȤǤ��롣�����Ƥ��ζ�Ʊ���ۤϥ���ꥫ�����ܤ����ܤ䴱ν�����������Ƥ�������ʤΤǤ��롣��2012/01/01�� ���� ž���������ܡʤ��ν���˴����ä��ɥ롡 ���塡�� ���ɥ�ο��ή���Ȥ����ɥ�����Ȥ��Ȥ������դ��ͤ�ϼ��˥������Ǥ���ۤ�ʹ���������뤤�ϥѥå�������ꥫ���ʤν�����Ǥ��롣�ɥ��������1960ǯ�夫�餢�ä��Ϥʤ������餫�줳��⤦50ǯ���ʹ������Ƥ������Ȥˤʤ롣�Ǥ⤳��ϥ������߾�ǯ���äǤϤʤ������¤˶�Ť��Ƥ��뤳�ȤǤ��롣�ɥ��˽��ȸ������դ�����������Ĥ�1�ɥ�360�ߤǤ��ä��Τ�77����Ǥ��븽�ߤ���ߤ�Хɥ�β����㲼�ϳμ¤˼¸����Ƥ������ȤȤ����롣����Ϥ䤬�Ƥ�50����˿�̤��ƹԤ���ͽ�ۤ���롣��2011/12/31�� ���� ž���������ܡʤ��ν��˴��̲ߤδ����ȱ߹� �������塡�� �����ﹽ¤���θ���ϰ�ʶ��λ����Фơ�9��11���������Ȥ���ȿ�ƥ����褬���ä���������������θ�Ҵ��ȾΤ��Ƥ�������ꥫ������Ū�ʷ���Ū�������Ѥ��ĤĤ��롣����ꥫ���ϡԻ����ϡդο���Ǥ��롣���Τ��ȤϺ��塢���ؤϤä��ꤷ�Ƥ������ȤǤ���Ȼפ��롣�����顢����ꥫ�����ܤ�����Ʊ���Ȥ���̾�η���Ū�������Ƥ���ΤǤ��뤬�����Ĥƾ��������ܤ���ä����ܤι����ά��̱���������Ǥ�Ƨ������褦�Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ�����ʤΤǤ��롣��ǰ��ۤ�ʤ����ܤι����ά�Ǥ��뤬�����ˤ��֤�в�ǽ����������Ϥ��Ǥ��롣�����������ܤ��ȼ�����ά���פळ�ȤǤ��ꡢ�����ϰ����Ȥ��Ʒ�ˡ9��˴�Ť������ά�Ǥ��롣���δ֤˳���ʸ��������1972ǯ������ι������ηаޤ�����ߤˤ���Ƥ����������Ǥ�̤��������Ƥ���Ȥ������ʬ������ѱɤ�������β��̡դ⤢�뤬����������뤳�Ȥ�¿���ΤǤϤʤ�������2011/12/30�� ���� ž���������ܡʤ���Ȭ�ˡ��������Ȥδط��Ͻ����ְ��������ľ�뤹�뤳�Ȥ���Ϥޤ롡�����塡�� ���ڹ��������ȴ����˽����ְ��ؤ�¸�ߤ��ħ���뾯����������Ω���졢�������ܤϤ���ű�����Ȥ�����ƻ�����롣�����˸�����Τ��������ܤν����ְ��ؤ�¸�ߤ����ܤऱ�褦�Ȥ���ѤǤ��롣���ڤμ�Ǿ���̤������������ΤϽ����ְ�������β����ᡢ���ΤޤޤǤϡ����ܤαʱ����ô�ˤʤ�פȽҤ٤�����ƻ����Ƥ��뤬�����������Ω��Ǥ��롣���ļ���Ϥ��餿�������ű�����Ȥ�����������Ѥξ��ɤ�Ǥ��롣�������ܤϤ�������˸����礤�պ������٤��Ǥ��롣��2011/12/25�� ���� ž���������ܡʤ��μ��ˡ���Ȱջ֤ȹ�̱�ΰջ֡������塡�� ������ꥫ�Ȥδط��θ�ľ���Τ���˷�ˡ9��β���ˤ����������Ĵ����Ϣ��Ϥ������¤ˤ��Ƥι���������ܳʲ������������Ǥ��롣�߿���η���ˤ��뱦����ݼ�ϥ���ꥫ�Ȥδط���ľ�����Ϥʤ����ʥ���ʥꥹ�Ȥϲ��̤Ǥ��롣���ܤ��ɤΤ褦��̾�ܤˤ��跳����Ƥ⤽������Ǥϥ���ꥫ�ط��θ�ľ���ˤϤʤ�ʤ��ΤǤ��롣���Ʊ��㡢���뤤���ݼ���Ф���ȿ�Ʊ��㡢���뤤���ݼ��¸�ߤ��롣��2011/12/23�� ���� ž���������ܡʣ��˲���Ʒ�ˡ����ͤ��롡�����塡�� ����̺Ҥ丶ȯ�̺Ҥ�����������ⲿ��ޤǿ�Ÿ���Ƥ���Τ�ۣ��ʤޤ� ��ǯ�ۤ��ˤʤꤽ���Ǥ��롣�����˽����Ϥ����ɱҶ�Ĺ�ι�ų��Ϣ���� ���ɱ���äμ�Ǥ���꤬��褷�ʤ��ޤ����ܤϥ�������ɾ�������Ф��� �϶��Ԥ���ʢ�Τ褦������������ϸ��ɱ���äˤ�餻�褦�Ȥ���Τ� �ʡ��˥���ꥫ�IJ�ϳ�ʼ��Υ������žͽ������뤷��������︺�˿� �ޤ�������ʤ������ˤʤäƤ��롣�������ܤϥ���ꥫ�����ط������ ����ι��ۤ�����ʤ������ϩ�����äƤ�����������ʤ������ξ��� ����Ȱ����ݾ�ˤĤ��Ƥδ���Ū����ǰ���ɤ����Ƥ�ɬ�פǤ��롣���ΰ� ̣�ǤϷ�ˡ9��Τ��Ȥ餿��ƹͤ�����ʤ����������ϰ�ΰ��� �ݾ�ȷ�ˡ9��Ǥ⤤���ΤǤ��뤬���Τ��Ȥ�ǰƬ�ˤ����Ƹ��ʤ���Ф� ��ʤ������ƴط��θ�ľ���ȥ������ط��ο�Ÿ�ˤϤ��Τ��Ȥ��ʤ���Ф� ��ʤ�����2011/12/21�� ���Խ�Ĺ�Ѹ���ȿTPP�ǹ�ȼ���θ�ȯ����ɤ⤤���æ��ȯ���ӳ�����Ԥ⤤�롡���Ȥ�ͤ��줿���ι����Ĵ���������¶� �����ޤ��ι���̱���ͤ������äƤ������Ū������ǡ���Ĵ�˴�̯�ʤͤ��줬���ΤȤ�����Ω�ġ�������ռ�����褦�ˤʤä��Τϡ�3��11������������̺Ҥ���Ǥ��롣��2011/12/15�� ���� ž���������ܡʤ��λ͡ˡ�����������ϩ�������桽����ϩ���������塡�� �����Ƥγ��狼�麣����70��ǯ�ˤʤ롣��ǥ����ʤɤdz�����θ�ľ������ƻ�䵭���⤢��餷�������ͤˤϤ��ۤɤζ�̣�Ϥʤ����������ƴط��˴��������椷�Ƥ��뤫�����9��11�θ�˥���ꥫ��������ά�Ȥδط������ܤ����������줿���������ξ�������Ͻ�����⥢��ꥫ����ά��ƱĴ�������֥å���ϩ����ƱĴ����������γ�����ʼ�ޤǤ�ä��ΤǤ��롣��2011/12/15�� ���� ž���������ܡʤ��λ��ˡ����ƴط��ȥ������ط��������塡�� ����̺Ҥ丶ȯ�̺Ҥǿ͡��δؿ������줵�줿���Τ��벭��δ��ϰ������������������Ƨ�߹��ߤǺƤӶ����٤������Ƥ��Ƥ��롣�ɱҾʶ�Ĺ���ܲ��ȤǤ⤤���٤�ȯ���Ǻ��𤷤Ƥ��뤬�����ܤ�����������Ťο����Ϸ��ߤ���ǽ�ȸ��ƥ�������ɾ�������Ф��褦�Ȥ��Ƥ���Τ�������Ȥ⥢��ꥫ�ι��������˱����뤿��Υ����������ʡ��ˤǤ���Τ��������֤ˤ��뤫�Τ褦�˸�������ϰ���������ɱҾʤ��濴�Ȥ��봱ν���ϸ��ι����ʤ�Ƥ���Ȥ��������롣��2011/12/14�� ���� ž���������ܡʤ�����ˡ�������ƴط�����Ȥ��ꡡ���塡�� ����̺Ҥȸ�ȯ�̺Ҥ�ľ�̤��ƿ���դϤ���ˤ����������Ǥ���Ѥ���������褺��������դ˼�ä��ؤ�ä���������դϡز��������������Ϥ���٤ȽҤ٤��������Τ���Τ��������Ÿ�Ϥߤ��ʤ������������٤�Ƥ���٤Ȥ������֤�³���Ƥ��뤷����ȯ����ǤϿ���ɤδ����֤������˸��ब³���Ƥ��롣�����ơ�������դ���ʤ����ΤϣԣУл��ø�ĤǤ��ꡢ����δ��ϰ�������ؤ�Ƨ�߹��ߤǤ��롣����ˤϾ����Ǥ�ޤ�����Ǥν����Ǥ��롣��2011/12/13�� ���� ž���������ܡʤ��ΰ�ˡ����ή���Ĥ���١������塡�� ���ͤν���ζ��ǯ���ˤʤ�ȡ�����ë�ܥ��ԡפ����롣12��15����16������ǯ��1��15����16���˳�����롣400ǯ��Ķ����ˤ�����褦�������Ĥ�ܥ��Ԥ�����ǯ����´����Ƥ����ΤǤ��뤬����ǯ�⤽���Ǥ��롣�ƥ�ӤǤϤ⤦ǯ�����Ф�����̤������뤬�����ǤϹ���Ȥʤä����Τ����ν�μ�Ǥ�����������Ƥ��롣�����Ѥ��ʤ����Ȥ���˾��̯�ʰ¿����ʤ���ǯ���θ��ʤˤĤ���蘆��뤳�Ȥˤʤ�Τ�����������2011/12/12�� �ˡ������� �ڤ���ݤݼ�ȯ�ۺǰ��θ���͢�С���ȯ͢�Ф�ߤ�褦����پ��ʤǤ��뤳�Ȥ�Ϫ�褷����������ȯ�������ꡡ��δ�� �����ܤϸ��ߡ��٥ȥʥࡢ�����ڹ������ȸ����϶��϶�������Τ���ξ�ǧ�Ƥ����ı���̳�Ѱ���Dzķ褵�졢���ı��ܲ�Ĥ�����줿�����ΤޤޤǤϺ�ǯ��˽���ξ���Dzķ褵�졢��Ω���Ƥ��ޤ����ǰ��θ���͢�С����줬��ȯ͢�ФʤΤ�������̳�Ѱ���ˤ϶�������������̵���İ��������äƤ���Ȥ��������褦��̵�������ä������ʤ�������ï�Τ���˻Ż��Ƥ���Τ�����ȯ͢�Ф����פ�夲�������Τ���ˡ�����ʶ�������������ܤ��Ȥ����Τ������줬���Ǿ�ǧ�����Ȥ���ʤ�С��ǰ��������Ȥ�����ˤˤ���̾��Ĥ�����������2011/12/11�� �פ��֤�����ܤǵ��Ť������� ����ǯ�֤�����ܤؤΰ��������ơ��轵���ѹ�����ޤ����������ܤˤ��ơ����졩�Ȼפä����ȤϤ�����������ޤ��������֤�äȤ��������ۤ������ڤ����ʤ��ΤǤϤʤ����ס������ؤ��ʤ��פȻפä����Ȥ�빽����ޤ������ʥ���ɥ�ᾮ�Ӷ��ҡˡ�2011/12/09�� ���� ���ƴط������꤬�����Ȥ����濴�ˤ���Τ��������塡�� ��������ʪ�ΤϤ��ޤä��褦�����ļ����ȯ����ƥ�ӤǸ��Ƥ��ƴ�����ΤϤ��줬���ƴط����ħ���Ƥ���Ȥ������Ȥ����ԣУл��ø�Ĥ�ᤰ�����Ƥο����㤤��ɽ�̲����Ƥ��뤬�����켫�Ȥ����ƴط��路�Ƥ��롣�褯�Ⱝ���⥢��ꥫ���ܤ��Ǿ�ϥ���������ʿ���ϰ�ηк�����������������ޤ�ƻ��äƤ��롣��������Ū����ǰ��������롣������Ф������ļ�����������ܤμ�Ǿ��ۣ��ˤ������Ȥ�٤�ʤ������ΤʤΤ������Ĥ��ͤϤ���ʼ��伫�����֤�����̱��Ǿ�����Ϣ���̡������ǤϣԣУи�Ļ��ä�ȿ�ФǤϤʤ��Ȥ������������顢�������Ȥ����Ĥ֤䤭��Ǥ롣��2011/11/18�� ���� TPP���ø�Ĥ����ܤ������кѤκ���ʣ������ܤϥ������ϰ�ηк�Ϣ�Ȥ��ۤ��٤������塡�� ������ꥫ�Υ����Хꥼ�������ϻԾ������Ծ츶���˴�Ť���ΤǤ��ä��ˤ��Ƥ⤽�����ǰ�̤�Τ�ΤǤϤʤ�������ꥫ�ι�פ��ޤޤ줿��ΤǤ��ꡢ�ԣУФξ��ˤϥ���������Υ֥��å�������ά�κ����ˤ��롣���ܤϥ������ϰ�Ǥηк�ŪϢ�Ȥ��ۤ��٤��Ǥ��ꡢ�̲�����Ǥ���άŪ���ۤ��Ĥ٤��Ǥ��롣����ˤ�����Ʊ�����η���Ū������Ū¦�̤Τߤʤ餺�к�Ū¦�̤����٤��Ǥ��롣���θ�ľ���ȥ������ϰ�Ȥηк�ŪϢ�Ȥ�Ż뤷�����ۤ�ͤ���٤��Ǥ��롣��2011/11/17�� ���� TPP���ø�Ĥ����ܤ������кѤκ���ʣ���TPP�ϥɥ���̲������ݻ��Τ���Υ֥��å����������塡�� �����ļ���ϣԣУи�Ļ��ä���ͳ�Ȥ��ƥ���������ʿ���ϰ����Ĺ�Ϥ��ꤤ��ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ���������������Ū��롣���ˡּ���줿10ǯ��פ����ܷкѤ����ڤ�ߤäƤ����Τϥ������кѤ���Ĺ�Ǥ��롣�ä����䥤��ɡ��ڹ�ASEAN����ηк���Ĺ�Ǥ��롣�����Ƥ��ΣԣУи�Ĥˤϴڹ�������ɡ�����ɥͥ����䥿���Ȥ������ӣţ��Τ������ϻ��ä��ƤϤ��ʤ����������������Ĺ�Ϥ��������Ȥϥ������ϰ�ΰ����Υ֥��å�������٤��Ǥ��롣�ԣУФϥ���ꥫ�Υ������кѤ���Ĺ�Ϥμ����ߤǤ��ꡢ�֥��å����Ǥ��뤬�������ˤϥɥ���̲߰ݻ��Τ���ηкѷ��γ��ݤȤ�����ά�����롣��2011/11/16�� ���� TPP���ø�Ĥ����ܤ������кѤκ����1���ǰ�Ω�����θ��ۡ������塡�� ������ꥫ�Ǥϥ��Х������Τκ������꤬���פ�����Ū����Ȥʤ�ĤĤ��롣�֥����פȤ���ή�Ը�ޤ����߽Ф������Х������Τ������Ǥ��ä��������Ѥ�ä��Ȥ����Τ��������ʡ��ˤ��줬���餶��ɾ���Ǥ��롣Ʊ�����Ȥ������������������̱�������������ƤϤޤ롣���Τ��Ȥ餿��ƴ����������Τ��ԣУл��ø�Ĥ�ᤰ��ɥ��Х���Ǥ��롣���ļ�����Ω�������Ʊ�������ηк�Ÿ���Ȥ����٤���Τ����������Ҵ�Ū�ˤϥ��Хޤ������κ����˸������к���ά�����ܤ�̱���������䴱ν��ƱĴ�ԥѥե��ޥ�ޤ�ơդ����˲�ʤ���������դˤ⡢��ν�ˤ�ԣУл��äޤǤ��Ȥ�ʤ�����������Ū�ϤϤʤ��Ȼפ��������ȿ�Ф�ư���Ϻ���ͭ����Ư���Ȼפ���������Ū�����ϤȤ��Ƶ�ǽ�������������2011/11/15�� ���� �߹�����κ���Ū���ϲ����¸�ߤ���Τ��ʥˡˡ������塡�� ���ɥ�ȥ桼���Ȥ������̲ߤϷк�Ū���פ�ȿ�Ǥ������ꤵ��Ϫ�褷�Ƥ��롣����ϴ��̲ߤ����̲ߤΰ�̣���¼���̵���̲����ޤ��Ƥ���Τˡ����̲ߤǤ��뤳�Ȥ�ݻ�����ۤ��ʤ�̷��˸������������뤫���������̲ߤ���������蘆��Ƥ���ߤϤ���̷���߹�Ȥ������ǰ��������������Ƥ��롣���α߹�����ܷкѤ˼�äƥץ饹�̤ȥޥ��ʥ��̤����뤬���ɤ��餫�Ȥ����ȥޥ��ʥ���(͢���濴��Ȥ϶�����̤Ƕ춭�ˤʤ�ˤ���Ĵ����������������롣͢�м�Ƴ���Ȥ��椬��ηкѤ�٤��Ƥ���Ȥ������Ĥ˻����ͤ���������ޤ�Ƥ��뤫�������2011/11/09�� ���� �߹�����κ���Ū���ϲ����¸�ߤ���Τ��ʰ�ˡ����塡�� �������Ȥ��������кѤϥ�ޥ�å�����δ�����æ���ƤϤ��ʤ������������ӲФ�����ͻ���������ܤκ�̳������Ĥ���������ͻ���ؤδ����Ȥ��Ƥ��롣����ꥫ���ܤϥ�ޥ�å��˺ݤ������̤λ���Ƴ���ˤ�äƶ�ͻ���ؤ����Ȥ�ߺѤ����������Ω���ɤ����˥���ꥫ���ܤκ�̳�����Ȥʤä������ꥷ��ʤɤκ�̳������ü��ȯ����桼���δ��������Ū�ˤϺ���Ʊ���Ǥ��롣����ϥ������볹�����˽ФƤ����Ԥ����ι�ư�δ��פǤ⤢�롣��2011/11/08�� �ˡ������� �л������ƥ��¼���顡�����������塡�� �����ĤƤʤ�֤���Ф�����dz���夬����η��������襤�Ϥ��������襤�Ϻ�����פȤ���ͦ�ޤ����Τ�ʹ�����Ƥ������⤷��ʤ���������������ʸ��ʤϤʤ��ä����ָ�ȯ����ʤ�ʡ��ν������פηл������¤���ߤǤ��롣�����ˤ��ä��ΤϺ¤��������ӻ���Ԥ���Ҥ�Ȥ��ȷл��ʤ�Ϥ��Τ��ä��������ϡ��д���䤨�ʤ����䤫�ʤ�Τ��ä����¤���ߤκǽ��������ǥ���äƤ��������뤫�⤷��ʤ����������������ˤϽ���Υ�����Ȥϰ㤦�϶������ä���������Τ褦��������褷���л������Ǥ���������狼��ФƤ����϶��������ꡢ�͡��Τ������˶���������Χ�����ä�������ϣ������������Ρָ�ȯ����ʤ�����ν������פκ¤���ߤ˼����Ѥ���Ƥ��뤬���ޤ�������ˤޤ��줿��Ȥ��Ƥ䤬�ƤϿ�������ư�β�ˤ�ʤäƹԤ�����2011/11/03�� ���� ���������ȸ����С�������κ�Ƚ�⤽�����͡ʻ��ˡ������塡�� ������ľ���Ȥ������⤷�����ؼԤ���������Ρַ�ˡ���פϿ��ߤ⤢�ꡢ��ɴ�η�ˡ�����ɤ�ʤ餳����ɤ�ȿʤ����Τ�������ΰ��ȸ������Τˡ����ܤ��ޤ������Ȥ���ʤ���ˤ��٤Ȥ��Τ����롣����ˡֹ�̱�Τ����ˡ��������̱�����פȤ���褦��������Ǥ��뤬�����������ѱ��ʸ���ܤǤ⤢�롣Ω��δ������ѱɤ�����Ū���ξ�ħ�Ȥ��Ƥ������Ƥ���Τ��жˤˤ����Τ�����2011/10/20�� ���� ���������ȸ����С�������κ�Ƚ�⤽�����͡���ˡ������塡�� �����Ω��δ���ֽ�������פǾ�����Ϻ�ΰ�����Ƥ��롣�־�����Ϻ�衢�����Ϥ��Ǥ˽���äƤ���פȤ���ɽ���ʸ�ϤǾ�����Ϻ�κ�Ƚ��Ƚ��ȿ��Ƚ���Ƥ���ΤǤ��롣��ˤ�äƥ��ͤˤޤĤ�뤦�蘆�ä¤Τ褦�˻�Ω�Ƥơ���ɤΤȤ����⸢������Ƚ���֤��Ƥ��롣��Ω��δ�衢������ʸ�����ۤ������Ǥ˽���äƤ���פȤ����٤��Ǥ��롣��2011/10/19�� ���� ���������ȸ����С�������κ�Ƚ�⤽�����͡ʰ�ˡ������塡�� ��������ˤϰ�����ɤ����礦��ͥ�����롣�Ҷ��Τ����������ˤ�����ͥ���ФƤ�������餷���Ƥ��ޤ�ʤ��פä���Τ����ļˤβƤν��Dz�Ǥϥ������˸����äƥ䥸�����ӡ���ū���Ĥ餵�줿��������Ϻ�Ϥ��λդǤ�������ѱɤȤȤ������Ū��������Ǥդ����Ƥ�줿����ʤΤ�����������2011/10/10�� ���� �����ηк�Ū��������������δ������Ԥ��λ��ա����塡�� ������ꥫ�Ǥϥ������볹���Ф����Ԥ����ι�ư�����Ƥ˳��礷�Ƥ������꤬�������롣����ꥫ�кѤ�æ��ϩ�ʤ���ϩ���ɤ��ͤ���Ƥ��롣���κ��ܤˤ���Τ������ȷкѸ�ؤλ��ȷкѹ�¤��ž���μ��ԤǤ��ꡢ����ϸ��ߤ����ܷкѤ�Ǥ����Ǥ⤢�롣�����ȷкѸ�λ��ȷкѤ��ϽФ������кѡ��Ȥ�櫓����ϰ����ü�ϰ�դζ��̲���Ǥ��꤫�ĸ���Ū����Ǥ��롣����ꥫ��1960ǯ��Ⱦ���餳�β������äƤ������������ηкѲ��ȶ�ͻ�кѤ����粽��������³����Ƥ����������ظ�ˤ��ä��Τϥɥ�δ��̲ߤǤ��ä�������ꥫ�кѤϤ��μ���Ū�ϤäƤ���Τˡ������кѤ�������������蘆���̷�����ˤ��ä��Ȥ����롣�ɥ뤬���̲ߤȤ����Ϥ��ʤ��顢���̲ߤǤ���³���Ƥ���̷��Ϥ��ξ�ħ�Ȥ����롣�����ηкѲ��ȶ�ͻ�кѤϼ��ηкѤ�����Υ���ʤ������粽���Ƥ�����������Ϲ�Ȥκ��� ��2011/10/07�� ���� �����ηк�Ū��������������δ������Ԥ������ա������塡�� �����ꥷ��κ�����þ�ˤ��桼���δ����ϰ����Ȥ���³���Ƥ��ꡢ����ϥ桼�����Ф���߹�Ȥ��Ƹ��ݤ��Ƥ��롣����ꥫ�ηк�Ū�ʴ������ä��櫓�ǤϤʤ������θ��ݤϤ�����������Ƥ��롣�������볹���˷���Ф����͡��ι�ư�����Ƴ��Ϥ˹����äƤ�����������롣����������кѤδ���������Ū���̤˽ФƤ������ȤǤ��ꡢ�������Ϥ˹������ǽ���⤢�롣���ܤο�ʹ�Ǥϱ߹���Хɥ롢�Х桼���ˤ����夲��졢���ܤ�̵������Ƚ����Ƥ��롣���Ū�ʱ߹⤬͢�л��Ȥ�춭���ɤ����ߡ��춭��Ω�Ļ��ȳ���������ž��æ��ϩ����Ƥ�����ƻ���ʤ���Ƥ��롣�����Ƥ��줬���ܤλ��Ȥζ�ƶ����⤿�餹�Ȥ�������������������Ƥ���ΤǤ��롣�դ˸����С��߹�ηкѸ��̤⤢��Ϥ���������Ϥ��ޤ���ƻ����ʤ�����2011/10/06�� ���� ��Ϥꤪ��������͡����κ�Ƚ�ϡ������塡�� �����Ϥ��ᤫ������ϽФƤ���Ф���������Ť��뤳�ȤϤɤ��ˤǤ�Ǥ��롣����Ū�ˤ褯�����뤳�Ȥ��������ʤ��ʤ�����ͽ�ۤ��Ƥ����������餫��ι������СԸ���¦�ξڵ��Ժ��ѡդ�������;�פ˸�̣�Ⱝ���������뤬��������Ϻ����������줿����������ˡ�װ�ȿ�κ�Ƚ��̤Ǥ��롣������Ϻ�κ�Ƚ��Ϥ��ޤ뤬������⤳�α�Ĺ���Ÿ�������Τ�����������2011/10/04�� ���� �����ηк�Ū��������������δ������Ԥ��ΰ��� ���塡�� ������ǯ���������Ѥ����Ѥ��ȸ��äƤ��꤯�������Ĥ��ʤ��Τ���������������ȤϤɤ������㤦�������������Ķ���뼫����ư�����ﳲ��⤿�餹�ˤ��衢�ɤ����͡���ʳ������꤬���롣�����θ������դ���ޤ褤���夿�ޤ�˼��Ĥ��줿�����Ĥ����פ��Ф��ĤäƤ��뤿�ᤫ�⤷��ʤ�����������ʷ�ϵ����Ѥ�äƤ��Ƥ���ΤǤϤʤ����������ζ��ҤϤ�ä�Ϫ���Ǥभ�Ф��ˤʤäƤ��Ƥ��롣�����������̺Ҥαƶ��Ϥ�������ˤ���Τ��������������롣�Ȥ����������ǤϤ⤦��Ĥ����������롣�ܤϲ��������ܺ�̳��������ͻ�����Ǥ������ܤϤ��줬�߹�ȤʤäƤ���˽�����˴������ޤ�Ƥ��롣��2011/09/27�� ���� �����������������������ꥫ����������ܤ��������塡�� ��������ꥫ����Ĥ�����ˤĤ���¿������ɾ���ФƤ��뤬�����ߤǤ�³���Ƥ��뤳�����Ū�ʶ�Ԥ����ܤ����������ȴط����������Ƥ���ɾ���Ƥ����Τˤϻ�ǰ�ʤ���в��ʤ��ä������ܤǤϣ����������̺Ҥ�����͡��ΰռ��������������ˤʤäƤϤ��뤬�����Σ�����������ü��ȯ���������³���Ƥ������ܤ��������������ʤ��ޤޤˤ��뤳�Ȥ��Ŧ���Ƥ����ʤ���Фʤ�ʤ������λ���ϥ���ꥫ�μ����ǤϤʤ����Ȥ�����϶����ʤäƤ��뤬������ϤȤ⤫���Ȥ��Ƥ⡢���λ��������Ȥ����İ�������ǻ��äƱ��������ȤϺ���Ū�ʸ���Ǥ��ä��������ƱĴ�������ܤ������Ʊ���Ǥ��롣��2011/09/16�� ���� ��äѤ긢�Ϥ�ѻ뤷�����Ǥΰ۵Ŀ���Ω�Ƥ����塡�� �����̤줿����˽���ȯ���ˤϿ��ߤ����롣�ͤϤ����������̤Ǥ�ŷ�ȤˤǤ�ʤ�ΤǤ����������Τ�Ϥ�����פ碌��褦�ʤ�Τ����롣���������п����������Ǥ����ä��ɤ��ä��������ˤ�ȷ���������ȿ�ʤ��ۤ�ʤ��ʤ��Τ�Τ��ä����Ȥ������������롣ȷ���ξ��ˤϽ꿮ɽ���Ȥ����ܤ��٤���Τ⤢�ä�����ɤΤȤ���������Ǥ���ȯ���������ɤ��ä�����2011/09/13�� ʡ�礫�� ��ʡ��Υȥ�å�����������ǽ���Ф�ޤ����ס�ʡ�纹�̤α���˿Ȥ��֤��ƴ��������ȡ��������¶� ����ʡ���Ԥλ�̱���롼�פ��ʤ�Ƥ���ʡ��ٱ祷��åפ���Ź��ߤ��ɤ����ޤ줿�˥塼���ϡ���ʹ���ƥ�Ӥ�����������Τ��Ϥä�����ʡ�礫��Υȥ�å�������ǽ��Ф�ޤ� �פʤɤȤ��ä���뤬�꼡����Ź�ޤ��ߤ������ʡ������Ĥ����̱���롼�פ� ��Ź����Ƥۤ��� ���Ǥä���������¤Ϥ��Υץ��������ȡ�ɮ�Ԥ�ޤ���֤�ʡ�縩����¼�������롼�פ���Ʊ�Ǽ���Ȥ�Ǥ���ʡ������ȿ��������ᤶ�������䤫�ʼ����ˡ��̶彣��ͭ������ʪ��������ή�̤��ʤäƤ����̱���ܤλ����ζ彣��ľ����֤����ġ���̱�˸Ƥӳݤ��֤դ����ޥ���åץץ��������ȡפ�Ω���夲�ƿʤ�Ƥ�����Τ���ʡ�纹�̤α���������Ԥΰ�ͤȤ��ƿȤ��֤��Ƥߤơ����α������˶�ò�����Ʊ���ˡ������������Ȥ�������ܤμҲ�˰����Ȥʤä�����2011/09/11�� ���� �����꤬�����Ƥ���ȿư�Ǥ������� �����塡�� �����ڤ�˫�����ڤ��Фȸ����뤬���ֲ��Ϥ���ʤ��ȸ����ʤ��Ƥ�̾����ʡ��������ڤ��Фäƿ��٤Ƥ��뤼�פȸ�ȯ����㌔����������������ڤϤΤ��ޤ������Τ�ʤ����������������ܤ���Ǥ��ڤϸ����Ƥ��줯�餤�Τ��ȤϤ��Ƥ���������Ǥ��롣����ϾФ��äˤ��Ƥ���������̱������������Ȥꤢ����˫��Ƥ����ˤ������ȻפäƤ���Τ��������ͤϽ�̱���ηä�̵�뤹�뵤�Ϥʤ��������Ŀ���դˤष�����Ϸٲ����ܤ������٤����ȹͤ��Ƥ��롣��2011/09/06�� ���� ����դ���ʸ�����äƤ��������ʤ��Ȼפ����������塡�� �����ظ���ʪ��٤˽��ܤλ����ФƤ��롣��ʤʤɤν�����Ǥ���뵷���λ��Ǥ��뤬����²��̿������Ԥ����顦���鵮²�����ब�ɤ�������Ƥ��롣��ä�Ǥ̿����뤫���ɤ����������������꤬���������٤��Τ�̾�Ĥ��Ȼפä���Τ������Ƕ�Ϥ�������ʷ�ϵ��ϴ�ʬ������Ƥ��Ƥ���褦�����������Ӥ�����դ��Ѥ��С���äθ��ҤⲼ���äƤ��Ƥ���Τ�������������������Ū���ϰ̤�ȼ�����ҤǤϤʤ��ơ���餬�����ꤿ���Τ�������ˤʤ�Ф�������2011/09/03�� ���� ���˵��θ��դ�������ˤʤ�ʤ��������������塡�� �����ƥ�ӤǤ�����Φ�������Υ��ӥ塼��³����ʹ�����ͤ�¿������������辡����Ԥ줿ʡ����Τ��ȯ���Ϲ��������Ƥ����������٤�̱���ޤ���ɽ�������ȯ���϶�̣�Ϥ��ä��������Ǥ����ΤϤʤ��ä������Ŀ������ȯ���⤽���Ǥ��롣���Τ褦������뤳�ȼ��Τ����ڷ��ʤΤ���Ȥ�������ʹ�����Ƥ������Ǥ��뤬������Ϥ�Ϥ�ͤ���������Ȥ����Ǥ⤢�롣��2011/09/01�� ���� ���¤��������æ��ϩ�������뤫����ˡ��罰�����Ȥβ��̡������塡�� �����ûұ�ι��夬�����Ȳ��Ȥʤ����������롣�Խ�俿������³���Ƥ����Τ�����ɤ����ԻĤʻפ��⤷�ơ����줬����Ȥ������ȤʤΤ��������ȴ�������ΤǤ������Ƕ�ε����Ϥ�����̯��ư��������Ϥ�Ƥ���褦�ˤ�פ��롣���Ƥθ��ȴ��Ȥϰ㤦���ε��ۤ�ɺ���䤷����̣�臘���Ȥʤ�ƽ���ʤ��ʤ�Τ��������������μ��夷�Ƥ���������⤽�κ¤�ߤ��褦�ǡ���Ѥ��ܻؤ��Ƥ�����̡�����ƻ�����������䤫�ˤ��뤬������Ū���¤����æ�Ф�������褦�ʿ�ʪ�ϸ��������ʤ�����2011/08/27�� ���� ���¤��������æ��ϩ�������뤫�������塡�� �������뿷ʹ�ˤ�������ܤʤΤ˲��α߹�ʡ��ˤʤΤ��Ȥ�������ब���ä���������ñ��ǥ���ꥫ��衼���åѤ����ܤ����äȰ������֤Ǥ��롢�Ȥ����ΤǤ��ä����������֤Ȥ����ΤϷк�Ū�ˤȤ������ȤǤ���������̯�������Ϥ��������������п�����Ȥ����Ϥ�ؼ����Ƥ����������������Ϥʤ�����2011/08/22�� ���� ���������μ�ʬ�����ν�Ȥ�ȿ�ʤϤ���Τ��������塡�� �����ͤ�̱���ޤ�����������˷Ǥ��������ƴط��θ�ľ���ס�����Ū���Τ�æ��ν�ס����褬���פȤ�����ǰŪ�����Ȥߤ�ٻ����Ƥ�����������ϴְ�äƤϤ��ʤ��ä��Ȼפ���������ǰ������������ΰ��Фʤ�ۣ��ʤȤ�����¿�����ȤϷ�ǰ���Ƥ����ˤ��Ƥ⡣��̺Ҥ丶ȯ�̺ҤϤ�����ǰ����ȥޥ��������̤���������ʬ����������Ū��Ȥ���Ǥ���ڤ��٤��Ǥ��롣�������ʤ����̱���ޤˤϼ��Ϥʤ��������Ϥʤ��ȸ����٤�����2011/08/21�� ���� �Ƥ˲��̤�ή�ԤΤ��Τλ��ȻפäƤ������������塡�� �����Ҷ������β��̤�λ���ݤ��ä����ɤ��Ǥ⤽�������������̤Τ��ޤ��Τ�������˰�ͤ���ͤϤ������ä�ʹ���Ƥ��Ƥ�Ǹ�ˤϿ̤��������Ƥ��ޤäƤ������Ƕ�λҶ������ϲ��̤�ʹ��������Τ�����������äȤ⡢�������Ȥ�������������Τ����¤ˤ��äƤϲ��̤ɤ����Τ��ȤǤϤʤ��Τ��⤷��ʤ�����2011/08/19�� ���� �ɥ��ĤϼҲ�Ū�˷�ˡ9����ϽФ����������塡�� ����8�������ˤĤ����ͤ餬�ͤ��뵨������㤤�����Ͻ뤤����˽гݤ����ǥ���ä����Ȥ⤢�ä����ޤ�����������Ͻ�ɾ��ǻ�ɾ���äƤ����������ε���ˤʤ�����ŤΥơ��ޤ�����ˤʤäƹԤ��Τ��Τä��������ᤤ�Ƥ���Ȥ����פ������ʤ��ǤϤʤ��ä��������褬��̱Ū����Ȥ����礭�ʰ��֤����Ƥ���Τ���Ǽ���⤷����������ˤĤ������Ť�Ÿ��������Τϻ���ˤ�ä��礭���Ѥ�äƤ��������Ѥ��ʤ��Τ����˹�̱Ū�ջ֤Ȥ��ƿ��ޤä�����ΰռ��Ǥ����������ͤ�8��ˤʤ������ˤĤ��Ƥε�����ǧ���ˤ��Ĥ�η����ռ��������Τ�������ǯ�˰������ܤ��Ƥ���ΤϤʤˤ����������ɥ��Ĥθ�ȯ�����ű��Ǥ��롣��2011/08/08�� ���� �ɥ�¤�ɬ���ʤΤ������߹ⶲ�ݤ������������������η����ˤ��衡�����塡�� �������ܿͤ���������Ȥ����緲����������Ƥ������ᤫ������������ˤʤ꤬���Ǥ��롣�����ˤϺ�����夬�����ҤΤ褦��¸�ߤ��Ƥ��뤿�ᤫ�⤷��ʤ�����������ˤ�������ư���˲���ȿ�����롣����Ȥ�̵��ǤϤʤ���3��11������̺ҰʹߤϿ͡��λ�����ռ��ϳ���������ˤʤäƤ�������2011/08/01�� ���� ���������������ܤε�ϩ�ʸޡ˸�ȯ���Ρ�����Ϣ����Ǥ�Ϥʤ��Τ��������塡�� �����뤵�Ͽͤ������Ť���å����Ʊ��Ǯ���Ǥ⤳����ϰ㤦���֤ʤǤ�������ѥ�פ�������äƤ����ΤϤ���Ǯ���Ǥ��뤬������Ϣ�βƵ����ߥʡ��ˤ�����������������Ƚ�Ϥɤ���餳����ν뤵�Τ褦������ʹ��ͥåȤ���������Ȥ����ˤ��Х��ߥʡ��ǤϿ�������Ƚ����Τ褦�����Ȥ�櫓��æ��ȯȯ�����Ф�����Ƚ����������ȯ�κƲ�Ư���ߤ��줿���Ȥؤβ�Ω������ޤäƤ���褦�ˤ��������롣���Τޤޤ������϶��뤬ɯ�������䤬�Ƥ����ϥ����Ȥ��徺����Ȥϳ����˰�ž����Ȥ�����Τ������Τ��Ȥϸ��Ѥ��Ӽ��ˤĤʤ���Ȥ�����Ⱦ�ж����Τ褦��ȯ����³���Ƥ��롣��ȯ�ˤ�륳���Ȥΰ¤����Ϥ�̤�����餿��Τ褦��ȯ���ʤΤǤ��롣��2011/07/22�� ���� ���������������ܤε�ϩ�ʻ͡� �ʹ֤ȼ�������աʸ�ή�ˤ�Ũ�Ф��븶ȯ�����塡�� ����Ϫ��ʪ�ΥȥޥȤ䥭�奦�꤬��̣������ˤʤä�����ͤˤۤꤳ��Ǥ��ä��ȥޥȤ䥭�奦��ʤɤ˰����դäƤ��֤�Ĥ��Τ�����������ä�����ǯ�����ļˤDzᤴ����������ǻ�����ä���������Ϫ��ʪ�ΥȥޥȤʤɤ�Ȣ�����㤦�Τ�����ˤʤäƤ������Ҷ���ζ���Ϣ�줿���ä��Ȥ���������̣���碌�����ä����Ȥ����Ҷ��ϥ��֥ȥॷ�������̴��ˤʤä�����ɡ��ͤλפ��Ϥ������ä����Ǥ�֤⤦Ϫ��ʪ�פϤȤ�����ʬ�ˤ�����Τ�����ǽ�����Ǥ��롣��������Ǥ⸶ȯ���������ͤ����¸��ȿ���Ƥ��뤫��ʬ���롣��2011/07/11�� ����� �錄����æ�֥ƥ�ӻ�İ��������������ԤȤ����ܤȵӤ����ڤˡ��¸���ͺ ��������ޤǣ���ε�����æ��ȯ�Ǥ��ä�������ϼ�����Ѥ��ơ��錄�����Ȥ�æ�֥ƥ�ӡ�����Ȥ�����������Ф��Ǥ˸������ԣ�ǯ���Ǥ��ꡢ�ܤȵӤˤ��ĤƤη������ϴ��ԤǤ��ʤ��ʤ�ĤĤ��롣�����餳��������μ�ʬ����餷������������ͤ�ľ�������������������ƥ�Ӥ��ϥǥ����Ѥ�롣�����餫�餪�ꤤ�����櫓�Ǥ�ʤ�����̵¤��˼��������ɬ�פϤʤ��ȹͤ����������ǻפ��Ĥ����Τ�æ�ƥ�ӤǤ��롣��2011/07/09�� ���� ���������������ܤε�ϩ�ʻ��� ��������ʤΤϸ�ȯ�̺Ҥ���Ǥ�����餫�ˤ��뤳�ȡ����塡�� �������ɤ�ᤰ����ȳ�����������ַ�����ܤ������ȷкѳ��Τɤ����褦��ʤ����ͤ�˸����Ĥ��Ƥ��롣���������ؤ�ˡ����Ω�μ������տͻ���������������̺Ҥ丶ȯ�̺Ҥ�������������ʤ��फ������ա��IJ����ޤؤο͡����Կ������礵�����2011/07/01�� ���� ���������������ܤε�ϩ����ˡ������������������������������̺Ҥζ����������塡�� ����ï�⤬�פ����������٤����䤷�ʤ����ȡ���������ˡ�Τ��ȤǤ��롣��������ˡ��Ω�˻��֤������ä��ˤ��Ƥ⡢����Ū�������Ȥ��ʤ�Ǥ���Ф���������Ƚ�����ϽФƤ��ʤ��ä��ΤǤ������Ȼפ�������Ū�Ǹ���Ū��������Ȥ������ȤȤ������٤�Ĺ��Ū��¤��ä��������ۤȤ����̤���ƹͤ������������Ū�Ϥ�����С��͡�����������Ƚ�ϽФƤ��ʤ��ä��ȿ仡����롣��2011/06/30�� ���� ����ϻ����̤��̿�Ǥ���Τ��ʡ��ˡ������塡�� ����������ˤ���«���Ȥ��ε��Ȥ��θ��դ����롣������ͤ�����̤οʹִط��Υ롼����̣���Ƥ��롣���Υ롼��Ϥ��������Ԥ�Ķ�����ط��ˤ�ä��ˤ�줿�ꤹ�롣�����Ǥ����������������ޤ��Τ������Τä�����Ȥ������ǽ餫�餳����ñ���ˤ���Τ϶ä��Ǥ��롣ȷ��ͳ���פȿ���ͤ���路���Ȥ������«�Կ��μ�����ؤȿ�Ǥ�դ�ȿ�ΤȤ����褦�ʻ��֤��ФƤ��Ƥ���Τ������������ػ����ε�ľ����Ф���ȷ�����֤ޤ�ǥڥƥ�աפ�����Ƥ���ΤǤ��롣���Τɤ��ʤäƤ���ΤȤ����Τ����̤ο͡���ȿ��������2011/06/10�� ���� ��फ�����뤤����फ������Ȥ����ַफ�������塡�� �����������뤫����̤����줬������פȤ����ϥ��åȤˤϤޤ��ʹ֤�Ǻ�ߤ������뤳�Ȥβ�����äƤ��롣������������ο�Ǥ��ᤰ����ư�ˤϤ�������������ư������äƤϤ��ʤ��ä����ƥ�Ӥ����Ǥ������εľ�������ʤ���������Ȥ����ζ�Ǻ�ϴ������ʤ��ä���̱���ޤξ�����ĻΤ��������褦�Ȥ���ư�����ܤˤĤ������٤�����������Կ�Ǥ��ư���ι�������Ф�����ؤ�ɽ�����뤳�Ȥ������Ǥä�����2011/06/03�� ���� ���̤ᤤ�����Ȥ�³�����ܤθ��Ϥμ��դ������� ���塡�� �����ޤ�Ȭ��ǤϤʤ��Τ˲��̤ᤤ���ä����Ԥ��Ƥ��롣�̺�ľ���ʡ����츶ȯ�δ���Ū���֤ؤ��б��������ܤ����Ťδ���ʴط����������Ƥ��롣�̺�ľ��θ���ϧ�ؤγ���������������Ǥ��롣���η�ϴ�š���IJ����š������ϰ����Ѱ���ʤɤ��������ư��������褷�Ƥ����������顢���������ηаޤǤϤ���ޤ��Ȥϻפ������͡������η�����ܤ��Ƥ����Τ����ܤ����Ťʤɤξ��ڤ��������μ������ޤä��褦�˸����ʤ�����Ǥ���Ȼפ�����2011/05/28�� ���� ���ޤ������Ȥ�����ζ���⤯�Ĥ��Ϥʤ����������塡�� ����������������Ĺ����ľ�ͼ���ˡ�¨���Ǥ���٤��Ǥ���Ȥ�����ʤ����ä����Ȥ�������Ƥ��롣�ͤϤ����ƥ�ӤβǸ��Ƥ���Ȼפä����������³���ᤰ�äƤ��͡���ư�������뤳�Ȥ��ΤäƤϤ��뤬�����줬���Τ褦�ʷ��Ǹ���Ƥ���Ȥ������ʤ��ä�����Ǥ��롣����������Ĺ�ϻ�����Ĺ�ΰ�ͤǤ��ꡢ����ο���ˤĤ��Ƥ�������ȯ����Ȥ�ǰƬ�ˤʤ��Ĥ�����2011/05/25�� ���� �̺��������Ǥ�������ư���Ƥ���Τ�˺���ʡ������塡�� ����5��12����ī����ʹͼ�����ƾ屡�Υ�ӥ��Ѱ�Ĺ���Ϳ���ޤν��ä��ܤ�����̡�����ŷ�ִ��Ϥ�����Ŵ��ϰ��ߤ���ǰ�����ż�Ǽ���Ϥؤ������Ƥ����褦�˹������ʤ˵���������ȯɽ���������Ƥ��롣���������Ŵ��Ͽ��ߤˤ����ŷ�ִ��ϰ��ߤ˰۵Ĥ�Ω�Ƥ�����ꥫ�����������Ȥ������ܤ���롣����ꥫ�������Ǥ⤫�ĤƤ����ƹ�աʼ����������Ǥι�աˤκƸ�Ƥ������������뤳�Ȥ��������ƤϤ����������Τ褦�ʷ������Τˤ��줿�ΤϤϤ���ƤǤ��롣��2011/05/19�� TPP��æ�������Хꥼ������� ���Խ�Ĺ�Ѹ���TPP���äؤȤޤ��ʤ���ֿ���ͳ���Ū�̺������פΥ��ʥꥪ�Ȥɤ��й����뤫���������¶� �����Ƥ���ФƤ����ʡ��Ȥ����Τ�Ψľ�ʴ��ۤ������ܷ���Ϣ��������������ܤ��̾���ά�˴ؤ��������ȯɽ�������������ƤˤĤ��Ƥδ��ۤ�������ϡ���̺Ҹ塢���Ĥ����ڤ��Ƥ���TPP�ʴ���ʿ�ηк�Ϣ�ȶ���ˤˤĤ��ơ���������äϰ������פ���������פȤ��������ǡ��ֿ̺Ҹ�ηк������˸������������Х�ʻ���Ÿ�����߳�ʥ��ץ饤��������ι��ۤ��Բķ�פȼ�ĥ�����ä��ʤ���Сֹ��������������ԣУл��ù�˰�ž���Ƥ��ޤ��פȡ������Ȥ⸫������ڤƤ��롣��2011/05/17�� �ˡ������� ��ȯ�Ϸ�ˡ��ȿ�Ǥ��롡����ϸ��黰 �ڤ���ݤݼ˸�ȯ����ۿ�ʹ����줿���Ƥǡ�ͥ�줿���ƤǤ�������������꿷ʹ�ˤϻ�ǰ�ʤ���ܤ�ޤ���Ǥ��������Ժ��ѡˡ���ȯ�Ϸ�ˡ��ȿ�Ǥ��뤳�Ȥ����Ū�˥ե������Τ�¨���ƽ줿���Ƥǹ�����������ΤäƤ����������������Ԥ�λ������ƷǺܤ��ޤ����ʤ���ݤݼ����Ŀ��ˡ�2011/05/16�� ��������̺� ���Խ�Ĺ�Ѹ��ۼ��Է��ξ���ԤϤ���ʤˤ��餤�Τ����������¶� ��������ʡ֤Ĥ֤䤭�פ��Ǥޤ�äƤ��롣ʡ�縩�λ����������ڤΥ��ԡ���Ƥ���Τ�Ȥ館�����������θ��λ������Υҥ������̤��ơ���������ڤ���Է��ν�̱�˿��٤����뵤�����פ��ǤŤ��Ƥ��롣�¤ȶ�Ǻ�ˤʤ����ڤ�̤�ʡ���������Ȥؤλפ��ʤɤߤ����ͤ��ʤ���ŵ��Ū�ʺ��̸��⡣����ʡ������Ƚ������ɤ�Ǥ��ä����֤Ҥɤ��פȰ�������äθ������ǵ㤤�Ƥ��뵤�ۤ����������Է��ξ���ԤϤ���ʤˤ��餤�Τ������ä��鸶ȯ������ˤĤ��졪��2011/05/14�� ���� ��̺Ҹ�������˱߹�ϥޥ��ʥ��ǤϤʤ��������塡�� �����߹�Ȥ����Ȥɤ����ȹ����Ƥ��ޤ��Ȥ���������Τ��⤷��ʤ�����������ݤ��ɬ�פϤʤ����߹���٤�����˸�������ܷкѤδ�����͢�м�Ƴ�ηкѤ�������Ǥ��ä����ܷкѤδ����ǤϤʤ��ä���͢�м�Ƴ�ǹ���Ĺ��뤲�Ƥ������ܷкѤι�¤Ūž�����������Ƥ��ʤ����Ȥ˷кѤ����ڡԴ����դϤ���ΤǤ��ꡢ��̺Ҥ����������������Ǥ��ʤ���Фʤ�ʤ��ΤϤ���ž���Ǥ��롣��2011/05/12�� ���� �ӥ��ǥ����ϥƥ�����β��ˤʤä����������塡�� ��������ꥫ���ܤϥѥ�������ˤ����ƥӥ��ǥ����������������Ƥ��롣������ƻ��ʹ����ȿ��Ū�˻פ��⤫����Τϡ֤��ä���ƥ�����ϲ�褹��Τ����פȤ�����ǰ���ä����ƥ�����ϲ�褹�뤳�Ȥ�ʤ����ե��˥�����Ǥ����褬����뤳�Ȥ�ʤ����Ȼפ����ӥ��ǥ�����Х���ꥫ����ν��Ԥˤ��ƥ���ꥫʼ�ʤɤ������饯�䥢�ե��˥���������Ϥˤ��餷�������ǤϤʤ��Τ�����2011/05/05�� ���� ��̺Ҥ����ܤμҲ�кѡʤ�����ˡ����ɥ���̲������ȿ̺������������塡�� �����ɥ�ϥ���ꥫ�ι���̲ߤǤ���Ȥ���¦�̤ȴ��̲ߤǤ���Ȥ���¦�̤���äƤ��롣�����Ƥ��δ��̲ߤȤ�����̣�϶�����������̲ߤ��̣���Ƥ���������ꥫ�кѤ����ΰ�����Τ褦�������кѤ��̣���Ƥ����ʤ�ɥ뤬�����̲�Ū�ʰ�̣�Ǥδ��̲ߤǤ��ä����Ȥ�̷��ʤ�¸�ߤ���������2011/05/03�� ���ڡ���ǥ��� ���Խ�Ĺ�Ѹ����������줵���꤬�Ȥ��������ꥴ��θ�ȯ����ɤ�����Ƚ�ɤ˿��֤äƤ��������ơ��������¶� ������̾��ɾ���ȤǷбĥ��륿��ȶȤ����������ͥåȾ�ΰ����θ�ȯ��Ƚ�ɤδ֤Ǥ���äȤ���ͭ̾�ͤˤʤäƤ��롣���������ʹߤ�ʡ����츶ȯ��˽�����������ȯ��Ƚ��Ϥ���������ϤĤ����δ֤ޤǸ�ȯ����ɤκ���ü�ˤ��ơ������äƤ����ͤ��������ब��ʡ����츶ȯ����ȯ����ľ��Σ���15����������ϡ����У£ХͥåȡפȤ��������ͥåȥ����Ȥǡ����ܤθ����ϳ�ȯ�ϻ��¾塢����ä��פȽ������Ҥ�ɿ�Ѥ��롢�¤˸����ʷ��Ҥ֤�Ǥ��롣��2011/04/30�� ���� ��̺Ҥ����ܤμҲ�кѡʤ��ΰ�ˡ����߹�ȥɥ�¡������塡�� �������������ε����Ϥʤ��ʤ��ޤȤޤ�ʤ����������Ƥ��롣�������̺Ҥ����ܷкѤ�Ҳ��Ϳ�����ƶ����ʳ���ï����ʤ��Τ��������������顢���������ȸ��ä��Ȥ����ǤޤȤޤ�ϤĤ��ʤ��������̤����ȤߤȤ����٤�ǧ������Ĥ��뤳�Ȥ����ʤ��Τ��Ȼפ�����2011/04/26�� �ˡ������� �ɥ��Ĥ�æ��ȯ�����ܤ��ơ����ֺ��ʿ �������ǯ�ͷ��ᡢ�ɥ��Ĥ�ι�Ԥ��Ƥ��ƥե�ե륿�������륲�ޥ��ͥĥ����ȥ���λͷ�������ý����ˤ��뵡���ä������ܤο�ʹ�ˤϸ����ʤ��������Τʼ�ĥ��æ��ȯ�ý����ʤ���Ƥ��������̥ȥåפθ��Ф����֤�����Ũ�����ȥ�פǡ��֥ӥ���åס��ޥ륯��������衣�ȥ�åƥ�������Ǥ�����æ�Ѳ�ǽ�פȤ������꤬�դ��Ƥ������ޥ륯���ϥߥ��إ�Υ��ȥ�å���ʶ����ȥ�åƥ�����Ф��ޤ���ɽ�Ǥ��롣��2011/04/22�� ��������̺Ҥ���1�����ơ������弣 ������̺Ҥȸ��ä��ͤ�����������Ѥ�ä��Ȥ����Ϥʤ����̺Ҥ����������͡��λ���α��ʤ��餢�줳��ͤ��Ʋᤴ���Ƥ�������Ǥ��롣���٤μ��ͤ��ɤ��ʤ��������줬�ȵڤ�����֤�ͫθ���Ƥ��롣������������̺Ҥ��ͤΤ������Τʤ��θ��ʤ���ִ��Ф��Ѥ��Ƥ��ޤä����Ȥϵ����ʤ�����2011/04/13�� ���ȿ� ����������Ӥ���ڡ�����������ʽ��ǥ���������ȡ���ȡ� �������ΰ콵�֤ǡ�ʡ����濴�Ȥ������Ϥ���ڤ����Կ��Υ����ѡ�ŹƬ����ä��ޤ���������Ϥ��������ڤ��������������Ф��줿����Ǥ��������ʤ���������Ƥ���櫓�Ǥ����������ο��Τ�Ϳ����ƶ��ˤ������������Ϥ���ޤ�������ϡ���������äƤ��롢�Ȼפ��ޤ������Ȥ����Τ⡢�¤����ܤǤϡ����Ǥ˿���ǯ����������������Ӥ����ʤ�����Ū�˿��٤Ƥ��뤫��Ǥ�����2011/04/02�� ��������̺� ���ε������ľ����ư�����ɰ�Ϻ ��������9.0���Ͽ̤�ü��ȯ�������Ȥ��⤿�餷������Τ��äƤʤ��絬�Ϥ�ŷ�Ҥȡ�������տ路����ȯ�ν�����ΤȤ����ͺҡ�ȯ����20�������������������ؤ���餷�����Ƥ���͡���¿�������ҳ��ϤǤ�������ʤ������Ǥ�����ɤ��ʤ뤳�Ȥ��������ˤ���Ƥ���͡���ޤ��ޤ����������ޤ������Τ褦�ʻ��˲��Τ褦�ʤȤƤĤ�ʤ��ʤȹͤ����뤫�⤷��ʤ�����Ƥʤɡ������ߤ��ʤ��Ȼפ��뤫�⤷��ޤ������ε�������ܡʤҤ��Ƥ������ˤΡ���ľ���ε���פ�ª����Τ�������ε����Ԥؤ���Ȥʤ�����������ޤ������Ȥϵޤ��פ���ΤǤϤʤ����Ȼפ����Ȥ����Τϡ���ǯ�٤�ͽ���Ƥ���¾�ο��ġ�����ˡ���������Ƥ��뤳�Ȥϡ��мव���٤����ȹͤ��뤫��Ǥ���2011/04/01�� ʡ�礫�� ���Խ�Ĺ�Ѹ��۰ŰǤ����᤹���ۤȹ�ư�������¶� ������³Ū��³�����š�����ᤤ�Τ����䤨�����롣���ؽФƤߤ�ȡ���ŷ������������ޤ��ܤ�Ť餷�Ƥ⸫���ʤ��ä����������⸫���Ƥ��롣����������ԤΤϤ��졢����Į�ȶ����ܤ��뾮�⤤���ξ�����������������ߤ��ΤϤ��Ĥ��ä������ȵ����ɤ롣����ǯ�����䣳��ǯ���餤�����Τܤ뤫�⤷��ʤ�����2011/03/31�� ���� ����������Ʊ���ʡ��ˤ�ɬ�פǤϤʤ����������塡�� �����դ������δ��������®ƻϩ�ʾ���ƻ�ˤ��ä�ʡ��Τ��來�Ԥˤ���Ϸ�ͥ����˵߱�ʪ���Ǥ������ͤν�°�����9������˻ߤβ�פ�ͭ����ȥ�å������Ѥ��Ƥ����䤫�ʤ���ǤϤ��뤬�߱��ư�������Ȥ������Ȥˤʤä��Τ���������Ȣ���ޤǽгݤ�10���ƴ�˵ͤ�Ƥ��ä�̾���100�Ĥ����ޤ��줿�����ϤǤϰ��������ڤʤɤο��ब�ߤ����ȤΤ��Ȥ��ä����������ơ����Ƥ��������������2011/03/30�� �ˡ������� ������ȯ�Ťΰ������ä�ɬ�����κƸ�Ƥ����¼�������ؽڶ������䤦������Ҿ�ͽ ���������ؤνڶ�������¼����ʸ����ϼҲءˤˤ��С��ָ�ȯ���ʤ�������������Ρ����ϲ�ҡ������ƹ�̱��¿���Ǥ����ָ�ȯ�ϰ����פȻפäƤ��������פȤ����ʡ����俷ʹ��3��25��ī��11�ַ̡к�������ʹ���סˡ��Τ��˸����ϳز�ǯ1��˼»ܤ�������Ĵ���ǤϹ����4��ʾ�οͤ���ȯ���Ѥ˹���Ū�Ǥ��ꡢ����٤����Ȥΰո���1��������ä��Ȥ������Ȥ��顢���Τ褦�ˤ�����Ǥ��롣�������������ˤ����Ǥ�����������2011/03/29�� ���� �۵ޤε߱�����줽���������Τ���� �����塡�� ����������ͧ�ͤμ�Ť�����˽гݤ������������������ˤ褯���Ť����Ȼפä������Ĥ�����������������ֺ�ǯ�κ��Ϥ��襤�������͡פȤϽ�˼�Ȼ���ΤĤ��Ǥ˸�����Ф���Τ������դ��ԤäƤ��ä����餯�Τ˵������ɤ����ǤƤϤ�館�ʤ��������Ȼפ������������2011/03/25�� ��������̺� �����¤ο̺ҡ�����������ʽ��ǥ���������ȡ���ȡ� �������������ˤ���������Ͽ̡�������ﳲ��⤿�餷�ޤ������ۤȤ���Ͽ̤Τʤ������礫��ܤ꽻�����ϡ��Ͽ̤��ݤ���褯����������ˤ����Ȥ�ͤ��ȤΤ褦�˻פäƤ��ޤ�������������μ��Ǥ��ΤäƤϤ����ΤΡ������ҳ��Ȥ����вл�����ȯ���äȤ�ռ����Ƥ��ޤ����������餿����Ͽ̤��ݤ���פ��Τ餵��ޤ���������Ϥ������ˤϤ�����߿����夲�ޤ����ޥ���ǥ����ȤϾ�����ä������ǡ�������Ͽ̤ˤĤ��ƽޤ����ʽ��ǥ���������ȡ֥��åץ륷���ɡ������������פΥ��ޥ�������ˡ�2011/03/24�� ���� ����Ū�ʶ�Ԥϲ���ż����Ƥ��뤫�������塡�� ������������Ǥ��������꼭Ǥ�������Ū�ʶ�ԤǤ��롣��Ǥ��������ۤ�����������ǵ��μ�Ǥ��ä��褦�������Ǥ����̡��⤪�������Τ������ޤˤ������Ȥ������¤����äƤ�������ƨ����ʤ��Ȥ������Ȥ��ʡ���2011/03/11�� ���� ��Ǥ�ǤϤʤ����ʤ������������䤦�٤����������塡�� �����������٤Τ��ȤǤȤ䤫�������ΤϤФ��Ф������Ȥ������Ȥ����롣�˾�����Ȥ���������ʤȤ����Ǥ��롣������������������ȼ����Ǥ��ˤĤ��Ƥ���ľ�ʴ��ۤ�����Ǥ���ɤ����ޤ줿���⤽���ߤ���ʤ��ä�̱���ޤμ�Ǿ�ؤ�𤱤ʤ��������줬�ޤ����ܤ�̱���ޤθ����ʤΤǤ���������2011/03/08�� ���� Ϫ�褷������ꥫ��������������̷�⡡���Ťʤ�ŷ������¸�������Ⱥ��������ѡ������塡�� ������������������������ܤ�����ꥫ�˽��ʤġˤ����饯�ؤ�Ԥ��סʡ����βȡ��ĵ����ҡˡ��Ƕ�γڤ��ߤϻ���ΤĤ��Ǥ˥֥å����դȤ������ܲ��˴�뤳�Ȥ��������βΤϤ����Ǹ��Ĥ����ܤ��齦�ä���Τ����ͤϺ�ԤΤ��Ȥ��Τ�ʤ��������ˤ����륢��ꥫ��ư����ͤ��Ƥ����Τǰ��Ѥ����Ƥ��ä�������ꥫ�Υ֥å��������ϥ��饯��������ͳ�Ȥ��ơ֥��饯�μ�ͳ����̱�粽�פ�Ǥ������ޤ������μ�ͳ����̱�粽��⡣�����ǥ��奸�˥��䥨���ץȡ��Х롼��ʤɤ��������Ⱥ۹�Ȥ�ٻ����Ƥ������������ϰ�Ǹ��Ϥ��ѳפ�ᤶ��̱���ι�ư�������Ƥ��뤳�Ȥ�פ���̷�����������ΤǤ��롣��2011/03/04�� ���� ����줫�鲭���פ��������ʷ��긢�Ȥ�����ǰ���о��������Ū��̣���䤦�����塡�� �����ͤ������Ǥ�̱���ι�ư������ʹ���ʤ��餳�δ֤β���ο͡��ι�ư�Τ��Ȥ�ͤ�������Τ���ϲ���ο͡���ư����ּ��ʷ��긢�μ�Ω�פ���ǰ�����ʤ��顢����Ū���Ϥ��о�Ȥ��������ˤ�Ϣư���Ƥ���ȽҤ٤Ƥ������������٤�ͥ�줿����Ȥ��Ƶ����˻Ĥ롣���Τ����ϡ�̱�����פȤ������ȤǤϤʤ����ּ��ʷ��긢�μ�Ω�פȸ������դ�Ȥ��Τ�������ˤ���ͳ�����롣���ܤ䥢��ꥫ�ϡ��������Ϥζ��岽=��ͳ����̱�粽�פˤ����Ȥ���̱���ޤ��̡��������������ϲ���ο͡��ΰջסʰռ��ˤǤ��뼫ͳ��̱�����Ȥϰ�äƤ��뤳�Ȥ��ΤäƤ��뤫�����Ʊ������ͳ��̱�����Ȥ������դ�ȤäƤ��Ƥ����餫�˰ۤʤ�ΤǤ��롣��2011/02/28�� ���� �����̱����ư�����鸫��ֶ���ס����ƥ�ӤΤ��Ȥˤ����ʤ��������ͤ��Ƥ������ȡʣ��ˡ������塡�� ������ӥ���ư�����濴�������Ǥ�̱��������Ū���Ⱥ�Ū���Ϥ��Ф��������������ǡ���ʬ�ε����ˤ��뤫�ĤƤ����Ȥ����餫�˰ۤʤ�Ȼפ����Τ����롣��2011/02/26�� ���� ̱²����Ʈ��Ȥϲ����ä��Τ����������ƥ�ӤΤ��Ȥˤ����ʤ��������ͤ��Ƥ������ȡʣ��ˡ��������塡�� �������礤�Ȥ������ФǤ�ƥ�ӤΤ��Ȥ����ˤʤ롣�फ���ޤ�Ǯ���ʵ�ͥե�����ä����������η�̤����ˤʤäƹ�������夫�ʤ����Ȥ����ä������ϰ㤦�������ʤΤ�����ӥ����Τ��Ȥ����ˤʤäƻ������ʤ��ä��ΤǤ��롣�⤦��̿�Ȥ������������ե��Ⱥۤ����ݤ˹Ԥ��Ȼפ����Ĥ�Ϥ굤�ˤʤ롣��2011/02/25�� ���� ��������ߤ����Ƥ���Τ�̱����Ǿ�ؤǤ��롡�����塡�� ����������ϸ����ˤ����Τ���������ȸƤФ��ư���������������Ū�ʽ��Ĥ�������˸����븽�ݤǤϤʤ������ͤ餬�ȶ���ܷ⤷������Ū���ݤȤ��Ƥ�Ϣ���ַ�������⥲�ФȸƤФ�뿷��������ɹ��褬���롣�ͼ��Ȥ⤽�ζ��դˤ����������ɹ���ΰ��Ȥ����٤��褤���ȿ�Ū��������ư��ߤ�и��⤢�뤫����老�ȤȤ��Ƹ��������ʤ��Τ����������Ǥ�����ϱ���������ԤȤ���˵�Υ�Τ���ʹ֤ȤǤϻ��֤���äƤ���Ȥ������Ȥ�������������ԤȤ��ƿ���äƤ��뼫�ʤȤ���Ƥ���⤦��ͤμ�ʬ�ȤǤϤȤ������ȤǤ�褤������Ͽʹ֤�¸�ߤ�٤ˤޤĤ��̷��Ȥ��äƤ⤤���Τ�����ɡ�����Ū�ʽ��Ĥ�ư�����鸫��������Ȥ��Ƽ��ФΤ��뤳�Ȥ��Ȼפ�����2011/02/23�� �ߤ롦��ࡦ���� ��ʹ���ɤࡡ�������͡��� �������ܤν��ǥ���������Ȥ���ʬ����������ᡣ�ֲ����Į����͡פ������Ҥʤ�¿���Υ饤������ȯ�������ٱ礷�Ƥ������ޤ��ֳ������Ϥ�Х������ס��ľ��롢����Ű�ȶ����ˡ��֥�������������ȡס���Little DJ������������ʪ��פʤɼ����ɮ�롣���ξ�������ˤ����äΤ�Τ����롣����δ�Ƥϵ��ͻ�β�ҡ֥��åץ륷���ɡ������������פ��Ф��Ƥ�����ޥ����顢�����ο�ʹ�ˤĤ��ơ���2011/02/22�� ���� ȷ��ȯ�����ǥ�������Ƚ�Ǥ����ʤ�����Τ��������塡�� ����ī����ʹ��ͼ������γ�ҤȤ��������ʥ��������롣�ɸ��Υ���ब�ܤäƤ��롣2��15����ˤϡ���ľ��Ψľ�ʿ͡�����ιͤ������Ф��դ���Ƥ�����ȡ���ν���ɤ��ˤ뵤����ʤ����ƹ��ľ��Ƚ�⤻����ƨ���������פȤ��ä���ȷ�������꤬��ŷ�ִ��ϰ����������Ť˲�������ͳ�Ȥ��ơֳ�ʼ������ϡפ����ؤ��ä���ä����Ȥؤ���Ƚ�Ǥ��롣2��13���դβ��쥿���ॹ�˷Ǻܤ��줿��ΤǸ��դ��ڤ��Ȥ����Ф���ޤǤ�����ľ�ʴ��ۤȤ����Τ��ͤΰ��ݤ��ä����ͤ������Ǽ��夲�����Τ�ī����ʹ����Ƚ�Ǥ��롣���Υ�����ޤ��Ƚ�ؤε���Ǥ��롣��2011/02/21�� ���� �����ץ�̱���ι�ư���۵������뵭���ȸ��ߡ������塡�� �����������ػ�ǯ���λ����ä��������եȤΥʥ��������ΤΥ����ꥹ��ե���Ф������褬������줿���ޤ����ϥ�Ǥϥ�Ϣ���ο������Ф���̱��������줿��������ư��Ȥ��ϥ˽ư�Ȥ����褦�ʸ��դǤ��ä��褦�˻פ�����Ū���ä���1956ǯ�Τ��Ȥ�����2011/02/18�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ�����7) �������ϼ�������ˤ����衡�����塡�� ������̾�Ų�ȯ �ɤ���㤢��̿���٤Ȥ����ܤ����롣��¼����������������˶۵ޤ˽Ф�����ΤǤ��롣��̿���ɤ����ϤȤ⤫���Ȥ��Ʋ�¼�ι����ʡ֤ɤ���㤢�פ��Ȥ������λ�����̾�Ų���Ĺ�����ԵIJ�βʤɤ��䤦�ȥ�ץ�����ˤ����Ƽ¸��������Ȥϸ����ޤǤ�ʤ������������¼����������¼���Ϥ�������Ϻ�ȥ��������Ƥ��������ή���줿����2011/02/12�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ����ʣ��˾����ӽ��αƤˤ���Ĥ���帢�Ϲ�¤�������塡�� ���������˻Ĥ���դϾ��ʤ���Ʊ���褦�˵����˻Ĥ�����Ū����⾯�ʤ���������ë�����ܤ�̱���ޤ�����ˤ��äƹԤäƤ��뤳�Ȥʤɤ�����˺�����Ƥ�������������ï�����α��Ϥ��ʤ����������������٤�о�����Ϻ����������ˡ�Ǥε��ʻ�����Թ��ʽ�����ǤϤ��뤬������ʤ������˻Ĥ�˰㤤�ʤ�������������λ��郎���ߤ��������ħ����褦�ʤȤ��������뤫������ͤ�Ϥ��λ���ΰ�̣�����Τ������Ϥˤ�äƤĤ��ޤ������ߤ��������Ф���ǧ����Ƚ�Ǥ����Ƥˤ��ʤ���Фʤ�ʤ��������Ʊ���˸��ߤ��������Ф���۵Ŀ���Ω�Ƥ��̣�����ΤǤ⤢�롣��2011/02/03�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ�����5�ˡ������ī�����������������塡�� �����褯������Ǹ��Ƥ���Ȥ������Ȥ������롣����ϥ��ǥ��������佡��Ū����ǰ��ʪ����Ƚ�Ǥ��Ƥ���Ȥ�����̣�Ǥ⤢�롣����Ϥ��μ��Ω��ˤ���ͤ�¸�ߤ����餫����ʬ���äƤ���Ȥ�����̣�Ǥ���˸��Ǥ����ȤϤʤ��������ε�ǰ����ä��б��Ǥ��뤫��Ǥ��롣����������Ǥʤ�������Ƚ�ǤȤ����褦�˻פ��Ƥ����ΤϤ����Ǥʤ��������Ǥ��롣�㤨�Х�ǥ��������ɤ��Ф��ʤ��Ȥ���Ω�Ǥ���Ȥ��Τ��줽�줬�Q�Τ褦�˿�Ʃ���Ƥ��뤫�����Ȥ��������롣�����顢�ͤ�Ͽ�������ƤϤ��ʤ��ȾΤ��Ƥ����̡��ο�����Ƥ��ʤ���Фʤ�ʤ������������Ϥ������ɬ�פǤ��롣��2011/02/01�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ����ʣ��ˡ�������ܤ�����Ū�����������塡�� ������ˡ�ڤ����ݡפȤ������դ����롣�ǤƤ��ǤĤۤɤ��β����Ϥ褯�ʤ�Ȥ�����̣������̱���������Ǥλ������˱���ʤɤϵդǤ��Ф��ۤ�����ˤʤ롣�����������������������ۤȵ������ʼ�̱�ޤȸ����ޡˤȤۤȤ���Ѥ��ʤ��ʤ뤫������Ⱝ���ʤäƤ��Ƥ��롣���ΤޤԤ��������ݻ��Τ����̱���Ϥ��Ȥ������֤ˤʤ롣����Ū�ʻ��ۤ�ů�ءˤ���������ɤ��Ф���ͤ䵻�Ѥ�����Ĺ����Ϣ�椬���ܼ�Ǿ�����餬�����ϰ����ȸ����롣��2011/01/29�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ�����3�˥���ꥫ�������ϸ��μ�Ω�����˻ߡ������塡�� ������ʹ�������Ǿ���̤�ڡ������Ƥ��롣������ 2�����Ȥ�פ����θ��Ф��Ǥ��롣������������ƻ�ˤϤ��β��̤�ξ��������⤽�η�̤��������ƤϤ��ʤ���ī����ʹ�μ����2009ǯ�ν��˥��Хޤ�ˬ�椷�����Τ褦�������Ƴ������Τ褦������ʹ�����Ƥ��ʤ��������Ƥ��������β��̤�����Τ褦��¦�̤������ä����Ȥ�ʪ��äƤ��롣9ǯ�ν���ˬ��Ǥϥ��Хޤ����������ǺǤ���פʹ�ȸ�ä��Ȥ����������ˤʤä����Ȥ��۵�����롣��������ܤǤ���ƻ�������˴�Ť���ΤǤ��ä��Ȥ������ޤ��դ��Τ�ΤǤ��ä�����2011/01/24�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ�����2�ˡ��ηä���Ϥ�ʤ���̱�������塡�� �����������ͤβȤζ��դǡ�����ë�ܥ��ԡפ�������Ƥ��������Σ���������ȣ���������ǯ�Σ�������ȣ���������ǯ�Ԥ��빱��λԤǤ��롣433ǯ���ˡֳڻԳں¡פΰ�ĤȤ������ޤ캣���ޤ�³���Ƥ���餷������Ƨ�Τ褦�ʿͺ��ߤ���ǹ�ơ�ʤʤɤ��ܤ���ʤ��顢�ż�ΤϤ������⤤�������������Ȥʤ��˿ͤ�̥�����Τ����롣�פ�λ��ļ�����������ʷ�ϵ��������ˤϤ���Τ������Ȼפ������֤�ФƤ��³���Ƥ����ͤε�ʬ�����ΤȤ����뤬�����������˷�ǡ���Ƥ���ΤϤ���������Ȥ�פ�����2011/01/23�� ʸ�� �ե�ν����Dz���Ĥ������������ž�������ꤷ�ƥҥåȺ���äƤ����� �����ե�ν����Dz���ĤˤϥҥåȤ����Ф��Ƥ����ͤ����ͤ����롣�����ž�������ꤷ����ǰ��ĩ�ߡ�����������������Ƥ��Ƥ����������αDz�϶���Ū�˥ҥåȤ��������ǤϤʤ�����������ˤ���ƶ���Ϳ���Ƥ����Ȼפ��롣�ե�ν������Ĥˤ�룳�ܤαDz����ˤȤꤿ������¼�������ˡ�2011/01/19�� ���� �������ܤ�����������Ƥ����Τϲ�����1�� �ޥ˥ե����Ȥ��դ��ƿϤκ�ʸ���ä��Τ��� ���塡�� �����ֿ������פȤ������դۤɤδ����ϤϤʤ������ֿ������פȤ������դ�ʹ��������⤢�롣��Ϥ괨������¿�����ʤ�ȤϤʤ��˾�ǯ���ޤǤ�ᤴ������Τ���뼯�ߤ����ȸƤФ�봨�����۵����롣����˿Ȥ��ڤ���פ��������ؤؤϼ�ž���̳ؤƤ����Τ��ä��������ε������Ǵ������봨���ϼ�����°���Ƥ����Τ������ͤ�Ϻ������������������Ǥ⤦��Ĥδ��������Ƥ��롣������Ҳ��ȿ�����뤳�����ʿ�Ū�ˤ�ư���Ǥ��롣�����Ǥޤ����ͤ�ϴ����Ȥ�����Τ����Ƥ���Τ�����2011/01/16�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ����ˡ��뤨�ʤ���Τ�Ļ벽���������Ϥ��塡�� ��������������Ūư�����ظ�ˤ��äƷ����ϤȤ��Ƶ�ǽ���Ƥ����Τ֤���������Ȥ����ߵ���ä�Ĺ����ɾ�ˤʤäƤ��ޤä��������ˤϻ뤨�ʤ��Ϥ�¸�ߤȤ����ռ���Ư���Ƥ��롣���ܤ��������Ϥϸ��Ϥν�Ȥ��︢�ϼԤ��ܤ��鱣�����Ȥˤ��ä������Τ餷���٤��餺�פȤ����Τ������Ǥ��ä�������ꥫ����������ۤ��ظ�˱������ȤǤ����ǽ������Ȥ�����̯�ʴط������ܤȤδط��Ǽ�äƤ�������2011/01/12�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ����˴��̲ߥɥ���䴰ʪ�Ȥ��Ƥαߡ��� ���塡�� ����1980ǯ��θ�Ⱦ�˸������äƤ������Ȥ����롣��˼ԤϤ��Ĥ�������Ŵ�ξ峤��Ź�ˤˤ����ͤǤ��ꡢ�к�Ū�ˤ����뤤�ͤ��ä����־���ʬ�ϸ����פ�����̾�Τ��ä���1980ǯ���Ⱦ�Ф���1990ǯ��ˤ��������ܷкѤϥХ֥�кѤ����������䤬�Ƥ���þ���ƹԤ������Ǥ��ä�������˼Ԥ��褯��äƤ����Τϡ������ܳ�Ū�������кѤμ�������饢�������ڤ��ؤ��Ƥ����Ф����פȤ��������ä������ߤ����ηк�ȯŸ��ͽ¬���Ƥ����櫓�Ƕä��٤��踫�������ä�����2011/01/09�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ����ۼ��Ҳ����Τ����ޤ����������塡�� ����ǯ�ۤ��εܻ���ʤ��ʤäƤ���פ���������������ͳ������櫓�ǤϤʤ����ΣȣˤΡ֤椯ǯ����ǯ�פ��ˤ�����˿��Ƥ��ޤ��Τ��Ƕ�ι�����ä����������Ĥ��Ф�����ɾ��ǯ��ޤ������ȤˤʤäƤ��ޤä����������ܤ��軰�ζʤ���Ѥˤ��äơ�����ꥫ���ɤ��Ƥ���ΤǤϤʤ������Ȥ���������������ư���ˤʤäƤ��롣���ﹽ¤�ν���θ�˥���ꥫ�ϣ�������λ���������������ά�������Ȥ��й��˺����������������ˤ��ϰ�ʶ��ؤ��б��䥤�����ʸ���ؤ��й��Ȥ������Ȥ����뤬������ꥫ�������������롣���ե��˥����饤�饯������ˤϥ������ˤ������ꥫ����ά�Ǥ��롣��2011/01/06�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ�)��������Ū�ʤ��Τ�����ѱɡ�����ϴ�ν���Ϥ��ϰ�Ȥ���ֵ�ˤĤ��ơ������塡�� ����ͧ�ͤ����äƤ������Ǿ�����Ϻ�ȿ���ʸ���Υ饸�����̤��Ͽ������Τ����ä���������ǿ����Ͼ��������ܤ������Ȥϡֲ��ǥ���ꥫ�˶����Ƥ���Τ��פȤ������䤬���ä���������Ф��ƾ����ϡ֥���ꥫ�ε�����Ϥȥ���ꥫ�˽��äƤ���ȳڤ��Ȥ�����Ĥ�����ΤǤϤʤ����פ������Ƥ�������2011/01/04�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ�����ѱɤ�¸�ߤ����ƻפ��������塡�� �������뾮����ʡؤϤʤ����̿��١ˤ��ɤ�Ǥ������ḫ���夬��ʸ�ǡ����ȸ���������Ƥ���Ȥ������롣1960ǯ��¿�������ܿͤˤȤäƤ������������ä��פȽҤ٤Ƥ��������������к�ǯ��1960ǯ�ΰ���Ʈ�褫��50ǯ�ܤǤ��뤬���ͤϤ��ΤȤ����ȸ���������Ƥ����Τ������������Ϥɤ��ʤΤ��������Ȥ������䤬������ʨ���Ƥ��롣��2011/01/03�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ�������Ķ�����ȹ��ۤ����塡�� ������ǯƱ���褦�˥ܥ䤤�Ƥ���褦�ʤΤǤ��뤬�����ܤ���������ϩ�����äƤ��뤳�Ȥ�ï���ܤˤ����餫�����������Фϲ������������Ȥˤʤä��Τ��������ȤϤ����餫���Τफ�����Τ�Ϣ�椬���ޤ�ȤǤ��ä����ޥ���ǥ����䴱ν���ݼ����μ��͡����뤤�Ϥ����Ϣ�ʤä��μ��ͤʤɤ��Ѹ����������ƴط��μ��Τ��ˤ������Ƥ��뤬���������ڳ��Ǥ���п������Фʤɤ��Ȥᤳ�ޤ�Ƥ������볦���������褦�˸����Ƥ��뤫�⤷��ʤ�����2011/01/02�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ�ȿ�Ʊ���Ȥ���¸�ߡ������塡�� ������ʹ��������ǫ���ɤ�Ǥ��Ƥ�ʤ��ʤ������ʤ��������롣�������ܤȥ���ꥫ������Ū�ط��Ǥ��롣ɽ�̾�����ܤȥ���ꥫ����������ΩŪ�ط��Ȥ��Ƥ��뤬��������ǤϤʤ�������ꥫ�����ܤؤλ��ۤϻ��ۤȤ������֤��ظ�˱�������Τ�����Ǥ��롣���λ��ۤϻ���Ϫ�褹�뤳�Ȥ⤢�뤬�ʤ��ʤ��Ѥ�ߤ��ʤ��ΤǤ��ꡢ���ۤε��ۤ��ʤ����ۤȤ���¸�ߤ��Ƥ��롣����Ф����ˤ�������ܤ��������Ϥδ����ư���������ʤ����Ȥˤʤ롣��2010/12/31�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ��������������ƹ�Ρ������ʤ������������������弣 ����̱���ޤμ�Ǿ���Ρ������ȥ��͡���������ɲ��Ȥ���ư���Ƥ����ï���⤬�����äƤ���Τ��Ȥ����פ�������Τ��Ȼפ�������Ū��ɾ����ƻ��ü���ˤ��λ��֤ؤβ�Ω���θ�ư��褯��������褦�ˤʤä������Ǥ�������꤬�������濴Ū����ˤʤ�ΤȤ�����������������ˤ��������Ϥ������ˤ����Τ��������ʤ����Ȥ����뤫�⤷��ʤ���������Ϻ�ȿ�����β��̸�ˡֿ����꤬��ʬ�ȴ���Ū�ˤʤäƤ����פȤ��������δ��ۤϼ���Ū�Ǥ��롣��2010/12/27�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ����Ź�¤�Ȥ��Ƥι�Ȥȹ�̱���������ϡ������塡�� ������ʹ�ε�������̤����ɤ�Ǥ����Ф��������ʵ��������뤳�Ȥ˵����Ĥ������̤����֤ε����Ȥ������ȤʤΤ����������ʤ�ۤɤȻפ碌���Τ��鲿�Ǥ��줬�Ȼפ���ΤޤǤ��롣������ȸ��äư��̤ε����˰��ֶ�̣����������Ȥ������ȤǤϤʤ����Ф��ɤߤ����Ф��Ƥ��ޤ�����¿������ʹ���ɤ�Ǥ���ȼҲ��¿�Ͳ��ȳȻ��˵��Ť�������������Ū�˹�Ȥ�Ҳ���濴�ˤ��ꡢ�����Χ���Ƥ����Τ��ϽФ���Τ����Τ�ʬ���롣�Ǥ⡢��������Ͷ�Ǥˤ����뤳�Ȥ����ʤ������ߤΤ褦�ʾ���������濴�ˤ����ͤ��뤳�Ȥϲ�ǽ���Ȥ��������ޤߤʤ���Ǥ��롣��2010/12/20�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ���������������פǴ��������������弣 �����֤錄�������֤��줤���ä��Ȥ� �饸������ϥ��㥺����줿 �ر���ˤä����Τ褦�ˤ��餯�餷�ʤ��� �錄���ϰ۹�δŤ����ڤ�व�ܤä��סΡʰ��ڤΤ�ҡˡ�����ľ����ļ�Į������ȴ���륢��ꥫ���Υ����פ��ݤ��ä���ϩ�Ϥ˱���ƿ̤��Ƥ���̴���Ĥ����ˤߤ��������̴���ä��Τ������Ȥϸ�����ε������ä������Υ���ꥫʼ���饸�㥯�ʥ��դ���ä����������Ф����ܤ���������ϴ������������Ƥ������ۤ��褦�Ȥ���ư����ФƤ�������2010/12/15�� ���� 12��8�������ܤΡ��軰������ؤ�ü��סʣ��ˡ���ȷ���������ӽ����ظ�Τ��ä���Ρ������弣 �����ͤ�1941ǯ�����ޤ��������ǯ�����ܤϥ���ꥫ�ȳ��路�����ͤ�4�����ޤ������������Ϥʤ�������ˤĤ��Ƥε�����1945ǯ�Ȥ��������ζ����ʤɤ����˳Ф��Ƥ���˲�ʤ���1945ǯ8���̵������������Ǥ��ä����Ȥ�ï���ܤˤ⼫���Ǥ��롣�Х֥�������Ȥ��θ�Ρּ���줿10ǯ�פ����ܤ����������Ȥ����������ɬ���������ƤˤʤäƤ��복ǰ�Ǥ�ʤ������ݥԥ�顼�ʤ�ΤȤ���ή�̤��Ƥ�����դǤϤʤ��������������������ط��μ��פ��оݤǤ��ä�����ꥫ�Ȥδط���ɽ����ΤȤ��Ƥ����ƤǤ���Ȼפ����ͤ��������������ܤ���ߤ��軰������Ȥ������դǸƤӤ����������롣�軰�������ü�������ĤĤ���Ȥ������ȤǤ⤤���ΤǤ��뤬����2010/12/11�� ʸ�� �����˥��Ȥ��������塡�����ǰ�ä��ޥ�������������������¼�������� ������������ǯ����ä������������Ȥ���������ʤ����դ��郎������äƤ����Τϡ���������ꥫ��������Ǥ�ͭ̾���ä��Τϥܥ֡�����������������ླྀ�Ρ֥���ꥫ�ӡ��ȡפ�֥������С��������פ����ܤǤ�٥��ȥ��顼�ˤʤä����ޤ������ȡ��Хå�������ɤξ��ϡ�������Ƚ��١����ˤ��������礯�굤̣�Υ桼�⥢�������ä������������Хå�������ɤˤ���������Ű�˸��른�㡼�ʥꥹ�Ȥ��ܤ����ä�����������ή��������������Ȥ������ꥷ���ϤΥ����˥��Ȥ䡢���������ʺ����Υ�å��롦�٥������Ȥ����ͤ⤤�������������˥��ȤǤϥ������ॺ���쥹�ȥ�ߤ��ä��������㡼���������οɸ������Ȥ����Τ⤢�ä�������ǯ��ˤϤ������������˥��Ȥˤ�륳��ླྀ�����ܤǼ����Ƚ��Ǥ��줿����¼�������ˡ�2010/12/11�� ���ڡ���ǥ��� �ϥå����ȥ���� �����ϥå����Ȥ������դˤϥ����ȥ������뤤��ȿ��ȤΥ�������Ĥ��ޤȤ�����������������ϻϼԥ���ꥢ�������⸵�ϥå������Ȥ��������������ľ�ǯ����˥ϥå����Ǥʤ餷��������⤢��ͤ�������ˤ⡢���θ塢�ƹ��ɾʤ�������ƥ����ȤΥӥå��͡���ˤʤäƤ���͡������롣�ϥå����ϰ츫��ȿ�����Υ���ܥ�Τ褦����������ι�Ȥ������ȷ�ӤĤ������������롣�����ᤤ���ϥå����ѤϤ��θ塢���ɤ��������˻Ȥ���ΤǤ��롣��¼�������ˡ�2010/12/05�� ���ڡ���ǥ��� ����������������ۤϡ� ������������������ˤ�ä����ꤵ�줿�Ƴ���ʸ��ϣ��������ˤΤܤ롢�ȸ����롣���ˡ�����ꤷ��������Ť����̤˸�ɽ���뤳�Ȥ������ˤ褤���ȤʤΤ�������������������������̤ξ����������ꤹ�������ϰ��Τɤ��ˤ���Τ������������ܤ�������̩������ʤ��褦�ˤʤ뤳�Ȥ����ۤʤΤ�������Υ������Ū�Ϥɤ��ˤ���Τ�����¼�������ˡ�2010/12/02�� ���� �ʤ�����Ū������ž���˻��ߤ��������ά�����弣 ������ϩ���ɤ��ͤ���Ƥ���褦��̱���������Ǥ��뤬������ư�����ͤ餬��˾����ΤϤʤ�����Ū������ž���˻��ߤ�ʤ��Ȼפ������������μ�Ǿ�ؤ�����Ū�����Τ����������餯��Τ�����������άŪ���ۤ�ʤ�����ˤ��Τޤޤ��뤺��Ԥ���������Τ�����2010/11/23�� ���� �����λ������ñ�ʤ������μ�Ĺ����ǤϤʤ��������塡�� ��������Ȥ������դˤ�ΰ��Ȥ������դˤ������äΤ�Τ��ͤϴ����Ƥ��롣����̾���������������Ϥ��ޤ��������������Τ�����ɡ����β���ǤϺ����λ����������ʤ�Ǥ��롣��濿����ȥ��ϡʰ��ȡ˸���ΰ쵳�Ǥ��Ǥ��뤬���礷�������ˤ�����������롣��������Ǥϼ�̱�ޤȸ����ޤ���濿��ٻ�����̱�������ܤⱢ�Ǥϻٻ����Ƥ��롣�������濿����ŷ�ִ��Ϥθ������ߤ���ˤϤ��Ƥ��뤬�������Τ褦������ſ����Ϸ��ߤ���ǧ�ؤ�ž�������Ԥ���뤿��Ǥ��롣��2010/11/22�� ���� Ƭ���Ф��Ƥ��ޤ��Ф����ǤϤʤ����������塡�� ������Ƭ�ϱ��������뤬���ϽФ������äƤ���פʤ��ʸ���ҤͤäƤ���֤ˤ��ä��ȥ��Ĥ�������Ƥ��ޤä�����α�����ή�ФǤ��롣����ʤΤɤ��Ȥ������ǤϤʤ������Ĥδ֤ˤ��������������դ�����Ф��Ƥ�������ľФ��������Ƥ��뤦���˴��������ʤ��ʤäƤ�������Τ��Ȥ�����������Ȥ������Ĥޤ�ʤ����Ȥ��ڤ�Τƴ�����ʬ��Ф����ΤǤ��롣��2010/11/14�� ���� ����������פʤ���㲽���Ƥ���ΤǤϤʤ����������弣 ������������פϿ�ʹ����ƻ���Τä����餤�ʤΤǤ褯�狼��ʤ��Ȥ��������롣�����顢�����Ϥ�Ư�����뤷���ʤ���̱����¦���й���ư����ȯ�Ǥ��ä��餷�������Хޤ��о���ǽ�ˤ����֥����פ����ư�����ݼ�¦�˰ܹԤ������˸��������������פ��Ф���̱����¦���й���ư���������ʤ��ä����Ȥ��ͤζ�̣�Ϥޤ����롣̱���ޤ䥪�Хޤ������κ¤˽��������ζ���Ūư�������ĤƤΡ֥����פ�٤����ͤ����δ��Ԥ�˾�������Ǥ��������Ȥ������Ǥ��롣���ξ��˥��Хޤμ�ä��ɤΤ褦����������˾��Ͷ�ä����Ǥ��뤬���۵ޤηк��к��ʺ�����ư�ˤ�������١���ͻ���ٲ��פʤɤ������Ǥ��ä��Ȼפ��ʤ��������Ǥΰ���ζ�Ĵ�����������Ǥ��ä��Ȥ�פ�ʤ�����2010/11/08�� ʸ�� ���ե�����ѿȡפ���ȡ���������¼������ ������ع�Dz����Ȥ����ܤ����������ꤵ�졢����ʸ������������롣���ե��Ρ��ѿȡפϤ���������������ǺǤ�û���ܤΤҤȤĤǤ��ꡢ�ͤ��ɤ�����������롣����Ф��꤫���Ѥγ��Υ�����դˤ�Ȥ������Ǥ������Ȥ����Ǥ��ξ���μ���Ǥ��륰�졼���롦���ॶ���ѿȤ�����϶���Ū�˲����ä��Τ����Ȥ���ͭ̾���椬���롣��2010/11/01�� ���� ���������ܤ�ˡ����ȤǤ���Τ��������塡�� �������ο���ư��έ���Ȥ��Ф���Ρ��٥�ʿ�¾ޤμ�Ϳ��ᤰ�ä����椬�����äƤ��롣���ι��������������������Ƚ�Ȥ��ƤǤ��롣����������̱���ޤλ����Ĺ�����ϡ����ϰ������ٿͤǤ��ꡢ������������ʹѤ�ͭ���Ƥ��ʤ���ˡ��������̤�ʤ���Ǥ���ġפȽҤ٤�ʪ�Ĥ����������2010/10/17�� ���� ������衢̱�����Ԥ����Ȥ���Ф��Ȱ�����������弣 ���������Ȥ�ᤶ���Ƥ���������Ϻ�ˤȤäƤ�����ǯ��ʤ������Ƿޤ��뤳�Ȥ����ܰդʤ��ȤǤ��뤫�⤷��ʤ��������ˤϻդǤ��ä�����ѱɤΤ��Ȥ����褷�Ƥ���������Ǥ��롣�ͤ����������ˡ�װ�ȿ��ᤰ�����ε��뤬����������Ǥζ������ʤεķ�˻�ä���������ѱɤκǸ��פ���������������Ϸ褷�ư���������Ȥ��ƤǤϤʤ�����2010/10/08�� ���� ���������ᤰ����ư�����۵����뤳�ȡ������弣 ������桼������ӥ�������Ȥ���̱²Ū������Ūʶ�褬�ϰ�ʶ��ȸƤФ�������ȯŸ�����Τ������衼���åѤǤϰ�����E�աʥ衼���åѶ�Ʊ�Ρˤ���Ÿ���Ƥ���Τˤ���Ϥʤ���Ȼפä����衼���åѤǤϹ�Ȥ�Ķ���ƶ�Ʊ�Τ�Ÿ�����Ƥ���Τˤ������Ȥ����٤��Ȥ����Ǥ�̱²ʶ��Ȥ����٤����褬�����äƤ���Τ�����ä��Τ��������Ƥ�����ƻ�ʤ��顢�쥢�����ǤϤ����������꤬��褵�줺�˻ĤäƤ���Τ��Ȼפä����ţդ��ǥ�ˤ����쥢������Ʊ�Τδ��פϳμ¤˳��礷�ʤ��顢̱²����Ω������ϲ�ä��줺�ˤ���Τ��Ȼפ����Τ��ä����ͤϺ��٤�����������դγ���Ǥ�����ҵ�����������狼����������ư�Ǥ��Τ��Ȥ��۵���������2010/10/05�� ���� ���ξ�����������ȤȤ���������ν��֤ϰ㤦�������弣 ��������������դγ���Ǥ�����ҵ��������������Ф����������ܤ��б��������Ǥ��롣�츫�����ζ��ź��˲����ڤ����ڤ�ΰ�����������ˤ��Ƥ⡢��γ��礬���ﲽ�������֤���ǤϤ��������äƤν��֤Ȥ������Ȥˤʤ롣��������˼Ĺ�������餬�����ϸ��ΤȤä����֤Ǥ��ꡢ��ʬ�β�����Ƚ�ǤǤʤ����Τ褦�˿��Τϵ��ˤ���ʤ������ڤ��ǥ����������������Ƚ����뤳�Ȥ���������������������ϸ��ν��֤�ǧ����Ȥ���������Ƚ�ǤǤ⤢��Ȥ����٤��Ǥ��롣������������ɤκ����ˤ��������ޤʤɤ��б��������Ǥ��롣�����Ф뤳�Ȥ��ٻ�������Ȥ����ΤϺ��ФǤ����2010/09/28�� ���� Ϫ�褹�븡����������Τι�¤�������塡�� ���������ٰ��Ѥ�ʸ��¤����ʵ���ͭ����ʸ�������Ʊ�Իȡˤ�����Ƥ�������ϫƯ�ʤθ���Ĺ��¼�ڸ��������Ф�������Ϻۤ�̵�������Ϥ��������κ�Ƚ�˴ؤ��Ƥϸ���¦�Τ�������ܺ������������Ŧ����Ƥ��ꡢ̵��Ƚ���ͽ�ۤ���Ƥ����������٤ϸ����ˤ��ڵ�β�����Ȥ�������٤����֤�Ϫ�褷��������ϸ����Ȥ��������ƥ�λ�������Ǥ��롣��2010/09/23�� ��˲��Ҳ���䤦 ����Ĺ����ȡ���ή�� �����Dz�ɾ���Ȥ�����Ĺ�������ǯ������ʤ��Ȥ�Dz���ǯ���⤤�Ƥ������ֱDz���Ĥ˸����Ƥ���Τ϶��ϤȤ������ٹ�νпȼԤǤ�����ʬ��������֤��Ȼפ��ͤϡ��ռ����Ƽ�ʬ����ή���鳰���Ƥߤ����Ϥ�ɬ�פǤ��ס�2010/09/23�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�(���˹�̱�ΰո���ռ��ˤ���Ū�ʺ��ۤ����������Ĵ���ˤ�����̱�դȸ��¤�ЪΥ�˴�Ϣ���ơݡ������弣 ��������ǥ���������Ĵ���ʤ��Τ������ʻ�̱���̱�θ��¤ΰջפ�ռ��ˤ�Ĵ����̤ǤϤʤ��������Ȥ��ƺ��Ф��줿��ΤǤ��������Ҥ٤������Ф��줿�Ȥ������դˤ�ͶƳ���줿�Ȥ�����̣�ϴޤޤ�Ƥ��뤬����٤��줿�굶¤����ꤷ�ƽ��褿�����Ȥ�����̣�ǤϤʤ���̱�դȸƤФ�븽�¤������Ȥ�ЪΥ�Τ����Τ��Ȥ�������Ŭ�ڤ��⤷��ʤ�������Ĵ���ʤ��Τ뤿�Ӥˤɤ����㤦�����������㤦������Ǥ��������ʤ�ΤϤ���ЪΥ�����餯���Τ��Ȼפ������������ι�¤�Ϥʤ��ʤ��ϽФ��ˤ������ͤ餬�´����Ƥ��������Ȥ�ЪΥ���Ƥ���Ȼפ��Ƥ⡢�����������ɤΤ褦�ʴ��פȤ��Ƥ��ꡢ��������Ƥ���Τ����Ĥޤ�������ι�¤�ˤ���Τ��Ĥ��ߤŤ餤����Ǥ��롣��2010/09/20�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�ʣ��ˡ����פʤΤ�������ƴط��θ�ľ���ʤΤ����������弣 ����̱���ޤ���ɽ���Ͽ��ξ����ǽ���ä�������Ϥ�������ͽ¬�Ǥ������Ȥ����ް��䥵�ݡ�����ɼ��������������Ȥ�ͽ�۳��Ǥ��ä���������������äǤ��뤳�Ȥ�ޥ���ǥ�����ͭ��̵���λٱ礬�����դ����Τ��Ȼפ�����̤ϱ��ߤä��ϸǤޤ�ˤʤ뤫���������ԤλϤޤ�ˤʤ뤫��ͽ¬�Ǥ��ʤ���������ɽ�����̤����ͤ����Ԥ��Ƥ����ΤϿ��Ⱦ�����ξ�����Ū�����ȹ��ۤ����Τˤ��������Ÿ�����Ƥ���뤳�Ȥ��ä�����2010/09/15�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�ʣ��ˡ�����Ĵ���Ȥ�����Ʊ���ۡ����弣 �����㤤�����˿�ʹ���Ԥˤ������줿�ͤϾ��ʤ��ʤ��Ϥ��Ǥ��롣�ͤ⤽���פäƤ��������Ʊ�����ǿ�ʹ���Ԥ䥸�㡼�ʥꥹ�Ȥˤʤä��Τϰճ��˾��ʤ��ʤ��Τ��ä��ʤΤ���������˰��٤Ϥ����������ä��ͤ�¿���ä��ΤǤϤʤ����Ȼפ������줬�Ҳ�������Ӥ���Ż��Ǥ��롢���뤤�ϼ�ͳ�ʻŻ��Ǥ���Ȥ����Τ����ۤȤ��Ƥ��ä�����Ǥ���ȿ仡����롣��ǥ����ؤΤ����������ۤϤȤ����Τˤʤ��ʤäƤ���Τ���������ˤ��Ƥ�ޥ���ǥ��������Υ�ǥ����ˤΤ���褦�ˤϼ���뤳�Ȥ�¿�����ޥ���ǥ��������������ؤαƶ��Ϥ�̵��Ǥ��ʤ������ˤ����פ���ΤǤ��롣��2010/09/14�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�ʣ��˱��Ż˴ѤϹ�������ʤ����ɡ������弣 �����ͤϱ��Ż˴ѤȤ�����ΤϹ����ǤϤʤ������������Ťȷ���դ��������뤳�Ȥ��Ƥ�����������������ˤϵ�̩�Ȥ���̾�ˤ����Ʊ����줿��ʬ�����ꡢ̩��ʤɤ��㤬����褦�ˡ������ʤ��Ȥ����ǽ���ʤ��Ȥ����Ф�뤳�Ȥ��ΤäƤ��롣�����Ƥ��������Ū�Ϥ�����Ū���������Ȥϴط��Τʤ��Ȥ�����Ư�����Ȥ����롣�ط��Τʤ�������ư������Ū�ޤߤ���ä���ư�Ǥ��뤳�Ȥ��������롣�����Ǥ������Ϥ�Ư�����뤳�Ȥ����פǤ����2010/09/12�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�ʣ��ˡ���Ũ�ɤ���Ȥ��ɤȡ������ȶ�ס������弣 �����־�����Ϻ�İ���ٱ礹���פȤ����Τ����ꡢ�ͤ����ÿͤΰ�ͤ�̾��Ϣ�ͤƤ���9��3���ˤ���äȤ�������ݥ�������ä�������ϸ������IJ���Ф��뵿ǰ��Ƥ�����������Ф�����˽������Ƥ����Τ�����̱���ޤ���ɽ����Ȥ������Ȥ⤢�ä��������ä����ͤ�Ϥ��δ֤θ����Τ���褦����Ƚ���Ƥ��������������ɽ����Ǥ�����Ȥ��ơ������ȥ��͡פΤ��Ȥ�����ˤʤäƤ���ΤǤ��Τ��Ȥ�⤦�����Ҥ٤��֤���������2010/09/07�� ���� ���ߤ��Ф��븫���ȹ��ۤ�ʣ���ȷ�����ͤ�ư��������Τϲ����������弣 �����Խ�������������Ǯ����ʤɽ뤵��魯���դ��ƥ�ӤΥ��㥹��������ʹ�����Ƥ��롣����ʤ齩�ε��ۤ���������������������Ϥʤ���̱����Ǿ�ˤϰ���˽�������Ϥ�Ƥ���Τ����������������夫���ǯ�����Ф��ʤ��Τ���ɽ����Ȥ����櫓�����Ǥ⡢�Ϥ��ޤä��Τ�������������Ū�����ȹ��ۤ����Ƥˤ��ƻٻ������뤷������ޤ����ͤϾ�����Ϻ��ٻ���������˴�ʬ���δ��ԤƤ��롣������ͳ�ˤĤ��ƤϤ�����ɾ����Ǥ����餫�ˤ���������2010/09/06�� ��ؤ˺�ĩ�����������������¼������ ��ǯ���������ǥ亮��ȥ�DC�ٳ��Υۥƥ�˽��ޤ��������λ������������Τϥۥƥ�Υ����åդ��ݽ��Τ��Ф��顢�쥹�ȥ��Υ����ա���š��ե���Ȥޤǡ��ۤ��������ڥ��������Ȥ���͡����ä����ȤǤ�������¿���ϥ��륵��Хɥ�ʤɡ������Ƥ���Ư������Ƥ���͡��Ǥ����������ǡ������פ虜��ޤ���Ǥ������֤��ȣ���ǯ�⤷���顢���ڥ���줬�Ǥ��ʤ��ä��饢��ꥫ�μ������ʤ���������������ס�2010/08/17�� �ܥ�ͥ��礫��μ�桡����¼ůϺ�ƥ����� ����¼��ռ��Ρؤͤ��ޤ�Ļ�����˥���٤˸�ʼ�Τ������֤���̤����롣�شֵ���Ӥ�Ĺ���á٤���������˼��Τ褦�ʰ�����롣�ظζ������Ϥ��뤿��ʤ顢����ä�̿��ΤƤƤ��襤�ޤ�������������ʹ�ʪ�ҤȤİ餿�ʤ��Ӥ줿���ϤΤ���ˤҤȤĤ����ʤ�̿��ΤƤ�ʤ�Ƥޤä����ϼ��������ȤǤ����١�¼��ռ����ͤ��ޤ�Ļ�����˥����ʸ���ǡˡ��裱�����У������ˡ����饯�ˤ�����ǯ������Ϥ��θ�ʼ�Τθ��դΰ�̣���Τä�����2010/08/15�� ���Ƥ���ζ���������������������¼������ �����ɥ��Ŀͤ�������������θ����������ˤĤ��ƥɥ��Ĥκ�ȣס�G�������Х�ȡ�1944-2001�ˤ������ޤ���ͭ�ͤ�Ƥ��ޤ�����1943ǯ���ơ�Ĺ�Ӥ��Խ�Τ��ʤ��ˡ������ꥹ�����ϱ���Υ���ꥫ��Ȭ�����ȤȤ�˥ϥ�֥륯��Ϣ³���⤷�����㥴�������ȾΤ���������ɸ�ϡ��Գ���ڤ֤����괰�������Ǥ����������˵�������뤳�Ȥ��ä����ס�2010/07/08�� ���� ��ؤ˺�ĩ�������������¼������ ������֡�Ķ�ץե������פ��˼�ä��Ȥ��δ�ư�ȿ̤��Ϻ��Ǥ�פ��Ф��ޤ������Ԥ�����������ض��������������ᡣ�ͤ������ܤ������˴�ư�����ΤϤ��褽�������ڡ�������Τ鷺�����ڡ����Ǥ���������Ϥ����ʸ�ϤǤ����֣塡�ǽ���äƤ���ñ���¿���Ͻ����ǡ�����ʳ����������Ȥ������Ȥ��狼��Ǥ��礦���ס�2010/07/02�� �Ҳ�ʳؼԡ��������Ȥ˺��ؤ֤��ȡ���ư�Ρ־��¡פ�����ȴ�����������¸���ͺ �����衼���åѶ���ηкѻ��ۤ˳ؤӤĤġ���ư�Ρ־��¡פ�����ȴ���ơ������ȼ��μҲ�ʳؤι��ۤ����������Ҳ�ʳؼԡ��������Ȥ˺����䤵�줿�����β桹���ؤ֤٤����ȤϾ��ʤ��ʤ��������˰�Ӥ��Ƥ���Τϡ���ȸ��Ϥˤ���ʤ����ȽŪ�ʻ������³���������ȤǤ��롣��Ĥζ�������������Ĥϡ���������桢�пس��̤˸����äơ������Ƶ��äƤ����פ���ޤ��������η�ʤ�������ˤ�������֡־Q�פ�����������Ѥ��褦�ȤϤ��ʤ��ä�������ȿ���Ϥλ����Ϻ��Υơ��ޤ���������С�ȿ�����ư��ݡפ��̤���ΤǤϤʤ�������2010/06/26�� ���� �����ࡦ�ե������۸��Ĥλפ��С���¼������ ���������ࡦ�ե����ޤ������Ƥ������������������ȡ����ǤϤ⤦���ä��ΤΤ��ȤΤ褦�˻פ��ޤ��������뤭�ä����ǥ����ࡦ�ե�������۸�����۸��Ĥμ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ��������饯�������ǯ����������ǯ�βƤΤ��ȤǾ��ϥ�����μ��ԥ���ޥ�Ǥ�����2010/06/25�� ���졿���ư��� ����δ��������ꥫ�˳ؤ֡����������ȡ��ޥ����ڥ���Ȥ�����������������¼������ �������ϵ��˥���ꥫ�ۤɹ�ʡ�β�ǽ��������Ϥʤ�������ꥫ�ΰ��֤ϡ�ʶ����䤨�ʤ��������鴰���˳�Υ����Ƥ��롣����ꥫ�������ι�ȴط�����ĤΤϡ������ǰפ��������סʥȡ��ޥ����ڥ������֥���ꥫ�δ����ס˺���������ɤ�ȡ����Ρ��ɤ��Υ���ꥫ�Τ��Ȥ����Ȼפ��Ǥ��礦����2010/06/15�� ����δ��������ꥫ�˳ؤ֡���������¼������ ������δ��Ϥΰ�������ä��������ư��ݾ��������ˤĤ��Ƶ�ʤɤǰ��̿ͤ�����������Ƥ��롢�Ȥ����Ƥ��ޤ������饯�Ǥϥ��饯����夹�Ǥ˼縢�ܾ����ʤ��줿�Τ���壶��ǯ��ФƤ�̤�����ܤϥ���ꥫ��°��ʤΤǤϤʤ�����������ܤ꤬���κ���ˤ���褦�Ǥ��������������⤽�⥢��ꥫ�ͤϤ��η�����衢��ͳ�Ȥ���Ω��ŤƤ����ΤǤϡ�����ʤ��Ȥ�ͤ������������ܤ˽вޤ������ȡ��ޥ����ڥ����Thomas Pai��1737-1809�ˤΡ֥������(Common Sense)�פǤ��������ܤ���Ω������Ф��줿��������ǯ�˴��Ԥ��졢����ꥫ�Ƕ����Υ٥��ȥ��顼�ˤʤä������Ǥ�����2010/06/10�� �ż֤���ǡ�������¼������ ����λ�Ŵ�ż֤˾�äƤ��ƥҥ�äȤ����ޤ������ɥ����Ĥޤ�ݤˤ�ǯ��꤬���;�����Ǥ��ޤ��������Ȥ�̵��������ޤ��������ɥ��˶��ޤäƤ��ޤä��ΤǤ�����οͤ������äƤ��ξ��������⤦�Ȥ��ޤ����������Ϥ����ʤ����ż֤Ͼ��Ϥ�����ޤ�����Ф��Ƥ��ޤ��ޤ����������γ��˾��ʤ��Ȥ⣵�����������������餤���ͤ��Ф��Ƥ��ޤ�������2010/06/03�� �Ҳ� ������ĩ��ˤ��Ƥ�����Ǯ�������ͥ��ͳ��������Ρ��Ľա١��¸���ͺ ������ǥ�����������Ȥ����ˤ��ȡ��ԣ£ӷϥƥ�ӥɥ�ޡֿ�Ͳ���פǽ�Ǧ�ԤȤ��Ƴ���������ͥ��ͳ�������뤬��쥮��顼�����ह�롣��ǯ������˴���ʣ����Сˤ�ޤ���Ȥ�������������������൭�Բǡ������Ľդ��ͤ����äƤ��������פȤߤ��ߤ������ƻѤ���ݤŤ���������ˤȤä��ĽդȤϡ֥�����ĩ��ˤ��Ƥ�����Ǯ�פ������ǡ����������������ˤ��礤�ˤ��䤫�ꤿ������˾�Ф��ˤ������Σ���������Ƭ�ˤ��äơ��Ľա����ʤ��������ĩ��ˤȤϤɤ��������������ư��������ʤΤ�����ͤ��Ƥߤ�������2010/05/10�� �ͤ����䤹���Ų��פȷ��顡�������Ԥ�é���夤���ۤ����ȡ��¸���ͺ ��������Ԥ��̤���Τ����Ȥ�����Ƚ���������Ƥ��롢���θ������Ԥ˻伫�Ȥ�Ĥ���é���夤������Ϥ�ʤˤ������δ�����Ф��롣��ǯ���塢�¼�˶줷����θ�����ˤϿͰ��ܴؿ�������������ԤˤʤäƤ�ʤ���ݻ����뤿��ˤϲ���ɬ�פ����ܿͤο������Ȥ�����̣�Ǥμ�����Ǥ�Ϥ���������������ޤǤȤϰۼ��ΰ��Ų��פȷ��餬�Բķ�Ǥ��롣���Ų��פǤϷݻ������Ϥ��Ƥ���Ԥ������ַ��ݸ����ΰ����ִ����Ḣ�פο��ߡ�����������Ǥϡ֤��Τ��ȿ��ȷפΤ������̰��μ���ª���ƾ������κ����鶵�餷���������뤳�ȡ��ʤɤ���Ƥ�������������¿ͤ餷���ͤ����䤹���Ų��ס�����ˤۤ��ʤ�ʤ�����2010/03/13�� ���ȿ� ¼�ˤ��ϲ��夬ή��Ƥ��롡�������¶� ������������ڤ꤬�������ʤ��ȵ��ˤ��ʤ���ܤ���ȥƥ�Ӥα�����Ѥ�į��롣���Ԥ������Ȳ��̤˸��졢�������Ԥˤ��������Ϥ��ƾä��Ƥ�������2010/01/01�� �Ҳ� ��ʸ�ֿʲ�������ڡפ�����˴��ԡ���꤬��֤��餳����ʬ��ڤ������¸���ͺ ������ʹ���Ϥ褯�ɤ�褦�ˤ��Ƥ��뤬���Ƕ�ϴ����Ȥ������ʡ���Ȳ�Ȥ����θ��ʤɤ�ĤŤ������Ω�ġ����¤���������Ǥ�ϩ����⤤�Ƥ��ơ����뤤���ż֤�����褤����˽�ʻ����˽в��Ȥ��������ʤ���ͭ���Τˤ����С������طʤˤ���þ�����Ϥ��Τ��ο���ͳ����ʡἫͳ�Ծ츶�������ϩ���λıƤ���ǻ���⤭�ФƤ��롣�����������褤�α��������λ������������ɤ����뼫ʬ�̤ܰλ�������Ω�ĤΤǤ��롣�������ߤ�����˾���ʤ��櫓�ǤϤʤ����־����ʿ��ڡ�ʸ������ǽ�������������ޤ����ֿʲ�������ڡפϸ��äƤ��롣��2009/11/23�� �Ҳ� ��Ƚ����Ƚ����äѤꡢ�ۤ����Ӥ��Ф����������ܹ�ͺ �����Ų��Ϻ��;������ˤ����ơ������ν��������������Сˤ������Ȥ��ơ����ͺ�ʤɤ����줿̵�������Ĺ������ʣ����Сˤκ�Ƚ����Ƚ�ǡ������������Ƚ���˵��Բ�����Ƚ���������������ƤӺ�Ƚ�������Ф�뤳�Ȥ��������������ͤϡֽ��פʤȤ����Ϻ�Ƚ���ΰո���ȿ�Ǥ���ʤ��ä��ȴ�����פ�ɾ�Ĥοʤ�����������Ҥ٤������������ʾٻش����Ф������������Ĥ��ФƤ����������ͽ�ۤ���Ƥ��������줫�餬��Ƚ����Ƚ����ǰ�������2009/11/07�� ʸ�� �����ꥹ�� ��ۤ��Żҽ��Ҥ�ڤ���� �������Ӷ��� �� �ѹ�Τ����Ĥ��ο�ۤǤ�̵�����Żҽ��Ҥ�ڤ�뤳�Ȥ��Ǥ��롣���η�̡���ۤ����ѼԤ������Ƥ���Ȥ������ޤ������Υ����ӥ��������ϸ��ο�ۤ�̾������Ͽ������ۤΥ��С��Ȥʤ롣�����Ǥ��뤤�ϼ���ǡ����ο�ۤΥ����֥����Ȥ˥�������������ʬ�Υ��С���Ͽ�ο��������Ϥ��롣����ȡ������Żҽ��Ҥ�ԥ塼�����˥���������ɤǤ���褦�ˤʤäƤ��롣��2009/10/30�� �ԥ����ʥ���ʥ�إ��ɥȥ�ӥ塼������Ҥ����աʣ��ˡ��������ȴ���������ʿ�¤Ϥ��ꤨ�ʤ����⤯������㡼����������䡡��¼������  ���������ʥ���ʥ�إ��ɥȥ�ӥ塼��ʰʲ��إ�ȥ�ˤϹ��Ū�ʱƶ��Ϥ���ĥ˥塼�衼�������ॺ�����ι�ݻ�Ǥ������ܤǤ�����������ߤ�����Ƥ��ޤ����إ�ȥ�ˤ��Խ����������⤬���Ĥȡ���ƼԤˤ�륳��ࡦ���⤬���Ĥۤ������Ǻܤ���Ƥ��ޤ������줫�����ˤ錄�äơ�����Ͱ�ͤλ��ۡ�������ץ��ե����롢�����ƥХå����饦��ɤʤɤ˾����Ǥ����äƤ�����ФȻפ��ޤ�����1��ϡ�Roger Cohen���ʥ����㡼����������ˡ���������ϺǶ�����Ū�˼�ɮ���Ƥ��륳���˥��ȤǤ����ä˥����γ˳�ȯ����ˤ���ॳ����¿���Ƥ��ޤ��������ˤϤ��Ӥ��ӽФ����Ƽ���ԤäƤ���餷��������������������Υǥ⸽��ˤ��Ĥ��Ƥ��ޤ�����������ϥ����˰����������������ζ��Ϥ�ƥ��������ʿ�¤��Ǥ����Ƥ褦�ȹͤ��Ƥ���褦�Ǥ�����2009/08/10��
���������ʥ���ʥ�إ��ɥȥ�ӥ塼��ʰʲ��إ�ȥ�ˤϹ��Ū�ʱƶ��Ϥ���ĥ˥塼�衼�������ॺ�����ι�ݻ�Ǥ������ܤǤ�����������ߤ�����Ƥ��ޤ����إ�ȥ�ˤ��Խ����������⤬���Ĥȡ���ƼԤˤ�륳��ࡦ���⤬���Ĥۤ������Ǻܤ���Ƥ��ޤ������줫�����ˤ錄�äơ�����Ͱ�ͤλ��ۡ�������ץ��ե����롢�����ƥХå����饦��ɤʤɤ˾����Ǥ����äƤ�����ФȻפ��ޤ�����1��ϡ�Roger Cohen���ʥ����㡼����������ˡ���������ϺǶ�����Ū�˼�ɮ���Ƥ��륳���˥��ȤǤ����ä˥����γ˳�ȯ����ˤ���ॳ����¿���Ƥ��ޤ��������ˤϤ��Ӥ��ӽФ����Ƽ���ԤäƤ���餷��������������������Υǥ⸽��ˤ��Ĥ��Ƥ��ޤ�����������ϥ����˰����������������ζ��Ϥ�ƥ��������ʿ�¤��Ǥ����Ƥ褦�ȹͤ��Ƥ���褦�Ǥ�����2009/08/10��
ʸ�� �������ܥ��뤵��ؤβ����ƻ����ͤ��륹�ȥ�ȥ�����㡼 ��2009/06/10�� �������ȥ�ꥢα�إե������Ĥ����ȸ���������  ��������������顢���ܹ���Σ��ԻԤǥ������ȥ�ꥢ���ܼ�ŤΥ������ȥ�ꥢα�إե������Ԥ��롣�������ȥ�ꥢ�϶������Ȥ��Ƽ����������Ǥ��ꡢ�����ƹ��α��������ؤʤɤdzؤ�Ǥ��롣��ʸ�ȼ̿�����¼ůϺ�ƥ������ˡ�2009/05/26��
��������������顢���ܹ���Σ��ԻԤǥ������ȥ�ꥢ���ܼ�ŤΥ������ȥ�ꥢα�إե������Ԥ��롣�������ȥ�ꥢ�϶������Ȥ��Ƽ����������Ǥ��ꡢ�����ƹ��α��������ؤʤɤdzؤ�Ǥ��롣��ʸ�ȼ̿�����¼ůϺ�ƥ������ˡ�2009/05/26��
�ڥåȤȤ��̤� �� ���Τ��ȴ��ա��¸���ͺ �����פ��֤�˲�ä��������夫���ͧ��A���⤫�̴�Ƥ��롣ʹ���Ƥߤ�ȡ��ֶ�����餷�Ƥ����ڥåȤΥͥ����Ƕᤢ������ιΩ�ä������������μ��촶�ˤȤ�Ĥ���Ƥ���פȶ�������������Ƥ��줿���ڥåȤȤ���餷�ˤĤ����ब��ä��Ȥ�����Ҳ𤷤褦����2009/01/10�� ����ξ�˻פ� �� ��˽�ϡ�ʿ�¡��¸���ͺ �����οͤ����彨�ˤ���ʲ��Τ褦�ʣ���/������Υ�å������ֽ���ξ�˻פ��פ��Ϥ������� ��Ǻ���ä˱�ǰ�ˤĤ��ƻפ����餷�Ƥߤޤ����פȤ��롣���夵�������å������������Ƥ��뤬���ֽ���ξ�˻פ��פ�ǯ��ǯ�Ϥˤդ��路�����ƤʤΤǡ��������פ�Ҳ𤷡������˻�ʰ¸��ˤδ��ۤ�Ҥ٤롣��2008/12/29�� �ڥ����ۻ����Τ������ܡפ�ͤ��롡�������ʤ��Ȥ�����ͳ�⤢�뤬�� ������ǯ������������٥�ˡ���뤹�����ܿͤ��Ф����������ȥ�ꥢ���ܤ�����μ���̳�դ������ˤ����餫�ˤ����פȤ�����ݤΥ����ץ��ա��뵭����Ф�����������Ф��������ͥåȾ�Τ����Ĥ������ܸ쥵���ȤǤϡ����硼�������˴��㤤����¿���μԤ��ַ��봶��פ�ɽ�����ֻ����Τ�ʤɵ����ʤ��ס֥������ȥ�ꥢ�ˤ����Ф˹Ԥ��ʤ��פʤɤΥ����Ȥ�¿�����Ƥ����������������Υ����Ȥ���ˡ��������ܤ�����ͤ��Ф�����μ���̳�Ť��Ƥ�����¤��Ŧ�����ո��ϳ�̵���������ä�������Ⱦ�Фޤǣ�ǯȾ�֤�����ܤ�ˬ�줿ɮ�Ԥ⡢��������κݤ˻�������Ƥ��롣�ʹ륢�ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2008/11/28�� �ʹ�����������������ߥ�̵���̻��͡����֥ץ饤�������˸��뵬���ʤ��Ҳ�δ����� ������ˡְ������������衿����ͳ����ȥ������ѥ��פʤ뵭���������٥2008.07.17�ˤǡ��ʹ��������⤷�ĤĤ���褦���Ȥ������Ȥ�Ҥ٤����桹������������ϡ��ʹ֤�����Ū�ˤϡ����פ�Ԥ����������Ȥ�����Ȥ��ƱĤޤ�Ƥ��롣�㤨�С����̤��и������μ֤Ϥ���������ӽФ��Ƥ��뤳�ȤϤʤ������������߿�ο帻���Ǥ������褦�ʿʹ֤Ϥ��ʤ����������ʤɤʤɡ����������������Ǥ��ʤ��Ȥ���ȡ����������϶��������ƻ������ʤ��Ǥ������������������Ͻ��褽����ʤ�����ǰ�ʤ��Ȥˤϡ��������������ޤ�θǤȤ�����ΤȤ��Ʋ���Ǥ��ʤ��褦�ʻ��ݤ��Ƕ�������������Ƥ��롣���ߥ����ơ����ո��Ǥ�̵���̻��ͤʤɤʤɡ��ʥХ��С������ɰ�Ϻ�ˡ�2008/10/09�� ���ư����������Τ�������롡���ݸ�����ܤ�ɤ��ۤ������¸���ͺ ���������������ʿ�¤�ɤ��Ĥ��äƤ������פ�ơ��ޤ˹��ä��뵡���ä������ι��äδ��ܤϡ����ư����������Τ�������롽���ݸ�����ܤ�ɤ��ۤ����פǤ��롣���ư��������Ϸ������кѣ��Ĥ�Ʊ��������ȤʤäƤ��ꡢ��������Ʊ�����ֽ����κ����פȤ⤤���٤�¸�ߤȤʤäƤ��롣�����̤Ǥ�����������Ʒ��νз���Ϥˤʤäơ�������ʿ�¤��˲����Ƥ��ꡢ�������к��̤ǤϻԾ츶�����ϩ���ˤ�뤤�Τ��ڻ롢�Ϻ����ʺ�������������������ʤ�äƤ��롣�������¿���ι�̱�ˤȤäƤϵ���ʡ���θ��̡פǤ��ꡢ���θ��������ư��������Ǥ��롣��2008/09/20�� �⤷�䤬����������Ф줿�顡���λ��Ρֽ꿮ɽ���פ���ȡ��¸���ͺ ���������ȥ�Ρֻ䤬����������Ф줿��פλ�Ȥϡ���ʰ¸��ˤȤ�������ष��¿���ι�̱��ͤҤȤ��ؤ��Ƥ��롣���λ�ο��ˤ��������ؤδ��ԡ�����˾�������Ƥߤ롣��̱���������塢�����ۤ��������Ƭ�ǿ���������Ф��Τϴְ㤤�ʤ����������꿮ɽ������θ塢��������ˤʤ�ΤǤ���С����ν꿮ɽ������Ȥ�����������ι�������륫���ˤʤ�ΤǤϤʤ�����������Ȥϻ䤿���δ��Ԥ��˾�˽�ʬ�������Τˤʤ�Τ��ɤ��������������ɤ����Ǥ��롣��2008/09/10�� �ְ�¸������æ�Ф���ˤϡ�ƶ��Х��ߥåȸ�����������ܡ��¸���ͺ�������� ������ϣ���ǯ������������ƶ��Х��ߥåȸ�����������ܡפȤ����ơ��ޤǹ��ä��뵡���ä������ϥ����ȡ������ȡ����ä�ڤ���뾮���϶��֤Ȥ��ƿ͵���Ƥ�Ǥ��륮���&���ե���space�������סʹ��縩ʡ������Į��ʿ�����ɽ�ˤǡ��֤ǣ���ʬ�⤫��������϶�ʤɤ�����̾�����礷�����ϵ岹�Ȳ����ɤ�����ΰ�ĤȤ��ơ����٤˼֡ʥޥ������ˤ˰�¸�����ְ�¸������ɤ�æ�Ф������פ��Ƥ��������濴�ơ��ޤȤʤä�����2008/09/05�� ���ܽ�ƻ�ϡ�ƻ�פä��Τ������Ǿ��Υ����������طʡ��¸���ͺ ����������ʹ���ý��磻����ʣ���ǯ�������ͼ��������ǡˤǡָ��ؤ����ܽ�ƻ�פ��ꤹ��ơ��ޤ���夲�Ƥ��롣�̵����ؤǡ��˽���碌�Ʋ��Ǿ��Υ������������ġʶ⣴���䣱��Ƽ���ˤ˽���ä����ܽ�ƻ�����ܽ�ƻ�Ͼä����֣ʣգģϡפ��ʴ�����Ƥ��ޤ��Τ� �� �Ȥ��������������Ȥޤ줿�ý��Ǥ��롣���ܽ�ƻ�����ƻ�פ������������Ƥ����Ȼ�Ŧ����Ƥ��ꡢ��������Ȥ�����¿��������ϸ�����ɤ������뤫�Ȥ����������Ǥ⤢��ΤǾҲ𤷤�������2008/08/27�� �������������衿����ͳ����ȥ������ѥ��������֥å���ϰ��㡢����ʡ��ɿ��פ����� �����ʹ֤ϡ�����Ū�ˡ����פǤ��롢����ְ��פǤ���Ȥ��������Ϥ��ĤޤǤ���ʤ��褦�Ǥ��롣���ꥹ�ȶ��Ǥϡ��ʹ֤����ޤ�ʤ���ˤ��ơֺ�פ�����äƤ���ʸ����⡨���ʤ������������ˤȤ��Ƥ��뤷������ʸ���Ǥϡ��ɤ��餫�ȸ����С��������⤬�������Ƥ���褦�Ǥ��롣�����¿ʬ��ʩ���αƶ��ˤ���Τ��⤷��ʤ���ʩ���Ǥϡ��ʹ֤ˤϡֶȡפ����뤬�����줫���æ���뤳�Ȥϲ�ǽ�Ǥ��롨���ʤ���������פǤϤ��뤬�������Ȥ��פ��Ȥ��롣�ʥХ��С������ɰ�Ϻ�ˡ�2008/07/17�� �����ģ��������ģ�ο��ߤ�����ԡפ������ô������ء��¸���ͺ ����ʡ�Ĺ�����μ�Ƴ�Τ�ȤǾ����ģ���ߤ���ư�����ʤ�Ǥ��롣���ʤΰ����ˤ������Τ�¿ȯ�������ε����Ԥ⾯�ʤ��ʤ�������Ԥ��ܤ꿴Ƭ��ȯ�����¤���������;���ʤ�����Ƥ��롣���������ǤϤʤ���������μ��פ�ᤰ��¿�ͤ����꤬���Ѥ��Ƥ��롣�����ģ�ο��ߤǤ����β���˽�ʬ�����뤳�Ȥ��Ǥ���Τ��������������ģ�ǤϤʤ��������ģ�ο��ߤ��������˸�Ƥ���٤������ȹͤ��롣����Ԥ�����λ���Ϥ��Ǥ˽���ä������������ԡפ����������ô������Ǥ��롣�����ģ�ˤ������褦�Ǥϻ��崶�Ф�����Ƥ��롣��2008/06/25�� �����̤��Ȳʳص��ѤȰ��̶���ȡ������ԤΡִĶ���ʿ�¡�����ؤλ�Ū�� �����ʲ��ϡ�ɮ�Ԥ�1999.05.14�ˡ��ֹ�������ե������פ���Ƥ���ʸ�Ϥߤ�Ŭ�礹��褦�ˤ鷺���˲���������ΤǤ��롣����ϡ���ΰ¸���ˤ��ֽ����ԡפ���Ƥ˴ؤ��뵭������Ū�ʰ�̣�ǡ����������롣�ֽ����ԡפ���Ƥ��������̤�Ĵ������ɮ�Ԥ⤽��ˤϻ����Ǥ��뤬�ˤΤ��Ф��Ʋʳء����Ѥ�����ο���˲��������뤫���䤦��ΤǤ��롣���बľ�̤�������ˤϤɤ�ʤ�Τ��������������������Ф��Ʋʳص��Ѥϲ�������뤫�������ƶ���Ϥʤˤ���������������ͤ��Ƥߤ��������ʥХ��С������ɰ�Ϻ�ˡ�2008/06/21�� �Ķ� �����ԡ���������ο��ä����桩��������ư�ᤰ���ݲ�Ĥ������� �����ܤǤϥ����������ʤ�����åȥ룱�����ߤ�Ķ�������ȥͥåȿ�ʹ���ɤ������������ꥫ�Ǥ⥬�������ʤ��夬��³���������������.����åȥ�ˣ��ɥ�λ���ˤĤ��������������ƥ�ӥ˥塼���˥����ͥ�碌��С����������ɤ���ʿ������֤��ޤ���ͤӤȤα������������֤�ή����Ƥ��롣��������ǯ�ˡ��������ɥ�ʲ��ˤʤä����Ȥ⤢�륬�������ʤϡ���������ǯ�ˤϤ���ƣ��ɥ��ۤ�����������ǯ�Σ�����顢���äȣ��ɥ�����ܤ��Ƥ������ʣԣգХ��å�����ʸ����ˡ�2008/06/10�� �֤�ä����ʤ��פ���������������������ѶȤ���ؤ֤��ȡ��¸���ͺ ��������������������פ��Ĥ����ѶȤ��ɤ����ޤ줿���Ҥ��Ĥ����������Ĥ��줿�֤�ä����ʤ������������̤εҤ˲Ƥ������Ȥ�ȯ�Ф������Ȥ����ä����Ȥʤä�������Էڻ��ɽ�졢�Ȥ������⤢�ꡢ�褷��˫��äǤϤʤ����������֤�ä����ʤ����������Ρʤʤ������ˤ��ˤ���١�����Ͽȶ����餷�����������˻��ޤ��������ӻ���ȯ�����Ƥ��롣������������ơ�����ꡢ�ȼ��������Ƥ���褦�Ǥϡ��䤬�Ƥ郎�Ȥ˺���Ȥʤäƹߤ꤫���äƤ��������������������ѶȤ���ؤ֤٤����Ȥϲ��������ε���ˡ֤�ä����ʤ���������ɤ��������������Τ���ˤϤɤ��˥�����줿��褤�Τ������ƹͤ��Ƥߤ롣��2008/06/07�� �������ˡ�δ���������ϩ���������ʷ��ȶ���ȵ�ۤ�ϲ�¸���ͺ ��������η������Ѥ�ʤ�뱧�����ˡ����̱��������̱��Σ��ޤλ���¿���ǣ���ǯ��������������ܲ�Ĥ���Ω������ȿ�Ф����Τ����ܶ����ޤȼ�̱�ޤǤ��롣���α������ˡ����Ω����̣�����Τϲ��������賫ȯ�Τ������������ʿ�����Ѥ��鷳�����Ѥؤȼ�Ū��ž�����Ƥ������ȤǤ��롣���δ���������ϩ�����⤿�餹��Τϡ�����ˤ����뿷���ʷ��ȶ���Ǥ��ꡢ���Τ���ε����ϲ��Ǥ��롣�Ͼ�Ǥ�ƻϩ�ʤɤؤ��Ƕ��̵�̸�����˰�����餺�����٤�ŷ��ˤޤ�̵�̸����α�ʤ������ˤ���Ĥ��ʤΤ�����2008/05/31�� ������� ����ˤ���ȯ�ϵ�����ʤ��������ԡ����ˤ�������ȯ�����ͤ���  �������ܤγƥ�ǥ������Ƥ����̤ꡢĴ����ߤˤ������ʪ�Ǥ�������ξ��Ȱ��ˤ�벣�Τ��Ķ��ݸ����Υ����ԡ����ˤ�����餫�ˤ��줿��Ʊ���Τ�Ĵ����ߤ�»ܤ��붦Ʊ�����ҤΥ�˥ե��������Ƥ���ط��Ԥ������ꤷ������ˤ��ȡֲȤ���Ƥ뤯�餤�פ��̤β��Τ⤢�ä��Ȥ�����ʪŪ�ڵФƤ��Ƥ��븽�ߡ����Ȱ��ˤ������β��Ρ��Ĥޤ���Ȱ��ˤ����������𤬤��ä����Ȥϡ���ߴط��Ԥ��������ȤΤǤ��ʤ������ˤʤäƤ��롣��������ϡ������ԡ���¦�ˤ�������������ˡ���������ԡ�������ǻ��͢������Ǥ��������������꤫�����𤷡������ʪŪ�ڵ�ˤ��������Ĥޤ������ʤ����𤷤��Τ����ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2008/05/25��
�������ܤγƥ�ǥ������Ƥ����̤ꡢĴ����ߤˤ������ʪ�Ǥ�������ξ��Ȱ��ˤ�벣�Τ��Ķ��ݸ����Υ����ԡ����ˤ�����餫�ˤ��줿��Ʊ���Τ�Ĵ����ߤ�»ܤ��붦Ʊ�����ҤΥ�˥ե��������Ƥ���ط��Ԥ������ꤷ������ˤ��ȡֲȤ���Ƥ뤯�餤�פ��̤β��Τ⤢�ä��Ȥ�����ʪŪ�ڵФƤ��Ƥ��븽�ߡ����Ȱ��ˤ������β��Ρ��Ĥޤ���Ȱ��ˤ����������𤬤��ä����Ȥϡ���ߴط��Ԥ��������ȤΤǤ��ʤ������ˤʤäƤ��롣��������ϡ������ԡ���¦�ˤ�������������ˡ���������ԡ�������ǻ��͢������Ǥ��������������꤫�����𤷡������ʪŪ�ڵ�ˤ��������Ĥޤ������ʤ����𤷤��Τ����ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2008/05/25��
���������ǡ������ܼ���δ��ᡡ�����ж�ù���˳ؤ֤��ȡ��¸���ͺ �������������������������פ�ΤƤơ���������ˡ־����ܼ���פؤ�ž���������Ȥ��Τ����ж�ù������塢����κ¤��¤Τ���鷺��������ǵ�餶������ʤ��ä������κ���פȤ⤤���롣����ù�������ޡ��⤷��ߤǤ���С����ܤ����٤���ϩ�Ȥ��Ƥɤ��������ۤ����������������Ϥꣲ�������ǡ־����ܼ���פ�빽�۰ʳ��ˤϹͤ����ʤ�������ľ��β�����ˡ�ƤΣ�������������������ڤӸ��︢����ǧ�ˤ�ߤơ��˲�����ޤ�ʤ��פȶ����ù���Ǥ��롣����ù���˳ؤӤʤ��顢���������ǡ־����ܼ���פι��ۤˤĤ��Ʒ�ˡ��ʿ����ǰ���ȯŸ���������β������������ǹͤ��롣��2008/05/17�� ��ˡ���������仺����Ͽ����̱���Σ���ǯ�ۤ���̴���¤롡�¸���ͺ �������Ū����˥塼�������ӹ���Ǥ�����ʿ�·�ˡ���������仺����Ͽ���줿�Ȥ����ΤǤ��롣��������ܤ����Ϥˤ�����̤ǤϤʤ�����̱���ΤΣ���ǯ�ۤ���̴���¤ä���ΤǤ��롣�����ʹ�ʤɰ����Υ�ǥ�������®�Ҳ𤷤Ƥ��뤬���ɤ������櫓������ǥ������Ƥ��ʤ�����̱��ǥ����Ρر����ٹ泰�ʣ�������ǯ������աˤ����路�������Ƥ���Τǡ��ݤ�ʲ��˾Ҳ𤷤�������2008/04/10�� ���֥ץ饤������������ν������֥�٥�룲���פǤ����Ĥ��顡�¸���ͺ ��������ꥫ�Υ��֥ץ饤�ࡦ����������Ϸ�ɤΤȤ��������̣����Τ�����ư���Х֥���������Ϥޤä�����Υ��֥ץ饤�ࡦ������ʿ����Ϥ��㤤�Ŀ�������ͻ��ˤ���þ��ñ�˿��ѡ���ͻ����þ�ˤȤɤޤ�ʤ����ޥ͡���������ܼ��������ͳ����к�ϩ���ιԤ��ͤޤ�Ȥ����º����ˤ�������Ū�ʳ��¡��ɥ�������¡ʣ��ɥ�ᣱ�����ߤ�������ˤ��������Τ����Ƹ������ᤶ���֥���ꥫ�λ���ס��֥���ꥫ���פ��Τ�ΤΡֽ����פȤ���Ÿ˾�ˤޤǹ����äƤ��Ƥ��롣 ��2008/04/06�� ƻϩ����⸻���Ĥ�������Ĥ���æ�ּ֡ס�æ��ƻϩ�פ��߷פ¸���ͺ ����ƻϩ����⸻�ΰ��̺⸻����������Ψ��ݻ����뤫�ѻߤ��뤫����ᤰ�������Ĥϡ����ܡ�Ϳ�ޤ����ޤȤ���Ω���ʤ��ޤޣ������ǤҤȶ��ڤ�Ȥʤ롣���������ι�����ĤǤϴο��Υơ��ޤ������ȤʤäƤϤ��ʤ����������æ�ּ֡ס�æ��ƻϩ�פ�ᤶ���Ȥ���ĩ��Ū�ʲ���Ǥ��롣��������������濴�θ��̤Τ������ˤ����������Τ���³����ߤ��Ƥ������֤Τ���κݸ¤Τʤ�ƻϩ�Ť����������ϲ����طʤ���Ƚ����ޤäƤ�������������������Ķ����Ĺ��Ū����顢æ�ּ֡ס�æ��ƻϩ�פ��߷ޤ�ɤ���������ޤ��Ȥ��Ǥ��롣����������Ϥ�ư���ˤ��ܤ��ۤ�ʤ��顢�������߷ޤ������Ƥߤ롣��2008/03/31�� �������۶��ʤϡֿ���ʻ��֡פ��������ۤ�ɬ�פʻ������Ƥ��롡�¸���ͺ �����������ۤΤ����������ƶ��ʤȤʤäơֿ���ʻ��֡פ��������Ǥ��롣�����ʡ���ɧ���ۤ餬��������ǯ�������Ǥ����λ�Ȥʤ�Τ�ȼ������Ǥ����Ȥ������ܤϡ���ƣ��Ϻ���������ۡ���������ȹ̼���ݶ��϶�����ۤ���������������Ȥ����ޤ�¿�������뻲������Ʊ�դȤʤä�����Ǥ��롣���������������Ť��б����������ष��������ª���ơ������ۤˤդ��路����ʪ����ͤ���Ȥ��Ǥ���������Ϻ���ɬ�פʻ���Ȥ��ơ��к������Ѥ�ȤˤĤ��Ƥ��뤳�ȡ��кѤ���餷�˺�����˲����Ƥ��뿷��ͳ���ϩ���ʡ�Ծ츶������ˤ˰���ε�Υ���֤����Ȥ��Ǥ��뤳�ȡ��Σ������������2008/03/21�� �ƹ�Ȥϵ�Υ���������Х���˿��Ρ��ѳספ���ԤǤ��뤫�������ɰ�Ϻ �����躢���顢�ƹ����������������������������ά�Ҥ����������٥2007.12.13��2008.01.08��2008.01.05�ˡ����ܤϡ����ߥ���ꥫ���������������к�Ū�ʤ���¾��ʸ����ޤ�ơ˱ƶ������˶��������Ƥ��ꡢ���ʤ��Ȥ������˷Ȥ��͡��Ϥ���ޤ��Ƥ��ơ����ܤϥ���ꥫ�μ¼�Ū��°��ȤʤäƤ��롣�⤦���١�����ꥫ����������ͤ�ľ���ơ����ܤγ�����˥���ꥫ�ؤ��ɿ��ߤ�Ƥۤ�����ǰ�ꤹ���ΤǤ��롣����ꥫŪʸ���ϡ��٤����ᤫ�졢�ϵ�ʸ��������Ǥ�����ʤ���ΤǤ��롣��2008/03/03�� ���������̿�������Τ������������ϡ֤������פ��ѴϤ¸���ͺ �������弫����Υ��������Ϥ������˾��ͤ������դ���ң��ͤ����������ˤʤä�������礭�����椬�����äƤ��롣��ҤϹ��������Τޤޤ��ϸ��ε����ʤɴط��Ԥϣ�������ܺ����Ǥ��ڤ餶������ʤ��ʤä������ε���˼�����������ˡֹ�̱����̿�Ⱥ���뤳�ȡפ�Ǥ̳�Ȥ��Ƥ���Τ�����ͤ�����������˾��ͻ�����������������ϡ֤������פ��ɱҾ�����ϲ������֤������פ�ɬ�פ�ʼ��ʤΤ����ѴϤˤ��٤����Ȥ���������ӽФ��Ƥ��뤳�Ȥ�Ҳ𤷤�������2008/02/28�� ��������Ĺ������Ϲ�ݿ������ȿ�����ܥ�ǥ����ϡ��Ƶ��ԡװ�������� ���������µ�����Ĺ�Υ����ѥ�Ǥ������ᤰ�ꡢ���ܤΥ�ǥ����Ͻ���뱫Ū����ƻ��³���Ƥ��뤬�����ܤ��ƹ����ڤ��Ƥ����ݿ�����˰�ȿ���Ƥ��뤳�ȤˤĤ��Ƥϡ��ۤȤ�ɿ�����Ƥ��ʤ�����ݿ�������ˤϡ��ֲ��ͤ⡢���줾��ι��ˡΧ�ڤӷ�����³�˽��äƴ��˳���Ū��ͭ������̵���Ƚ���������٤ˤĤ��ƺƤӺ�Ƚ�������Ͻ�ȳ����뤳�ȤϤʤ��פȤΰ���Ժ����θ�§�����Τ˽�Ƥ��롣�ʰ��Ρˡ�2008/02/27�� ���Τ��γ����¸�ϴ������������Ȱ����ݾ�μ�Ω����ơ��¸���ͺ ������������硼���ˤ�����ǻ������Ǥ���ʼ�ˤ�뾯����˽�Ի�������Ƴ��弫���⥤�������Ϥ������˾��ͤ������դ���ң��ͤ����������ˤʤä�����礭�ʾ��Ϳ�������Σ��Ĥϡ���Ϣ�Τʤ��̡��λ���Τ褦�˸����뤬���¤Ͽ����ǤϤĤʤ��äƤ��롣�����طʤˤ��붦�̹�ϡ����ˤ�ޤ������ڤ����ܿͤΤ��Τ�������Ȥ�����Ω���ä���¸�������кѹ�¤�Ǥ��롣�����ġʤ椬�ˤ��줿�����ʹ�¤�����ܤ������Ȱ����ݾ�μ�Ω��ɤ��¸����Ƥ����Τ�������������С֤��Τ��ΰ����ݾ�פ��̱�μ�˼���᤹���Ȥ��Ǥ���Τ������䤦���Ǥ��롣��2008/02/22�� ����¿���ͤ����ȡ�ʿ�����ס�ɴ�жᤤ��Ϸ�Το����˳ؤ֡��¸���ͺ �������٤μ��ʲ��������ä��ֿͤ����ϻ���¿��ι��ƻ�פ��ꤹ������ʸ�̤�Ҳ𤷤褦������������ޤ����褿�顢�֤ޤ��ޤ��ᤤ�פʤɤ������ƤߤƤϤɤ������Ȥ������ߤ��٤��ʸ�����¤�Ǥ��롣�����Ĺ�����Τ�����Ǥ��롣ï����Ĺ������˾��Ȥ�������������ϲ椬������ɤ������뤫�Ǥ��롣ɴ�жᤤ��Ϸ�ΤΡ�ʿ�¤�ƻ�פ��������ԵӤ˳ؤӤ�����2008/02/16�� �ߥ饤���ʥ�������Υ����ǥ�ƥ��ƥ����ƹ�������ɽ�פϴ����� �����ե����奢�������Ȥ��������긢�ϣ���������ߥͥ���������ȥݡ���ǹԤ�졢��о�Υߥ饤���ʥ����ʣ����ˤ�ͥ�����������˾売���ܤμ㤵�Ǥ�ͥ���Ǥ⤢�ꡢ���ƥ�ǥ����Ϥ��β�����礭�������������ܤǤ��ƹ��Ʊ���褦�˥�ǥ��������ܤ���������ξ�Ƥ����ܿ͡ס�������ξ��ι��Ҥ���ġפʤɤ����äʻ����Ǥ���ƻ����Ω�����ʥ��������ܤ���ɽ���ƹ�ݻ��ʤɤ˻��ä����ǽ���ޤǼ������Ƥ��롣��̱�ι�Ǥ����ƹ�����ޤ줿���ƹ����������ܥ�ǥ�������ľ�˰��ƹ�ͤ���ǧ��뤳�Ȥ�����ʤ��Τ����������ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2008/02/04�� �����ǥ������༣���褦���Τ�����ȥ˥åݥ���ס��¸���ͺ ������Ū���ФΤ椿���ʿͤϽդ�ˬ�줬�ֶᤤ�ȴ����Ƥ���Ȥ��Ƥ⡢���������´��Ȥ��Ƥϸ��ߤκ���Ǥ��롣���٤Ǥ������������¿���Ȼפ��Τǡ����ε���������Ȥ�������θ�Ū��ˡ����Ϫ�������٤��༣���褦�ȸƤӤ���������Ʊ���˰�ͤҤȤ꤬�Dzᤴ���ˤϤɤ�������褤��������ˤϤɤ��������š��Ҳ���פ�ɬ�פʤΤ���ͤ�����Ƥ���������2008/02/04�� ������� ���ʤ��ϥ������ȥ�ꥢ���ΤäƤ���Τ����桼���塼�֡�������������ȥ�ꥢ��ȿ��ߡ�Ԥ��䤦 ������Ⱦ��βƤϻ�ˤȤ�ͫݵ�ʵ���������ܤϥ������ȥ�ꥢ����ˤ�����ɹ�Τ�������Ĥ����ꡢ�����Ĵ����ߤ�������������ĥ���������ȥ�ꥢ�����ܤ���ߤ��¼�Ū�ʾ�����ߤ�����Ƚ���롣��ϴĶ��ȿ�ƻ��Ω�줫�����ܤ���ߤ�����Ū�����ꤷ�Ƥ��뤬���������ˤϴ����ή����丫����ή���Ԥ����ʤ��ʤ����������ȥ�ꥢ�����ܤ��������餪�ߤ����ͤ���դ�ʹ�����Ȥˤʤ롣����Ū�ˤ����������ܤ���ӤƤ���桼���塼�֤Ρ�������������ȥ�ꥢ��ȿ��ߡפ��㳰�ǤϤʤ����������ȥ�ꥢ������Ū����Ƚ���Ƥ��롣�����Ƥ���ư��κ�Ԥϥ������ȥ�ꥢ���Ф����μ��������Ǥ��뤳�Ȥ��顢�����Ĥ��ε����������롣�ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2008/01/15�� ������������Լ縢�פγ�Ω������ԡ�����Ԥ�����פȤϡ��¸���ͺ ����ʡ�ļ���ϡ��������ǯƬ���Բǡ�����ԡ�����Ԥ�����ˡפȸ�ä�������ȯ���ο��դϺ��ҤȤ����������������ȯ�ۼ��Τϰ����ʤ����Ϻ��ؤ�������ʤɹ�̱���褬�����¤˴٤äƤ��뺣����������Ԥ�Ż뤹������Լ縢�פγ�Ω�����Ȥ����ȹͤ��롣���ΥХ֥�кѤ�����������������ǯ��ν�Ƭ�����ܤ����������ײ�פ��Ǥ��Ф����ޤ����꤬������Լ縢�γ�Ω�פ������Ȥ⤢�롣����ԡ�����Լ縢�Ȥϲ����̣���Ƥ���Τ������ε��������Լ縢�Τ���������Ƥ���������2008/01/10�� ���ܹ�Ȥ����������������������ͤӤȤؤκ��۶��δ����������ɰ�Ϻ �������ܤȼ��չ�Ȥ���ˤˤϡ���������ϡ������ʥ����ˤˤ�룲��ˤ錄�����ܿ����λ�ߤ����ꡢ�������Ⱦ���Ȥ������ά��տޤ���ī���أ���ˤ錄���ʼ�����ʤɤ����ä���������ˤϡ����ī���Ȥθ�ή������Ǥ��ꡢ�ä����ܤˤ������Ϥ�ʸ����ʸ�����ݼ�����ܤ���˷������礭�������������ʤ�������Ȥλ�ߤ�����С����ͻ������ޤǡ����չ�ȤϤ��ʤ�ͧ��Ū�ʴط����ݤ��줿�褦�Ǥ��롣���ϡ�������ڻ��ۤ˴�Ť��ơ����ܤ�����Ƥ����Ȥ��Ƥ�Ǥ��뤬���������������ݿ��������ܤϼ��չ�ؤο�ά�ԤˤʤäƤ��ޤä�����2008/01/10�� ����ꥫ������ΰ���֡��֥����Υߥå��ҥåȥޥ�פ�ʪ�졽�����ɰ�Ϻ 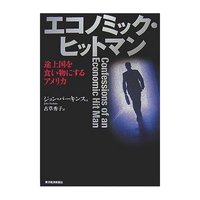 ������ˡ֥���ꥫ�������Ū���������ռ��סʡ���Ϣ�����ˤǥ���ꥫ�������ƽ���ʤɤǡ����Ϥˤ�ä�����žʤ�ʤɤ��ߤ��褿���Ȥ�����ƽҤ٤������Ϥˤ��ʤ��������Ū������ۤ���ߤ��Ƥ����������ǤϤ��ΰ�ü��Ҳ𤹤롣����ϡ������Υߥå��ҥåȥޥ�Ȥ����͡����濴�ˤʤäơ���ݶ�ͻ���ءʣɣͣơˤ�������ԡʣף¡ˤ�𤷤�ȯŸ�Ӿ���к�Ū�������դ��먡����п�̱�ϲ������꤫���Ǥ��롣���������ҥåȥޥ�ΰ�ͤǤ��른��ѡ����Ȥ����ͤ����γ�ư��˽Ϫ�����֥����Υߥå��ҥåȥޥ�ι���ס����ˤȤ����ܤ��顢���Τ������Ҳ𤹤롣��2008/01/05��
������ˡ֥���ꥫ�������Ū���������ռ��סʡ���Ϣ�����ˤǥ���ꥫ�������ƽ���ʤɤǡ����Ϥˤ�ä�����žʤ�ʤɤ��ߤ��褿���Ȥ�����ƽҤ٤������Ϥˤ��ʤ��������Ū������ۤ���ߤ��Ƥ����������ǤϤ��ΰ�ü��Ҳ𤹤롣����ϡ������Υߥå��ҥåȥޥ�Ȥ����͡����濴�ˤʤäơ���ݶ�ͻ���ءʣɣͣơˤ�������ԡʣף¡ˤ�𤷤�ȯŸ�Ӿ���к�Ū�������դ��먡����п�̱�ϲ������꤫���Ǥ��롣���������ҥåȥޥ�ΰ�ͤǤ��른��ѡ����Ȥ����ͤ����γ�ư��˽Ϫ�����֥����Υߥå��ҥåȥޥ�ι���ס����ˤȤ����ܤ��顢���Τ������Ҳ𤹤롣��2008/01/05��
�ֵ��פ���ԤǤ��뤫����ǯ���ֵ��פ����������룰��ǯ���¸���ͺ �����������������������ǯ�ϡֵ��פ��������ֵ��פ����褦�Ȥ��Ƥ��롣���Ρֵ��פˤޤĤ�봶�ۤ�¿���οͤ��餤����������ͧ�ͤ����彨�ˤ�������ءʷ��ˤΥ�å������ʣ���ǯ������ʬ�ˤ��Ϥ������ְ�ǯ�������ɽ���Һ�ǯ�δ����Ӥ����Ф줿�ҵ��Ӥ������伫�Ȥ�ȿ�ʤ⤳��Ƽ��夲���פȽƤ��롣�⤦��Ĥϡ����ܷб�ƻ������ɽ�������������Ρֳ�����å������פǡ��ֺ�ǯ��ɽ�����ա�"���Ĥ���ϡ����ܤȤ����Ѥ�����������ǰ�ʻ��פȤ��롣�ɤ����ֵ��פˤ�����뼨�����٤����ʸ�ʤΤǡ��ʲ��˾Ҳ𤹤롣��ǯ����ǯ�ϡֵ��פʤ�ֵ̡��פ����᤹���ȤϤǤ��ʤ����������������������Ԥ����ư�ǯ���֤롣��2007/12/28�� �ͣġ������פ�������Ρֵ��ס���̱������Ǥ��פ����ά���¸���ͺ ������ǯ�������ɽ������Ρֺ�ǯ�δ����פˡֵ��פ����Ф줿����ǯ�ۤ����ܡ���Ȥˤ�뤴�ޤ����������������ʼ�ȴ��������������ǯ�����ĤƤ��ä��������������κǸ���о줷����ǯ����Ρֵ��פȤ������ܤγ��弫����ˤ���Σͣġʥߥ������ɱҡ˼¸��Ρ������פ�������ɱҾʤϡ������פ�Ϥ䤷�Ƥ��뤬������Ū�˻��Ȥޤ줿�������פǤϤʤ����Ȥ������䤬�Ĥ롣���ξ塢���Ρ������פ��⤫��Ƥ���ȡ����Ť����Ȥ��ϡ������Ǥ��٤����ǹ�̱������Ǥˤ������Ǥ���Ȥ������פ˴٤äƤ����ǰ�����롣��2007/12/24�� ��Ƭ����������ꥼ������кѥ������Х벽�ؤβ̤��������¸���ͺ �����������ꥼ���������ϰ�������ˤȤ���̾�ο�����ĩ�郎���ܤ�ޤ�����������Ƭ����������ĤĤ��롣����ϷкѤΥ������Х벽���������ˤؤ��й����Ȥ��ơ��������Х벽�����߽Ф�������������뤿��˻�̱�������ͤ��Ĥ����̤������Ȥ⤤���롣�������ꥼ��������ܻؤ���Τϲ��������μ����Ϥɤ��ޤǿʤ�Ǥ���Τ�����������̤����Ƥ��룲�ͤν�����ư�Ȥθ�������ĥ���������ɤä�������ϡ�����������Ƥ����������Х벽�סʣ���ǯ����������Ǻܡˤ�³�ԤǤ��롣��2007/12/21�� ����������ǽ�������ƴ⡡��ʪ�Υ������Хꥹ�Ȥηٹ𡡥����������£�����ǯ�����ɡ����ۤνա� �����ֻ䤿���ν���Ǥ����ϵ�ϼ�ʬ�����ʹ֤����Τ�ΤǤϤʤ��ס��쥤�����롦��������Ρ����ۤνաפκǽ�����ΰ���Ǥ��롣��ǯ��������ϡ��쥤�����롦������������£�����ǯ�Ǥ��ä�����ǯ��ǯ��ȼ������̿������������ǯ�˽��Ǥ��줿�����ۤνաפϡ������������ζ��滶�ۤˤ���礭���ﳲ��Ф��Ƥ����ƹ�����Ǥʤ������ܤ�ޤ��������ݤ���ǧ�����������̻��Ѥ��Ƥ������������졢�礭��ȿ����Ƥ�������衢������ʪ�ؼԤǤ��ä��쥤�����뤬�ʤ������ۤνաפ���Τ���Ļ���Ĥ��ʤ��դζ��ä˻Ϥޤꡢ���̤�ƻ�פǽ��������ۤνաפ��١��ɤ�ľ���Ƥߤ����Ȼפ����ʲ�ƣ��karibu����ҡˡ�2007/12/14�� ����ꥫ�������Ū���������ռ��ʾ�ˡ����ɰ�Ϻ�ʥХ��С����β�� �������ߥ���ꥫ�罰��Ϥ����ϵ���ͣ��Υ����ѡ��ѥ�Ǥ��롣�������ɤ���̣�ǤⰭ����̣�Ǥ⥢��ꥫ��ư����������ư��������������ǯ��������λ�����衢�ä˥ƥ��Ȥ��з�Ȥ���Ⱦ�ʵ�Ū���������������Ǥ��롣�äˡ����ܤθ������Ϥ��αƶ������˶��������Ƥ��뤷������ꥫ�Ȥ�嫤˶���ĤĤ��롣���λ��ˤ����ꡢ����ꥫ���ܼ�Ū�ʤ�Τ�Ƹ�Ƥ���뤳�ȤϽ��פǤ���Ȼפ��롣��2007/12/08�� ��̿��ʬ�����Τϡ��������ӥ�ͼҲ���¤�ư�ɡ����奨��(���ռ��ס� ������������ǯ����������Ԥ����ȤϹ������ˤ��������������ɤؽ�Ƭ�����������ӥ�ޡʥߥ��ޡ��˿ͤǤ���Ԥ���ʣ����Сˤȱ�����ΣӤ���ʣ����Сˡ������©�Ҥ�N����ʣ����СˤΣ��ͤǤ��롣�Ӥ����Ԥ����ӥ�������θ��ԥޥ���졼�νпȤǤ��롣���ͤϣ�������ǯ�˥ӥ�ޤǷ뺧���Τ���ϣ�������ǯ�ˡ��Ӥ���ϣ�������ǯ�ˤ��줾���������������ͤ�¿���γ���ͤ������Ǥ���褦��û���ںߥӥ��ʣ������ˤ�俭���뤳�Ȥʤ����ܤΰ���Ź�ʤɤ�Ư���ĤŤ������ںߴ��¤ϤȤä���Ķ�ᤷ�������С����ƥ��Ǥ�����ˡ��ϫ�ԤǤ⤢�롣��2007/11/30�� �ɱ������ι�¤Ū�𰭤˥�������羦�Ҹ���̳�������ǡ��¸���ͺ ��������ϸ��������ϣ���ǯ����������������羦�ҡֻ����ιԡ���̳�εܺ긵���Ƶ��ԡʣ����ˡ����ܥߥ饤������Ĺ�����̳�岣�Τʤɤε��������ᤷ�����ɱ�������ᤰ�뵿�Ǥˤɤ��ޤ��ܺ��μ꤬�ڤ֤������ܤ���뤬���ɱҾʤ�����η�����Ϣ��ȤȤε��Ǥ˻������ꤹ�٤��ǤϤʤ�����������������������������������ʣ���ΡפȤ�����¤Ū�𰭤�¸�ߤˡֻ�̱�λ����פ��ܤ���餻����������Ȥ��Ǥ��롣���ư��ݡᷳ��Ʊ����٤�����������ʣ���Τ�����뤹�����Ͻ����ĤĤ��롣��2007/11/10�� ���Ȥ�ʿ�¤��ڤ�Υ���ʤ� �֤μ��Ƥ��졢�������ȴ�����줿���夬���ä��������¶� �������ܤ���������ά�����ꥢ��ꥫ��������ꤷ�����Ȥʤ��Τ�ʤ����夬���������ܤ�����ؤʤɤǥѡ��ȥ�����ζ����Ȥ������ȴ�Ϣ�ιֵ��뤳�Ȥ����뤬���ɤ�ʥơ��ޤΤȤ��ˤ�ɬ�������������ä����Ȥ����롣����ϡ����Ȥ�ʿ�¤��ڤ�Υ���ʤ��ط��ˤ���Ȥ������Ȥ�����������ʿ������ο������桢�֤Ť�������ݤ����̱�Ȥ��ƻ������ܤˤ�äƵ��Ƥ��졢�������ȴ������ƥ����८��������줿�����������ܤ���̱�ˤϤ��롣�����ɴ����ʼ��˰���ȴ�����Ф���Ǥʤ�����뼫ͳ����å�ä��Ȥ������Ȥ��ä��Ƥ⡢�������ʤ��褦�ʴ�Ƥ��롣��2007/11/08�� ���饯���ή�ѵ��ǡ����֥�����ε����פ�Ű�����������ζ�סʥ��㡼�ʥꥹ�ȡ� ����ʡ�Ĺ����������������飱����;����ʹ�ƻ�ϡַ�������פ���æ�餷����̣������夤����������ä����Ȥ�ɾ�����ĤĤ⡢�ֿ�����Ÿ���ζ�������˳�����פȡ����ͤ���ɾ���Ƥ������Ȥˤ�����ǯ�⡦���š����顦�����������ʤɤΤۤ��������ɱҤ�ᤰ������Ƥ����Ѥ��Ƥ��롣�����Ǥϡ����̤Ρ֥ƥ���������ˡ�סʣ�������Ǵ����ڤ�ˤ�ư���˹ʤäƹͻ����ߤ������֥ƥ�����ˡ�פˤĤ��Ƥϡ����������Ǥ���夲������������Ƥ������֤����θ弡������ߤ˽ФƤ��Ƥ��ꡢ�����ξ����Ƨ�ޤ��ơ����������Ŧ�������Ȼפ�����2007/11/01�� �֤��ޤ��������ܤ��������硡�����Ϸ�ˡ�����ư��ݤȤ�̷�⡡�¸���ͺ ������ǥ�����Ϣ���Τ褦���꼡����̱�Τ��ޤ����������������Ƥ��롣�֤��ޤ��������ܤ��������� �� �Ȥ��äƤ�褷�Ƹ�ĥ�ǤϤʤ����ܤ�ʤ�������ʤ�ۤɤ���̮�֤�Ǥ��롣�ʤ�����ۤɤΤ��ޤ����������äƤ����Τ������κ�����õ�����Ƥ����ȡ������Ƥ���Τϡ�ʿ�·�ˡ�����������Ƥ������ư��������ζ����Ǥ��롣����̷���ʤ���������Τ褦�˹�����ȸ��������Ƥ��������ݼ������ζʤ��ä��������⤫�Ӿ夬�äƤ��롣���η�ˡ�����Ȱ��������Ȥ�̷����������ʤ��Ǵ�̱�Τ��ޤ��������ڤ����䤹��̯��ϴ��ԤǤ��ʤ��ΤǤϤʤ�������2007/10/28�� �ƹ�̱���������������������ܤˤ�륯���ǥ������ʹԡפȻ�̱��ǥ������پ⡡���ɰ�Ϻ  ���������Υ���ꥫ��̱�����������Ȥ���ɽ�����褦���ʤ�������ꥫ�Υ����륿�ʥƥ�����ǥ����ΰ�ġ�AlterNet���������������������ϡ��������ܤˤ�륯���ǥ��������Ϥˤ��ʤ��ˤ��ʹԤ��ĤĤ���פ�ɽ�����Ƥ��롣ʬΩ���������Τ�����Ωˡ�ܤ����β�����ˡ�Ϥ��Ǥˤ��ʤ�Ĺ���ֹ�ȴ���ˤ���Ƥ��ơ������ܡ��������ܡˤ��פ��Τޤޤ�������ʤ�Ƥ��롣����ǯ�Τ����˹����̤ä�ˡ���Τ����������������ۤ���Τˡ������Τ��յ����ơ��ؤ������Τ���դǡ˾��ˤ�äƤ�ˡ���˹�«����ʤ��Ȥ��Ƥ��롣��2007/10/25��
���������Υ���ꥫ��̱�����������Ȥ���ɽ�����褦���ʤ�������ꥫ�Υ����륿�ʥƥ�����ǥ����ΰ�ġ�AlterNet���������������������ϡ��������ܤˤ�륯���ǥ��������Ϥˤ��ʤ��ˤ��ʹԤ��ĤĤ���פ�ɽ�����Ƥ��롣ʬΩ���������Τ�����Ωˡ�ܤ����β�����ˡ�Ϥ��Ǥˤ��ʤ�Ĺ���ֹ�ȴ���ˤ���Ƥ��ơ������ܡ��������ܡˤ��פ��Τޤޤ�������ʤ�Ƥ��롣����ǯ�Τ����˹����̤ä�ˡ���Τ����������������ۤ���Τˡ������Τ��յ����ơ��ؤ������Τ���դǡ˾��ˤ�äƤ�ˡ���˹�«����ʤ��Ȥ��Ƥ��롣��2007/10/25��
�������֤�ä����ʤ���������Ϸ�ޡ���ʡ�פ��Ծͻ��˹ͤ��롡�¸���ͺ ������Ȥ��Ծͻ����꼡���Ǥ��롣�ǶἪ�ܤ�Τϡ��϶ȣ�����ǯ����ˤ�ؤ��߲ۻҤ�Ϸ�ޡ���ʡ�ס��ܼҡ����Ÿ������ԡˤ����Ĥ꾦�ʤ���¤������������ܼҹ����̵���±Ķȶػ߽�ʬ�ʣ���ǯ����������ˤȤʤä��Ծͻ��Ǥ��롣����ʤκƻ��ѤʤɤΥ롼���ȿ��ĤŤ��Ƥ�����Τǡ���Ĺ�ϡ֤�ä����ʤ��פ���ͳ�˵Ƥ��롣����������ϡ֤�ä����ʤ���������̵����Τ�����Ω�ä����ѤǤ��롣������������֤�ä����ʤ��������ϡ��ɤ�������̣�������ƹͤ��������Ծͻ��Ȥ����褦����2007/10/21�� �����������Ǿ—���μ�ꡡ�ְ�ä������ѤϤ����˿����դ�����Τ������ɰ�Ϻ �����Ҷ���Ǿ�ϡ�����Ū�����ʳ��ϡ�������ΰ�ְ�֤˼��Ƥ��륷���ʥ�˴�Ť�����������롣��ƤȤ��ΰ���ǧ������Ϥޤäơ����٤Ƥηи���Ǿ�˵�Ͽ���졢����˴�Ť��ƺ����˥塼����֤���������������Υ����ʥ�ؤ�ȿ�������롣�ʹ֤��̾������Ķ��Ǻ���뤳�����������ϡ��ʹ�����Ǥι�ư��ɬ�פ�Ǿ��ư���ݾڤ���褦�˽���Ƥ���褦�Ǥ��롣����Ϥ����������������Ļ�����Ƹ��������ʴĶ��ˤ��뤳�Ȥ�����ˤ��Ƥ��롣������ʬ���ϤʤɤϤ���ޤǤ˷������줿���Ǿǽ�Ϥ�����Ȥ�����Ƭ�����̤˽����˺��夲���롣��������������ʬ���ϡ�Ƚ���ϡ������ϤȤ��ä���̤�Ǿǽ�Ϥϡ���Ĺ�������Ͱ̤ޤǤˤϽ�ʬ�ˤ�ȯã���ʤ��褦�Ǥ��롣�������äơ�������Ƚ���Ϥʤɤ���ʬ�˷�������������Ǿ�˿����դ���줿�ͤ��������ۤʤɤϡ����Ȥ��Թ����������ΤǤ������ȸ�ˤʤä��Ѥ��뤳�Ȥ��Բ�ǽ�ǤϤʤ��餷�����������������Τ��Ȥ��������ã�ϡ���ʬã�˹��Թ�ʿʹ֤��ƾ夲��Τ����Ѥ��Ƥ��롣��2007/09/12�� �����������ﳲ�Ȳó�������ҡʥΥ�ե��������饤������ �����Ƥˤʤꡢ����������ʤ뤳���ˤʤ�ȡ�̴�롣�������������Ƥ�Ǥ��롣���ٱʤ�����ʻ�ε����ˡס��ٿ����һҤ��������ޤ�̴����ˤ��ʤ��顢��Ϥ��줬̴�Ǥ��뤳�Ȥ��ΤäƤ��롣������¿ʬ����̤ޤǤ�������������Υ��ʤ����Ȥ⡣�����������Ĥ�ϡ���ʬ������̿��ʤ館�����Ȥ�֤��ޤʤ��פȤ�������ʬ����������Ȥ����櫓�Ǥ�ʤ��ΤˤȻפ��ʤ��顢��Ϥ�֤��ޤʤ��פȤ���������������縩Ω����������ع���ǯ�������饹�ϡ������Ϥ���쥭�����λ�����Į�ʻ�����ˤ��³��ϸ����դ���Ȥ˹Ԥ������������Ǥ�������2007/08/26�� ���ȴ��Ǥ�����Τ����ᡡ æ�ַк���Ĺ�פ�������������¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� ������ʰ¸��ˤϣ���ǯ������������ܥץ쥹�����ӥ������������Ķ����dz����줿��ʩ���кѥե����������㸦���ǡ����ȴ��Ǥ�����Τ�����פ��ꤷ�ƹ��ä�Ԥä������ܼ���Ϻ���λ������ǡ���Ĺ��´��ˡ��פʤɤ����Ѥ�餺�к���Ĺ����˼��夷�Ƥ��뤬���к���Ĺ�ˤ�äƻ��ͥ륮����ϲ���ϵ�Ķ��α������˲���˿ʤ�Ƥ������ȤϤ�Ϥ������ʤ���������Ĺ�Ǥ�褷���ȹͤ���æ�ַк���Ĺ�פ���������������Ǥ��뤳�Ȥ�Ĵ����������2007/07/26�� �٥����ꥢ��ȥե��å����������ʤ�������������ưʪ �����Ѹ�Υ٥����ꥢ��Ȥ������դ����ܸ�Ǥϥ�������ɽ������뤳�Ȥ�¿�������ֺڿ�����פȤ���������Ȥä����ܸ����⤢�롣ɮ�ԤϤ���ޤǡ��ڿ������������ʤɡִĶ��ˤ�ͥ�����������⤤�Ƥ����������٥����ꥢ��ˤȤ���֤δؿ����ϡ���Ϥꡢ̿�����ڤˤ��뤳�Ȥ���¿���οʹ֤ϡ����������Ǥʤ�������ȶ�ˤ����Ƥ������ʤʤɤ���Ѥ���̿�������˰��äƤ��롣�������ȥ�ꥢ�Υե��å�����֣٣ţΡפ��ǿ���������ʤɤ˴ؤ���٥����ꥢ��ů�ؤ��ý��������������Ƥ�Ҳ𤹤롣�ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2007/07/05�� �����˷����̵����Ϥ���Ρ������ɰ�Ϻ�ʥХ��С�����β�� �������ܹ�Ϸ�ˡ�η�����ϡ����⤬�ʤ����ȤˤʤäƤ��ޤ���������¸�ΤΤ褦�ˡ����¤ˤϻ��¾�η���Ἣ���⤬���ꡢ���ε��Ϥ������Ǥ�ͭ�����礭����ΤǤ������ߡ���������Ϳ�ޤϡ���ˡ�ʣ���ˤ���ꤷ�ơ�����������η���ˤ���Ʋ���ȹˤ���ʼ���褦�Ȥ��Ƥ��ޤ�����ˡ����������ϡ����ʶ������Ϥˤ�餺�ä��礤�Dz�褹�٤��Ǥ��ꡢ���ܤϤ�������Ȥ�����ΤǤ����������äơ�����ϻ����ʤ���������Ƥ��ޤ���¿���οͤη�ǰ�ϡ���������褿�Ȥ������⤬�ʤ��Ƥɤ������ɸ�Ǥ���Τ��Ȥ������ȤΤ褦�Ǥ������⤬�ʤ��ƹ�Ȥ�����Ω�ĤΤ����������¤Ϸ����⤿�ʤ��Ȥ�������Ω������ΤǤ��������ˤϷ��������ʤ����Ǥˣ�������⤢��ΤǤ�����2007/06/28�� �ڿ�����Ǥΰ���ϡֻ��͡פ����ƹ�λ��狼��ͤ��� �����ƹȥ�˺߽��������������������ʤ������ʤ��ִ����ڿ�����ԡסˤΥ��åץ뤬���壶���֤Τ郎�Ҥ��व�����Ȥ��ơ����ȥ�ι�����Ƚ��ϣ�������ֻ��ͺ�פ�ǧ�ꡢ���ͤ˽��ȷ���̿�������˥塼�������ܤǤ���줿�������Υ��åץ뤬�郎�Ҥ��±���Ϣ��ƹԤ����Ȥ�������Ԥλ��¤ʤɤ����������ڿ�����δ������������쥯�Ȥ˶�Ĵ���줿��ƻ���ƤˤʤäƤ������Ǥϼºݡ��ڿ�����ϰ���ˤȤ�����ʹ٤ʤΤ������������ڤ��Ƥߤ������ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2007/06/22�� �������Dz趦Ʊ����֡���β��դ�������ܡ������ؤδ��Թ�ޤ� 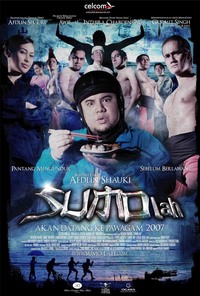 ����̡��䥢�˥ᡢ�����ץ졢���饪���ʤ����ܤ�ȯ�����Ȥʤ���������˹����ä�ʸ���Ͽ������롣�ۥ顼�Dz�⤽�ΤҤȤĤǡ����դ���Ȥʤä��Τ����Ľ��״��ĤΡ֥�סʣ�������ǯ���ʡˤǤ��롣���θ塢�ƹ�����Ǥ�����졢�ּ���ʱ��ꡧ����å��ˡפ��м�Ť�����줫��ʱ��ꡧ�������������������ˡפȤ��ä����ʤ����ӽФ��Ƥ��롣�ʥ�������ס��롦�������ˡ�2007/06/19��
����̡��䥢�˥ᡢ�����ץ졢���饪���ʤ����ܤ�ȯ�����Ȥʤ���������˹����ä�ʸ���Ͽ������롣�ۥ顼�Dz�⤽�ΤҤȤĤǡ����դ���Ȥʤä��Τ����Ľ��״��ĤΡ֥�סʣ�������ǯ���ʡˤǤ��롣���θ塢�ƹ�����Ǥ�����졢�ּ���ʱ��ꡧ����å��ˡפ��м�Ť�����줫��ʱ��ꡧ�������������������ˡפȤ��ä����ʤ����ӽФ��Ƥ��롣�ʥ�������ס��롦�������ˡ�2007/06/19��
�⳦�ͤ����衦ʿ�´Ѥ��ɤ�����ά�����ǧ������¼�ľ�¢���¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� �������ܿ��������Ϸ�ˡ������������ݻ������︢����ǧ�ˤ��������������ΤǤ�������ܡפ��ܻؤ��Ƥ��ꡢ�����кѳ��Υ�����Ǥ���⳦�ͤ�¿����ٻ����Ƥ��롣���������κ⳦�ͤ������ɤΤ褦�����衦ʿ�´Ѥ������Ƥ���Τ����ۤȤ�ɸ���뤳�Ȥ�ʤ��ޤޡ��⳦�ˤϡַ�ˡ��������פ������Ȥ�����������ޤäƤ��롣Ⱦ߷������غ⳦�ͤ�����ǧ����¼�ľ�¢�����찡����٤ϡ����ܳ������Υ�����Ǥ��ꡢ���찡�����٤���¼�ľ�¢�Ȥ����⳦�ͤ������ɤΤ褦�ˤ��Ƥ��������ά������ä���ǧ������ʿ�»ָ��ؤ�ž�����Ƥ��ä��������פ��Ƥ��롣Ʊ�����꤬����˺⳦�ͤ����衦ʿ�´Ѥ�ͤ��롣��2007/06/16�� �ַ�ʼ��פ���Ĥ˻�ä������⡡���ˤ���̱�ƻ뤬�Ϥޤä� ����������ϤȤ��Ȥ������ܷ��ʤߤΡַ�ʼ��פ���Ĥ˻�ä��褦�������������ܶ����ޤ����ꤷ�ƥ�ǥ����˸��������֥��饯�������ɸ����Ф���������Ϥ�ȿ��ư���פʤɤ��ꤷ��Φ�弫���������ʸ��϶���٤����Ƥ���������ƻ�ܸ��Σ��������Ρ��Ŀͤ˴ؤ���ӥ�ޤ������ֱ��ʤɤξ��������ڡ�����ʸ�����˾ܺ٤˽�Ƥ��롣���������־���������פ���̳�ϡ����������̩�ݻ��Τ��������δƻ롢���߽����к��������ɤ��ߤƤ⤽����̳��Ķ���Ƥ��롣ȿ������ʿ�¤��ʤ��뽸���ǥ�ʤɤˤϡ�������Ρ֥��ѥ��פ�ɬ����äƤ��롽����̱���ַ��פ˴ƻ뤵������ˤʤä��Τ����ʲϹ��ءˡ�2007/06/07�� �ƹ������κ����ϲ�ǽ�������饯ű����¤ʤ���ͽ�����̲���طʡ����ɰ�Ϻ �����Ĥ��ˡ�����ꥫ��̱��¿����ȿ�Фˤ�餺��̱���ޤ��֥å��������Τ˶����ơ���������ͽ���Ƥ������Τμ�ĥ�̤ꡢ���饯����η���ű��δ����դ��ʤ����ƵIJ���̲ᤷ����̱���ޤϡ����η���ͽ�������˥��åȤ��뤳�Ȥ����Ū�ưפ˽��褿�Ϥ��ʤΤˡ��Ǥ��롣�ʤ��ʤΤ������Τ褦�ʥ���ꥫ�����������ϤɤΤ褦�ˤ��ƽ��褷��������Ѥ��뤳�Ȥϲ�ǽ�ʤΤ�����������2007/05/27�� �٥����ꥢ��ؤ�����ʤ���ʹ����ܤˤ�����ڿ�����Ԥζ�Ǻ �������ܤ���ʹ��ͣ�졢�٥����ꥢ��ʺڿ�����ԡˤǤ��뤳�Ȥ����Ķ�����ʤɤ��Ф�������Ū������ΰ�ĤǤ��뤳�Ȥ�����ʤ�������٥����ꥢ����ƹ�ͱѸ춵�դ����ܤǤζ�Ǻ����������������Υ����֡������ȡ�The Foreigner�ˤ��֤��Ƥ��롣�����Ʊ�����Ȥ���Ƥ�Ҳ�����ʸ���ȥ٥����ꥢ�������ͤ������ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2007/05/08��
����Ϥ�Ϥ�ΤƤ��ޤ�������ξ���Ǿ�˥��뤫��䴸�ι�ȯ�����¸���ͺ ��������ϰ����Ѥ�ä�����Ǥ��롣����Ҳ�Υ�����������֥å����������ΤȰ������ܼ�����Ф�����˾���Ϥ����Τǡ������Ȥ��Ƥ����˾Ҳ𤷤��������μ�ݤϡֿʹ��ͤϥ������������ȻפäƤ������������Ǥ�ʤ��餷�������ξ����Ǥʤ��Ȥ����ϡ��ƹ����˵�ޤǤ�ʤ�����ʷ����Ϥ�ԻȤ��ơ�����������˲����ɤ�����Ǥ��ꡢ��������ܤ��ɿ路�Ƥ��뤳�ȤǤ�������ξ���Ǿ�¡�����Ϥ�Ϥ�ΤƤ��ޤ��פȰ䴸�ΰդ�ɽ���Ƥ��롣����Ϲ����ʹּҲ�ؤΡ��ä�����ξ���Ǿ�ؤΰ��ι�ȯ���Ȥ�ʤäƤ��롣��2007/04/29�� �ʤ����������Τ����������³�˸Ǽ�����Τ�—���ꥹ�ȶ����ɤν������ۤȤδ�Ϣ�����ɰ�Ϻ ������������ǯ���������ǡ��ƹ�̱�ϥ��饯����ȿ�Фΰջ֤�ɽ���������ˤ�餺���֥å��������Τϴ�����������³�˸Ǽ����Ƥ��롣��ˡ֥���ꥫ������ռ���ʿ�±�ư��ʿ�·�ˡ��(��������/��/����)�ʤ륳���ˤ����ƥ���ꥫ�θ��ߤ���������Ԥ��Ƥ�������—�ä˥��ե��˥�����ȥ��饯���ˤĤ��Ƥ����ΰռ���ư�����Ĥޤ�ǵ��������������ϡ��ʣ���������ȡ��������Ȥʤɤ����׳����ռ����ʣ��˥����饨��Υ������˥��Ȥˤ�륢��ꥫ�������������ʣ��˥��ꥹ�ȶ����ɤν����ռ��λ��ĤǤ��롣�Ƥӡʣ��ˤ���夲�Ƥ⤦�������겼���Ƥߤ��������ܤγ�����ˡ�����ꥫ�Τ�뤳�Ȥ�ͣ���������ɽ����뤳�Ȥδְ㤤�˵����Ĥ��������ơ���ˡ����ꤷ�ƤޤǤ��Τ褦�ʥ���ꥫ�ȹ�ư�ˤ��뤳�Ȥ������ܤ����ܰդ�����˴�������������������ߤ�����ǰ�ꤹ�뤫��Ǥ��롣��2007/04/29��
�ʹ֤ι��������ʵ�ư�������⳦�ͤȴ�ȿͤδ��̤κ����¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� ����ī����ʹ�ʱ���̭���ԡ���������ǯ��������աˤϷкѾ����ʬ��ǰۿ���ľ�ھ�ȤǤ��ä��뻳��Ϻ��ʣ�����Ф��µ�ˤ����ǡ��⳦�ͤ�β��۵��������ý��������Ȥ�������μ�ݤϡ����κ⳦�ͤʤ�ֿʹ֤ι����פΤ���˹�ư���٤��������δ�ȿͤϡַʵ�ư���פ�������ˤʤ������褢��٤��ַбļԤλ֡פϤɤ��عԤä��Τ������뻳����䤤�����Ǥ��ä���Ʊ���бļԤǤ⡢�⳦�ͤȤ���ɾ������뤿��ˤϡ����̡ʤ����ϰ̤ˤդ��路��ǽ�Ϥ�����ˤ�����äƤ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ�����������ξ����������ߤ��������̤�˳�����Τϡ������δ�ȿͤˤ����ʤ������뻳ʸ�ؤδ�Ĵ�ǤϤʤ��ä�������2007/04/19�� ������Ȥ�������Ū�����ҡפ������ϲ�ǽ�����ϵ�ȿ����¸³�Τ���ˡ����ɰ�Ϻ�ʲ��ؼԡ� ����R.Dawkins�������Ϥ������Ū�����ҡפȤ�����ǰ�����롣����ϰ����ҤȤ�����Τϼ��ʤκ������Τߤ��ɵ᤹������Ū�ʤ�ΤǤ��ꡢ����ˤ�äƤ��٤Ƥ���ʪ�ʲ���¿������ʪ�ε�ư�����������Ȥ�����ΤǤ��롣�������ʪ�δ���Ū���ʤǤ��뼫�ʺ������������ʤ�¸�ߤȷ�³�ˤȤä�ɬ�ܤǤ��뤳�Ȥ˴�Ť��Ƥ��롣���ʺ��������ʤ���С�������ʪ�ϻ���䤨�Ƥ��ޤ�����Ǥ��롣���ʤ������³������ʪ��¸�ߤ��ʤ��ʤ롣�������äơ������Ҥ�����Ū�ˤʤ餶��ʤ��������������Ҥ��Τ�Τ����ռ�Ū������Ū�Ǥ���Ȥ�����̣�ǤϤʤ������ߤμҲĶ������¿���ϡ�����Ū�����Ҥ�������פʤ��Τ��ɵ�˵������롣��2007/04/12�� �Х������ݡ���˿ʽФ����ᥤ�ɵ��㡢�ӥ��ͥ��ˣ�ʬ������ ����������ո���ȯ�ͤ��Ϥˤ����ᥤ�ɵ�����濴�Ȥ����ᥤ�ɡ��ӥ��ͥ�����������ϰ�ˤ���äƤ��롣���ݡ���䥿�����Х��˥ᥤ�ɵ��㤬��Ź�����ΤϤ��ΰ�����������ǥᥤ�ɵ����ᥤ�ɡ��ӥ��ͥ���ʬ�Ϥ��ߤƤߤ����ʥ�������ס�����������ˡ�2007/04/10�� �⳦�ͤ��ʳ��٤�������롡�����������ָ�����ӥ����� ���¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� �����Ƕ�֤��ͤ���⳦�͡פȤ�����ɾ��������ĤĤ��롣��ȿͤȤ��Ƥ�Ω�줫��ӥ��ͥ����ȶ����϶����Τ���λܺ������ܤˤ��ͤ��ꤹ��Ȥ�����̣�Ǥ��롣Ʊ���ˡ֤�����⳦�͡פȤ⤤���롣¿���ι�̱��Ƨ����ˤ��ƴ�����פ��ɵ��;ǰ���ʤ����Ȥ����ۤɤΰ�̣�Ǥ����������줾����̤��ü����Ŧ���Ƥ��뤬������˲ä��ƻ�ϴ�����ϩ��������ִ������⳦�ͤ����פȸ���������������ˤդ��路���ʳʤϤɤ��ء����Ȥ����ۤ������ĤΤäƤ��롣�⳦���ܻ������ܷ���Ϣ�ʸ�����ڻ��ײ�Ĺ�ˤ�����ǯ��ö��ȯɽ�������蹽�ִۡ�˾�ι����ܡסʸ�����ӥ����ˤ��ɤߡ����θ��ư�������פ���ȡ������������ݤ���������2007/04/08�� �ּ�Ĺ���ʳʡפ������ϡ��饤�֥ɥ��Ҷ����˼·�Ƚ�衡�¸���ͺ ��ʩ���кѽΡ� ����ʴ���軻�����������פ�ӲԤ�����������줿�Ҷ������饤�֥ɥ������˼����ȼ·�Ƚ�褬�����Ϥ��줿����Ȥ��Ⱥᡢ�Ծͻ��ϣ�������ǯ��ΥХ֥���夫���䤨�뤳�Ȥ��ʤ�������������Ƥ���Τϡ��ִ�Ȥ��ʳʡס��ּ�Ĺ���ʳʡפǤ��ꡢƱ���˴�Ȥ�ɤ��ߤ������ɵ�����餻�뼫ͳ�Ծ츶��������Τ�ΤǤ��롣��2007/03/25�� �ʤ����ܿͤ�ȿ��ߤ������Ϥ��ʤ��Τ����طʤ˸������ꡡ ������������˵�����������������ݤǤβкҤˤ��建ģ�Ϥ��θ塢��ɹ�ΤǤ�Ĵ�������ߤ���ꤷ������ɹ�Τ˶ᤤȿ��߹�Ǥ��륪�����ȥ�ꥢ��˥塼�������ɤˤȤ������ߤϴ��ޤ���Ƥ��뤬�����ܿ������λ�˴�λ��¤⤢�ꡢ��֤٤��˥塼���ǤϤʤ����ޤ����ܤ���ߤ˴ؤ���ͤ�����Ū�˲���櫓�ǤϤʤ�����Ƥˤʤ�ȺƤ����ܤ�������Ĥ���ɹ�Τˤ�ä���뤳�Ȥϳμ¤���¿���Υ������ȥ�ꥢ�ͤ�˥塼�������ɿͤϤʤ������ζ���ȿ��ߤΥ����ˤ�ؤ�餺�����ܤ���ɹ�Τ���ߤˤ�ä����Τ����������ȼ���Ƥ��롣��������ᤰ�äƥ������ȥ�ꥢ���˥塼�������ɤγƻ�˱�ʸ�Ǵ�Ƥ���ɮ�Ԥε������ݤ����ܸ�Ǥ�Ҳ𤹤롣�ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2007/03/22�� �߹��ʤᡡ�ַ�ǰ��ƻ�פ˷礱���̱�λ��� ���������ᤫ����ʤ���߹��ᤰ�ꡢ����ǥ����ϡֱ߹��͢�д�Ϣ��Ȥμ��פ˷�ǰ�פʤɡ����Ѥ�餺�߹��ž���뤿�Ӥˡ����������̱����������פ�⤿�餹���Τ褦����ƻ���֤��Ƥ��롣�Ϥ����Ƥ����ʤΤ���������������Ĺ���夫�飱������ǯ�����ޤǤϡ�͢�д�Ϣ��Ȥμ��װ����ϴ�Ȥ�Ư��ϫƯ�ԤˤȤäƤ��¶�������ʤ������פʺ����˳Τ��ˤʤä������������֤����ʤ�Ķ���פι��ʵ������ȤϹ���פ�夲�ʤ��顢ϫƯ�ԤؤΥ٥������ϣ��������߰ʲ���ϫƯʬ��Ψ��������³���Ƥ��롣�Ǥ���С���̱�ˤȤäƤϥ��������ʤ�Ϥᡢ͢���ʲ��ʤ��㲼������ι�Ԥγ�´��ʤɤ����ޤ��߹⤳�����ޤ��٤������ʰ��Ρˡ�2007/03/22�� �ष��������ǽ�β����������Ȥ��٤����ϵ岹�Ȳ����������������ɰ�Ϻ �����⤦��������ϵ�������;�Ϥ��ʤ��ۤɡ��������Ϥä��ꤷ�Ƥ���Ȼפ��Ƥ��롣�Ͱ�Ū���ӽФ���벹�����̥����ʣ�����ú�Ǥ���¾�ˤ�����Ȳʳ�Ū��Ω�ڤ��줿�������롣�ʳ�Ū�ˤ��Τ褦�˷�������Τ������Ȥϡ��ʳؼԼ��ȴ����Ƥ��Ƥ⡢����Ū�ˤ��������Ť餤ʷ�ϵ��ǤϤ��롣�伫�Ȥϡ�������ú�ǤοͰ٤ˤ������ϻ��¤Ǥ��ꡢ�ϵ岹�Ȳ��ˤ������٤αƶ���ڤܤ��Ƥ��뤫�⤷��ʤ���������Ϥ����ˤϤʤ��Ƥ��ε����˾�ħ��������γ�ư�ʻ��ȡ��������ˤˤ��β�����Τۤ��˽���������ȹͤ��Ƥ��롣�����Ƥ�������Ϥ����̤�����������٤��Ǥ��롣�����ܡ��££äΥ����ͥ룴�ǡ���Great��Global��Warming��Swindle��GGWS�ˡפʤ벹�����̥������GHG�ˤ�Ű��Ū����Ƚ�������Ȥ����ä��Τ�ˤ��������⤦���ٵ������Ƥߤ���������ϡ����롦�����Ρ����Թ�ʿ��¡���inconvenient��truth�ˡפ��б������ΤǤ��롣��2007/03/19�� ����Ǥ��ޤ��͡����ޤ����ͨ������������֤��̤���ˡ��¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� ��������ǯ�ʾ���ΤΣ�������ǯ������ܤ�����ǽ��뤷�����ο�ά����ˤ������֤��ޤ��͡����ޤ����͡פ��äǤ��롣���褬����äƤ��顢¿����̱���ϡ֤��ޤ���Ƥ����פȴ��������Ǥϰ���ï�����ޤ����Τ��Ȥ����ȡ����ѵ��ʳ�����Σ�������ǯ�ᾼ�£���ǯ�����������μ���ˤ�跺���줿�������Ȥ��Ȥ����Τ���Ĥ������Ǥ��롣����Ǥ����ʳ��Ϥ��٤Ƥ��ޤ��줿�Τ��Ȥ����ȡ������ǤϤʤ������ޤ��ͤ˼���ߤ���¿���οͤ������ΤǤϤʤ����������Ǥʤ��������Ͽ�ԤǤ��ʤ��Ȥ������꤬��夷�Ƥ��롣���פʤ��Ȥϡ������ñ�ʤ����ʪ��ǤϤʤ����¤��ܲ�Ʊ��������֤��ĤĤ���ΤǤϤʤ����Ȥ����ưפʤ餶���äǤ��롣��2007/03/04�� ���ˤʤ��˺�����פؤ��ƹ������ʤδؿ������ɰ�Ϻ�ʸ��ƥ���˥������綵���� �����ץ��ץ�Υ�����ʤ����ϡ������åȥ��ɤβʳؼԡ��������ॺ���֥�å��ˤ�äƣ�������ǯ���ȯ�����졢��찵�����Ȥ��ƹ����Ѥ����Ƥ����ȯ���ԤϤ���ˤ�꣱������ǯ�Ρ��٥���ޡˡ����줬�Ƕᡢ˺�����Ȥ����Ѥ�����褦�ˤʤä����ȥ���ꥫ�ã£ӥƥ�Ӥ���ƻ���ȡ֣���ʬ�פǡ���ǯ�������������줿����ƻ���줿�Τϡ��Уԣӣ�(��Post��Traumatic��Stress��Disorder)�ɾ��ηڸ����Ѥ���������������Ǥ��뤬�����ȤκǸ�˾����������ڤ��줿���Ȥ����ѵ��ˤʤ롣����ϡ��ƹ������ʤ��������˶�̣���Ƥ���ȤΤ��ȤǤ��롣��2007/02/26�� ���ߤ���������ž����ʩ���кѻ��ۤ�Ω�ä� ���¸���ͺ ��ʩ���кѽΡˡ��������������������������������� ������ϣ�������ǯ������������ʸ����ۡ����������ϻ���ڡˤdz����줿�֥������Х른��ѥ����̸����ס��Ʋ��������β������Ϻ����Ĺ���šˤǡ����ߤ���������ž����ʩ���кѻ��ۤ�Ω�äơפ��ꤷ�ƹ��ä��������μ�ݤϡ��ʣ��˷����ϰ�¸�ɤˤ����ä��ƹ�Υ֥å���������������ɿ魯�����ܤΰ��������϶�����������Ǹ�Ω���ĤĤ��뤳�ȡ��ʣ��ˤ�������æ�Ф��뤿��ο�ϩ�Ȥ��ƽ����������ϩ���������ɵ�ϩ���ؤ���ž�����Բķ�Ǥ��뤳�ȡ��ʣ���˾�ޤ������ܤ�ϩ������Ȥ����ж�ù���ξ����ܼ���˳ؤӡ������Ѿ�ȯŸ�����뤳�ȡ��ʤɤǤ��롣��2007/02/24�� ����ꥫ������ռ���ʿ�±�ư��ʿ�·�ˡ�����ɰ�Ϻ�ʸ��ƥ���˥������綵���� ��������ꥫ�ϡ��������轪λ��Σ���������Ⱦ�ʹߡ����衼���åѽ���ˤ���ʬ�٤��Ȥä��������̱����������Ԥ��Ƥ���������ϴ�ȡ����ܲȤ�Ű�줷�����ܼ���Ծ�кѤγ�ĥ�����¸����뤿��Ǥ��롣���������Ϻ��Ǥ������ĤäƤ��롣�������������ꡢ¿�������衼���åѽ������Ĥ���������ˤ�ä�����������̱�Ϥ�¿�����������������ʤ��ʤä�����Ϫ���ʿ�̱����ϥ��֡��ˤʤä����ؤ�ͣ��Ρ��������Ȥ줿����ꥫ�ϡ����衼���åѤ�ޤ����������ä������ǡ����Ф��δֻ���Ū��Ȥ�����̤��������ܿͤΥ���ꥫ�Ȥ�������Ф��빥���ϡ����δ��˺��줿��ΤȻפ��롣����ϡ������餯�裲�����������Σ���ǯ���餤�δ��֤Ǥ��ä������θ塢��������ǯ��Ⱦ�Ф��餤���顢����ꥫ���Ƹ�����Ϥޤ������ˤʤ롣��2007/02/16�� �ڥ�������褦�ʤ顡�֥졼���β��줿��ȷбġ��¸���ͺ ��ʩ���кѽΡ� ������Ȥ��Ծͻ����Ի���������䤿�ʤ����ʤ�����μ���פ��ڤä��Ѥ����ʤ��Τ����ڥ�����ݥ������ͷ����Τ�������βۻҥ����������Ȥ��ʼ��������Ի�����������Υ��˸�����Ƥ��롣���Ǥ˥ڥ�����ݥ������οͷ���ŹƬ����ä����������������¤����Ƥ����顢�֥ڥ�������褦�ʤ顼�פȤ����������餷�����λҤ�����ʹ�����Ƥ������������Ѥ��ܤ���ȡ�����ȶ��Ź��ŹƬ�˼䤷������ɽ���Ω�äƤ��롣��2007/02/05�� ���������ˡ�ֹ�ȴ���פΤ����ᡡ���ҵ��١ʶ��饸�㡼�ʥꥹ�ȡ� ��������������������ǯ����������ˡ����ܤ�ʿ�¹�Ȥ����礭�����뤳�Ȥˤʤä�����ʿ�¤ʹ�ȡ��Ҳ����������̱�פΰ������ä��������ˡ������������Ʊ���ˡ��ɱ�ģ���ɱҾʤ˾��ʤ��졢������γ�����ʼ���������̳�פ˳ʾ夲����뤳�Ȥˤʤä���������������ȹ硢��̱���Τ�϶������ˡ�ֲ����˻ߡפΤ���������̾�����ǥ⡢������Ǥκ¤���ߤ�֥ҥ塼�ޥ�������פʤɤ�Ÿ������Ʈ�ä�������ǰ�ʤ����˻ߤǤ��ʤ��ä����ֵ������������Ĥä��פȤ����ͤ⤤�뤬����Ϥ����ϻפ�ʤ�����2007/01/22�� ���������λ�³Ū�кѼҲ�ȤϨ�ʩ���кѳؤλ������� ���¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� ������ϣΣУϡֽ۴ķ��Ҳ��ס���ɽ������̱ͺ��˼�ŤΥ��ߥʡ��ʣ���ǯ��������������dz��šˤǡ֣��������λ�³��ǽ�ʷкѼҲ�ȤϨ�ʩ���кѳؤλ�������פȤ����ơ��ޤǹ��ä��������μ�ݤϡʣ���ʩ���кѳؤΣ��ĤΥ�����ɡ��ʣ��ˡֻ�³��ǽ��ȯŸ�פȤ�����ǰ��¿��Ū�����ơ��ʣ��ˣ��������λ�³Ū�кѼҲ��ᤶ���ѳץץ�Σ��Ĥ����̤Ǥ��롣�ʲ��˼���������ޤ�ơ����γ��פ���𤷤�������2007/01/20�� ���ι����������ӥ�ͤ����λ��������������奨��(���ռ��ס� �����������ä������Ǥ��롣�����Υӥ�ͤˤȤäƤ⤢�꤬�����Ϥ��Ǥ��롣�ӥ�ޤοͤ������ܤ������ä�Ȥ��褦���������ä���ڤ��Ƥ��ʤ��ä�����ˤ϶Ф���伫������äϤ����äƤ�����ɬ������ܤ����Ф�ȤϤ�����ʤ����ۤ��οͤ����ô��Ȥä���硢�ӥ�ͤ��������ܸ���ä��ʤ���Фʤ�ʤ��ä�����顢�����ˤȤäƤ���Ϥʤ��ʤ��ह�����������Ͽ��ۤ��뤳�ȤϤʤ������Ӥʤ�ܤ����Ф뤳�ȤϤ狼�꤭�äƤ��롣����ǤⱿ�ΰ����ͤ⤤�롣��2006/12/29�� �֤��Τ��פäƤʤˡ����ϵ�Τ��Τ������ˡ��¸���ͺ ��ʩ���кѽΡ� ������������ǯ��ޤ��ϵ嵬�Ϥ�¿���Τ��Τ���̵���ˤ�ä��Ƥ��ä�������Ȥ�����ȸ��Ϥˤ��˽�Ϲ٤ˤ�äơ��絬�Ϻҳ��ˤ�äơ������ɤˤ�äơ�����Ȥ�����ʹ�Ū�ʴĶ����ǡ�����˼���ο��ζ줷�ߤȶ��ˡ����ΰ����ǡ֤��Τ��äƤʤˡ��פ����Ĥ��줿ǯ�Ǥ⤢�ä�������ơ֤��Τ��פ�ơ��ޤ˹ͤ��롣��2006/12/22�� �����Ѥ����ܤ�ʸ���פ���ϫƯ�Ķ��ȥɥ�ޤ������Ѥ��ھ���ͤ��� ������������ǽ�ͤ������Ѥ�ʸ���פ�ȯ�����Ƥ���Ϥ䡢����ǯ����������������ܤǤϡ����Ȥι�ư���Ф�������������졢��Ƚ���줿����������ǯ���ܤ�³��������ƻ�˲ä������ܤΥƥ�ӥɥ�ޤ����ȥ�ꥢ�Dz��ܤ�������ˡ��֤�Ϥ����Ѥ����ܤ�ʸ���פʤΤǤϡ��Ȼפ���褦�ˤʤäƤ�����Ĺ����ϫƯ�Ȥ���ˤ�뿴�μ䤷�����ھ��ȤʤäƤ���ΤǤϤʤ������ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2006/12/14�� �����äƤ����֤�ä����ʤ��ס������ΤȤ�ä����ʤ��ز¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� ���������Ρʽ�Ĺ����߷���ʹ������䡦�¸���ͺ�ˤβ������β��̿��סʣ�������ǯ����������աˤ��Ϥ������������Τϣ���ǯ������ڸ����ԡ����μ�������Τ��в�������糤�͡����������ɡס�Ź�硦��߷��ͺ����ˤˤơֿ������פ˴ؿ��������ϸ��ο͡������ޤꡢȯ������Τǡ�����ʹߡ����ʡ�����Τ뤳�ȡˤˤޤĤ��¿�ͤʳ�ư�깭���Ƥ��롣����������Τˤ�����֤�ä����ʤ��פ�ơ��ޤȤ�������Ÿ���ŤΤۤ�����ä����ʤ��ز��ȯ�ʤɹ�����֤�ä����ʤ��פζᶷ����𤹤롣��2006/11/09�� �ʤ���ϥ٥����ꥢ�������ΰ��ˤ��ʤ��ϵ��դ��Ƥ���Τ������� �����������饪�����ץ졼���ơ�����ɤ�������˹��������ܤ�ʸ���Ǥ��롣���������ܤ����ǾҲ𤹤뤦���ǡ�����Ȥʤ�������ˡ��¾�ˤ⤢�롣��������ܤ��֥٥����ꥢ��Τ��ʤ�ͣ�����ʹ�פǤ��뤳�Ȥ��������ʤ�ʩ������η���ޤ��С��Τ������ܤΥ٥����ꥢ����ϥ����ǤϤʤ�������������伫�Ȥ��٥����ꥢ��Ǥ��뤳�Ȥ����ܿͤ�������ȡ��ޤ�ǡ��ѿͤǤϡפȤǤ�����������ܤĤ��Ǹ����롣�ڿ���������줺���ɤ�����ϡ����դäѡפ٤������Ƥ�������Ȼ����褦��¸�ߤ餷�����ʥ��ǥ졼�ɡ���¼ůϺ�ƥ������ˡ�2006/11/08�� �ֻҶ�����Ƥ�����������ס�����Ū������������¸���ͺ��ʩ���кѽΡ� �������٤�ɾȽ�⤤���ʲ����餪�ڻ��Ȥ�����ä�����λ��ҤˡֻҶ�����Ƥ������������¾��ΤҤȤꤴ�ȡפ��ꤷ�ơ��ʲ��Τ褦�ʾ�郎�����Ƥ��롣�ɤ�Ǥߤơ��פ鷺�ФäƤ��ޤä������¤Ϥޤ���ʤ��äǤ��롣���εդ��������С����줬�����ޤ��ֻҶ���Ω�ɤ˰�Ƥ�����������פ����Ѥ�ꤹ�롣����ϵ���Ū����������Ȥ⤤����ΤǤϤʤ�������2006/10/23�� |
  |
| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |
| �褯������� �� ���䤤��碌 �� ���ѵ��� �� �Ƽ�ʸ�� �� ����Ǻ� �� �����ۿ� �� ��ҳ��� |